【小説 津軽藩起始 油川編】序章 堪る不満 天正九年(1581)春
目次
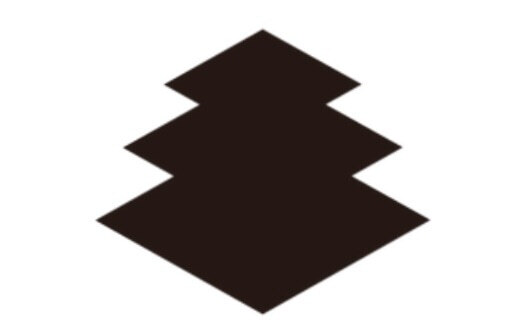
→→第七章←←
嘆き
8-1 想定外
「頼英殿……どうなされました。このような時に。」
慌ただしさを増す城内に入ってきた老僧。さも焦っている素振りで奥瀬の元へ寄る。そして耳元でコソコソと伝えるのだ。
・
「これは寺の小僧が見てしまったことですが、驚かれることなきよう。」
「この際だ。何を話しても許そう。」
・
頼英は唾を呑み、少しだけ善悪に伴う躊躇いこそあるものの……意を決して口を開く。
「山菜取りの小僧が伝えるに、あちらの山の中は兵でごった返しているとのこと。そこで上の者が密かに見に行くと、おおよそ二千もの兵らが山で潜んでおりました。」
・
・
ほう……大きく出たな。
・
「旗印は “錫杖の先”。真ん中には大きな卍の旗もございました。おそらくは……大浦軍。為信は我らを裏切ったのです。」
・
・
……二千。真偽はともかく、兵の過多に疑いこそ残るが……奥瀬は悩んでしまう。
仮に頼英が真の事を申し伝えたとしても、夜襲ならば火など点けずにそのままここに攻めてくればよい。なのに攻めてこない。それとも火をつけて怯えさせようという魂胆ならば、その二千とかいう兵らすべてに松明を持たせればよいではないか。意図が分からぬ。一方でそんな奥瀬にお構いなく、頼英は話をまくし立てる。
・
「そのまま身を潜めて兵らを窺っておると、ありえぬ話も聞こえて参りました。すでに浪岡は寝返り、白取は為信に従った模様。いずれ街道筋からも兵らが攻めて参りましょう。」
・
・
もう訳が分からぬ。
・
・
白取が……。為信を見下していたあの白取が……。ここで奥瀬は己の馬鹿さ加減に笑えてきた。真偽は据え置くとして、もしそれが本当なら……為信にしてやられた。婚儀の話ははなから罠だ。何を私は油断していたのだ。堤氏が暗殺され、よく考えれば為信にとって絶好の機会。大浦の領内で争い事が起きていたので外へちょっかいを出す余裕などないと考えてもいたし、そのような彼らにとって婚儀の話は助け船だったはず。南部氏に属する一豪族として、未来永劫裏切ることなく居続けると……。もちろん奥瀬と大浦が手を結び、白取を浪岡から原別に戻すというのが表向き。ただし南部の大きな権力を後ろ盾に、大浦が内側の不平を抑えようという考えはなかったか。
ここでまさか、為信と白取が繋がってしまった。
8-2 妹を、どこへやった
……だとしたら、勝ち目はない。堤氏の兵力を白取が割いているわけで、さらにそこへ大浦が合力となるならば、我らに勝算はない。奥瀬は至極冷静にそのことを見抜いていた。
・
・
・
ただし為信はよく策を用いる。まだわからないことだらけで……しかも一つの恐れが目の前にある。それは頼英が嘘をついているという可能性だ。頼英、ひいては明行寺が裏切るなどということはまずないだろうが……あの山の明るさには疑問が残るし、すべての話はこの老僧からしか聞けていない。つまりは何とでも刷り込みができるのだ。
そして……ふと思ったことを問いただしてみた。
・
「して……私の妹はどうしている。妙誓はやっぱり為信と戦うべしと申しているか。」
・
その言葉を聞いた途端、頼英の顔が一瞬だけひるむ。奥瀬は見逃さなかった。……これは何かあるぞと踏んで、頼英の言い出すのを待たずして、次の言葉を添える。
・
「やはりこのような大事な場だ。己一人で決めるのは心細いので、妙誓をこの場に呼んではくれまいか。あやつの直にくる物言いはきついが、本質をついておる。ささ、今すぐここへ。」
・
・
・
予想外の言葉に、頼英の目の前は暗転する。もちろん真夜中なのだから暗いのは当たり前なのだが、ここで言い返せないようでは “策” が潰えてしまう……。それだけは避けなければならぬ。避けねばならぬのだが……ある意味で老僧もまた本来の人の道に反することをしている。さらには彼女は奥瀬善九郎の妹なのだから、いまここで斬り殺されかねぬ。
・
奥瀬の疑いはさらに強まり、じっと頼英の顔を睨み……、答えが返るのを待つ。周りは騒がしく動き続けるのに逆らい、傍から見ると二人だけはその場で時が止まっているかのよう。
頼英の頬に汗が伝い、胸倉は吹き出たものでまみれている。それでもそこらの小僧と違うのが彼。なんとか知恵を絞り、口を開くのだ。
「今は恐らく、ありとあらゆることに憤慨し、苛立っておいてでしょう。正しい答えを導き出せるとは思えませぬ。」
・
・
そして奥瀬は、わざと怒鳴る。
「それでもよい。あやつの本音が聞きたいのだ。今すぐここに連れてこい。」
8-3 賭け
妙誓は寺の庫裏にて縄で縛られている。決して痛めつけるためにそのようにしているのではなく、あくまで事が終わるまで黙らすためだ。下手な横やりを入れられては迷惑でしかない。ただそのことを奥瀬様にどのように説明したらいいものか……説明も何も、してはならぬのだ。
・
・
・
はよう、はよう……あいつを連れてこい。……と頼英は目を強く瞑りながら願った。わしの寿命はもういらぬから、あやつさえ連れてくれば、奥瀬様は信じざるを得ない。城門の方へ意識は飛び、今か今かと待ちわびる。
・
もちろん奥瀬にはそのような頼英の心の内は知らない。だがふと城門の方に目をやった。すると……人のせわしなく動くその奥に、何人かの僧侶に抱きかかえられている見知った男がいた。袈裟姿ではあるが、まさしく奴だ。
・
久慈信勝……。
なぜおまえがここにいる。為信が裏切ったとすれば、その弟は直接私を騙した張本人ではないか。縁談の話を……私の息子と為信の娘を結ばせようと勧めたのはまさしく奴だ。奴のおかげで……危機に瀕している。そこで奥瀬はいてもたってもいられなくなり、動かぬ頼英を捨て置いて城門の方へ向かった。そして信勝を前にして……強く頬を殴った。信勝はそのまま崩れ落ち、地べたに膝と手を付き、ひたすら涙する。奥瀬はそんな彼の姿を見て “何事か” と思い、さらにわけがわからなくなってしまう。どのような言葉を吹っ掛けるべきかわからぬし、果ては困惑したまま彼に付きそう僧侶へ顔を向けた。
すると僧侶が言うには
・
「私は浪岡へ移った法源寺より参りました。明行寺の求めを受け、久慈信勝様をお連れいたしました。」
・
元々油川には三寺あり、浄満寺・明行寺・法源寺の三つである。浪岡が再び南部氏の勢力下に入って以降、津軽郡代による統治の一環として天正十年(1582)に法源寺は油川より浪岡へ移転していた。頼英は策のため密かに法源寺と接触。奥瀬善九郎の説得のために……奥の手として久慈信勝を連れ出せはしないだろうかと画策。沼田祐光の話では久慈信勝も一種の被害者、悲劇の人。そこで頼英は賭けていた。すべてを知った後ならば……動いてくれるだろうと。彼の清い心ならば、なんとかして戦は避けたいと思うはず。いや、思わねばならぬのだ。
奥瀬善九郎という男は、山の松明だけでは企みを見抜いてしまうかもしれぬのだから。
為信方の者らは……あからさまに彼を避けて動いていたので、独りぼっちで漂っていたところを法源寺の僧侶らが必死に説得し、油川へ連れ出すことに成功した。もちろん為信方は浪岡と油川の間の道を封鎖しているが、明行寺の者と名乗れば不審がられることはない。
8-4 我が身は、なんとでも
奥瀬善九郎と法源寺の僧侶が目を見合わせて戸惑っているとき、突如として久慈信勝は叫んだ。
・
「すべて私が悪いのです。私が誑かしたも同じ……ひたすら南部と大浦の和を願い、精進して参りました。しかしこれほど報われぬ事がございましょうか。」
・
目には涙、次第に鼻からも水が垂れ、ただしそのようなものはお構いなしに、信勝は叫び続ける。
「白取と大浦を仲良くさせようと結ばせてみれば、いつの間にか白取は大浦の手駒に成り下がり。奥瀬様と大浦を結び付けようとすれば、悪巧みに利用される……。こんなにコケにされて、叫ばずにおれましょうか。」
・
そして信勝は奥瀬の黒い袴を掴み、必死になって訴え始めた。
「私は罰せられてもよいのです。ただ……戦だけは避けて下され。私の願いはそれだけでございます。すでに浪岡には大浦軍が入り、油川へ向けて兵を進めていることでしょう。虚を突かれた油川に勝ち目はありませぬ。町を戦火に及ぼしたくないのであれば……ご英断を。」
・
奥瀬から表情が消え、笑いや哀しみなど一切ない。ただただ信勝の顔を見て、さらに近くで見るために身を屈めて同じ目線に座った。そしてそのまま信勝に問うのだ。
・
「お主はこれからどうするのだ。」
こちらへ伝えに来たということは、兄である為信を裏切ったことになる。それを承知しているのだろうか。おそらくは……信勝は切羽詰まってしまい、そこまで考えてはいまい。
・
「どうぞ刀を腹に突き刺して下さい。それが嫌なら首を手で直接お締め下さい。どのような御命令にも従いまする。」
・
・
その言葉を聞いて、奥瀬の顔に表情が戻る。その面構えはたいそう穏やかなもので、戦支度で荒れ狂うこの場所には不釣り合いなものだった。
8-5 油川殿の最後
「私はこれから汚名を進んで受けよう。“奥瀬善九郎” という男は、大浦為信の前に戦わずして逃げたと。」
・
その言葉は頼英や久慈信勝が望んだことであったが、あまりにも物分かりが良すぎるし、奥瀬の心のあり様というものが計り知れない。そんな彼らの想いを察したか、奥瀬は次の言葉を添える。
・
「勝ち目のない戦をやって無様に殺されるのは損だぞ。馬鹿らしくも思えてくる。……ただし収まらぬのが、戦支度をしている将兵らだ。久慈殿、後のことを頼んだ。」
そういうと信勝の肩に手を載せて、二回ほど軽くたたき、まるで後のことを信勝に任せるとでも伝えているかのよう。……つまりは奥瀬に為信の謀反を伝えに走ったとするならば罰を受けざるを得ないだろうが、説得の末に開城させたとなれば話は違う。奥瀬なりの信勝への気のかけようであった。
・
そのあたりの考えを頼英や僧侶らは悟ったのだろう。その場にひれ伏し、その場を去り行く奥瀬の後姿を涙ながらに見送った。そして奥瀬に付き従っていた配下の者らも大将の意を汲み、他の者へ戦支度をやめるようにと指示を出していく。
“殿さまは大浦があまりにも強大で、勝ち目がないことを悟られた。そこで城を開け放ち、将兵と町衆の命を乞うことにした”
“すでに浪岡は落ち、後ろの山々では兵らが屯し、今こそ攻め入らんとうずうずして待っている”
“これより油川は大浦家の勢力下へと収まる。兵が入られるまで久慈殿の指示を仰ぐように”
・
・
そして当の奥瀬は、城の本館へ再び入り、奥まった角にある書斎にて灯をつけ……筆を執る。周りは未だ騒がしいが、心底落ち着いているようで。奥瀬の耳には硯をする音だけが聞こえる。そして妹あてに、文書を認めるのだ。
・
”これから油川の民を、本当の意味で守るのはお前しかいない。よくよく周りの人の意見を聞いて、努める様に”
油川入城
8-6 去り行く舟
……舟は出る。静まり返った海は、ひたすら暗くて濃い青色。ただし漆黒にはなり切れず、奥底が見えるくらいの透明感を持ち続けている。空のように完全に真っ黒になることはなく、人が浜辺を動けば、しっかりと影をうつす。どんな影でも否応なくうつす。
・
波が騒げば音は鳴る。浜辺を歩けば草履と砂が擦れる。たまに貝の破片も混ざっているか。ただしどちらも似たような音でしかない。……油川の浜辺はこのような感じだが、田名部ではどうであろうか。……おそらくは同じだろうが。
・
奥瀬善九郎は舟に乗る。急な話だったので大きな船は用意できないし、奥瀬自身大げさなものを欲しなかった。東の海岸線を伝っていけば南部領。いずれは田名部に付くのだから、わざわざ危険を冒して海のど真ん中へ進む必要はない。小舟で十分。
敗れた将ならば静かに去るべきと、城を出てすぐ浜辺へ向かった。そして元服前の息子と妻を乗せ、後は船頭のみ。ゆっくりと東へ東へと舟は進む。……ただし奥瀬の意に反して一人、また一人と浜辺を歩む人が増える。そしていつしか群れとなり、百人、二百人は同じ方を向き、同じ方へと歩く。油川の殿様を行かせてはならぬ、戻って来いよと叫ぶ者もおり、海に浮かぶ舟へと涙するのだ。
奥瀬はこれではならぬと、わざと彼らに見えぬ方へ進めと船頭へ指示を出した。そしていつしか姿は浜辺から見えなくなり……町衆や将兵らはその場に立ち尽くした。
・
遠く遠く、さらに遠くへ……。
残るは名残惜しさ。いつしか朝日は上り、民衆は油川へ帰らざるを得ない。彼らは日々の暮らしがあるし、これからも生きていかねばならぬ。領主が変わってもやることは同じ。
・
……………
・
・
同日明朝、大浦為信率いる三千兵は油川へ入った。今羽街道(現、奥州街道)と大豆坂街道の両方より、西と南から侵攻。途中で ”謎の松明が山で掲げられている” との報があれど、こちらへ誰かが攻めてくるような気配はなし。警戒のために歩みを止めていると、油川より降伏の旨が到着。為信弟の久慈信勝と明行寺頼英の連名にて城が明け渡されたとの知らせを受け、本来行うはずだった夜討ちを中止。改めて日が昇ってから入城する運びとなった。
道を進むと町へ入る。所狭しとならぶ町屋の数々、聞くところによると千軒も連ねているらしい。そこに住まう民衆や他国より商いに参っている者と様々だが、怪訝な顔つきで兵が進むのを睨みつける。
そして目の前には開け放たれた城門。脇に控える将兵。誰もが武器を持たず、大浦軍の城へ入るのを誰も止めない。ただし憎しみを抱いているのは十二分に伝わってくる。
8-7 風当り
油川はどんよりと曇っていて、しかも肌寒い。まともに海風が当たるせいなのだが、決してそれだけではない。なんとも町が静まり返っており、活気はまったくもってない。しかも行きかう人へ顔を向ければ……避けられるか、もしくは睨まれるか。子供らが大浦の兵に近寄ろうとすれば、親が慌てて連れ戻しに来る。……このままで油川を治めることができるのか。
・
城へ入ると奥瀬の兵らが屯こそすれど、大浦兵が城内を把握し終えると、各々家へ帰っていった。……城は湿地帯から引き入れられた簡単な水堀で囲まれており、その中に小高い丘陵に建っている。三つある郭の上にそれぞれ館があり、そこには奥瀬の将兵や侍女らが仕えていただろうが、彼らは全て外へ去った。後に残るは閑散とした建物だけ……。
そこへ三千の大浦兵が我が物顔で入り、畳の上を土足で踏み荒らす。身なり行いの立派な者はいれど、あぶれ者だったり身寄りのない他国者が多いので、銭はないか着物はないかなど容赦ない。……先に侍女らが退いてよかったと言えよう。
・
為信は油川本館の上座に胡坐し、幾人かの心ある者よりこのような現状をきく。しかし彼は止めなかった。これをとめると……跳ね返りが己へ向かう。ここに至る経緯を考えると……下々の者ほど丁寧に扱わねばならぬ。それに今のとことは油川の民衆へ被害が向かっているわけではない。城の中で済むならば……幸いなこと。
・
そして忠言が終るなり為信は立ち上がり、近くにある木の小窓を開けようとする。……少し上へ開けただけなのに、その隙間からは冷たい風が音を立てて吹き付けてくる。次にすべてを開け放つと、音こそなくなったが顔めがけて強い風が直接当たる。……城内に入った時より、風の勢いが増したのだろうか。それともここはある程度高い場所だからか。
・
ただし本当はそんなことを考えてる暇はない。さてと気を入れなおして、次への一手を考え始めるのだ。
8-8 一筋縄ではいかぬ
大浦為信が浪岡と油川を手中に収めたことにより、六羽川合戦以降の混乱後に敷かれた天正七年体制は崩壊を迎えた。これまで浪岡には新たなる御所号として浪岡北畠氏遠縁の山崎政顕を据え、実際の統治を行う代官としての白取伊右衛門。下には三奉行として久慈信勝、浅瀬石の千徳政氏、三戸より派遣された東重康が支えるという体制が六年続いた。しかし再び為信が決起したことにより山崎氏は再び農民に戻り、白取氏は為信の家臣に成り下がった。久慈信勝は周知のとおり。浅瀬石千徳は為信正室のお家柄なので以前のように戻り、残るは東氏……。
事前の調略にて東重康は浪岡より油川へ移っており、奥瀬と大浦との婚儀の支度を手伝っていた。ただし油川城主である奥瀬善九郎は城より逃亡し、重康のみ取り残される形となってしまった。こうなると彼は孤独無縁なので急ぎ油川より退散し、堤氏の治める横内城へ入る。蓬田城や高田城、堤館らの南部側勢力に急ぎ書状を送り、三戸には津軽への直接的侵攻を要請。さらには派閥こそ違えど、奥瀬と個人的に仲が良い平内の七戸隼人にも救援を求めた。果ては油川にくすぶる不満を抱く将兵らにも……手を伸ばす。
まったくもって、油川に入った大浦軍は安心できぬ。そのことは為信も重々承知していた。まず手を打つべきは妙誓尼の扱いである。彼女は奥瀬善九郎の妹であり、これまで民に対して行ってきた実績は計り知れず。彼女の一声で油川の町衆が蜂起しかねない。
本来であれば抗えぬと諦めさせるために、一定の軍事行動を見せておくつもりだった。だが何らかの経緯により、油川は浪岡同様に開城へ至ってしまった。戦わずして落ちるのは素晴らしいことなのだろうが、町衆への威圧にはならぬ。……このことには明行寺全体で関わっていた疑いがあるし、となると老僧の頼英も油断できぬ。もう一つの寺である浄満寺は奥瀬の菩提であるので、今回の事によろしく思っているはずがない。
8-9 事は済んだ
……松明を燈した夜は過ぎ、辺りは再び明るさを取り戻した。そして噂というものは早いもので、明行寺を中心に行われたことが、昼過ぎほどにはほとんどの町衆へと知れ渡ってしまった。この行為はまさしく寺が為信に味方したように見え、事前に侵攻のことを城に教えなかったことも著しき問題である。問いを受けた寺の僧侶らだが……答えに窮した。もちろん町衆の言いたいところは理解できる。ただし彼らは頼英の意図を知っているので、無下に頼英を追い詰めるわけにもいかぬ。かといって擁護するような話をしようものなら……自らの命が危ない。
町衆はなかなか話したがらぬ僧侶らを見て、これでは埒が明かぬと彼らを捨て置き、頼英の下へ参らんと寺の奥へ奥へと向かう。……さすがにそれはならぬと僧侶らは慌てて止めにかかり、それでも奥へ進もうと企む者は……拳をふるった。
奥を見られれば、柱に縄で縛られた妙誓がいる。あれを見せてしまえば……すべてが終わる。何としても防ぎとめるのだ。それとも一番悪手かもしれぬが……城に詰める大浦兵へ助けを求めようか。
・
・
・
時を同じくして、庫裏には頼英を睨む妙誓。師匠より事のあらましのすべてを教えられ、そしてすべてが終わってしまったことも知った。“今すぐ縄をほどけ”と喚くのだが、頼英はもちろん、周りにいる僧侶の誰も縄をほどくはずはなく。そんな状態の彼女を離したら、いったいどうなることやら。般若面の妙誓は叫ぶ。
「師匠は敵に魂を売った。お売りになったのですぞ。いくら民の命を救うために松明を掲げたとて、兄上の説得をしたところで、罪は罪。重たき罪。畜生道に落ちればいい。」
頼英は反論しない。あの時はすでに趨勢が定まっており、奥瀬は為信に敗れることは変わらなかった。言い訳したいことは山ほどあるが……いまの妙誓に利くのは、兄からの文書のみ。懐よりそれを出し、静かに妙誓へ差し出すのだ。
8-10 一目、会いたい
文書を差し出された妙誓。表地の字から兄上が書いたのだということはわかるので、これ自体を疑うことはせぬ。しかし僧侶がご丁寧に紙を横に広げると……彼女は目をつむる。もちろん読むべきなのだが、いかにも見せつけられているような気がして、ならば見るわけには参らぬと思わず抗ってしまった。しかしそれでも……少しずつ瞼は開かれ、勇気を以ってこれと接する。
・
読み進めていくと……今度は己の意志に反して、目の前の文字が見えなくなっていく。目をつむったわけではない。涙で目の前がぼやけはじめたのだ。そして最後まで読み切ることはせず、その場で顔を横に向けて、紙が水で濡れてしまわぬように避けて泣くのだ。
その様を見ていた頼英も、彼女の心を察するに余りある。ただしこればかりはどうしようもなく、もう変えることができないのだ。きっと二度と兄と妹は顔を合わすことはない。そして妙誓は突如としてこのように叫んだのだ。
・
「今すぐこの縄を解け。私も追って田名部へ行き、兄を連れ戻してくる。」
……切羽詰まったような表情。さっきの怒りの形相とは違い、必死に懇願する様はなんとも哀しい。ただし無情にも頼英は静かに首を横に振った。
・
「妙誓。最後まで読みなされ。」
・
読んでしまうのは容易いが、いざ読んでしまえば、これに従いざるをえぬ。それだけは避けたい。途中まで読んだので最後に書いてあることはおおよそ想像がつくし、つくからこそあえて先を読まぬ。決して読むものか……。
それでも読まねば事が進まぬ。ふと我に返れば、私がこの寺の住職だ。私情を挟むのはあまり喜ばしくないこと……そんなことはわかっている。それを言ってしまえば住職を他の僧侶らが縄で縛っているこの状況こそおかしいのだが。嗚呼、怒りもすれば哀しくもなり、憎しみはもちろん、しかるべきものがならぬことへのいら立ち。様々な感情が入り乱れ、思考は複雑に絡み合い、一向に答えは出ぬ。
・
ただしここで、一発の高めの音がすべてを止めた。頭よりはるか上の方を、何かが飛んでいく。
→→第九章へ←←









