https://aomori-join.com/2021/01/19/aburakawa/
Contents
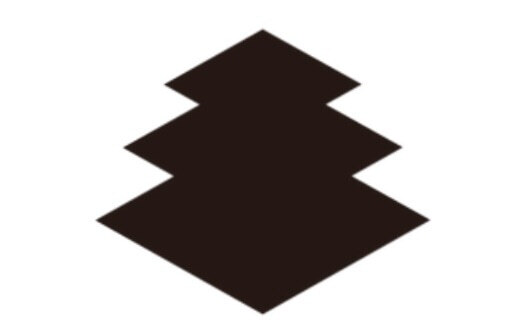
→→第六章←←
禅譲
7-1 申し合わせ通り
天正十三年(1585)三月一日。雪は解け、草木は芽吹く。京都や坂東に遅れ、津軽にも桜が咲き始める頃……。大浦為信率いる “一団” は浪岡へ入境を果たす。これはあらかじめ津軽郡代の堤氏ならびに油川城の奥瀬氏からも許しを得た行動であり、むやみに世を乱すことではないと公に示されていた。これは為信の娘である富子……八歳になったばかりの子供は、奥瀬善九郎の息子……十歳になったばかりの青年へと嫁ぐのである。父である為信も婚儀に参加するために、その進みゆく一団を取り仕切るのは自然なこと。
・
ただしこれは偽り……。
明日には武器を持った荒武者へと化し、油川へ乱入する手はず。
・
為信率いる一団は、白昼堂々と浪岡城を開門させ、再び浪岡は為信の持ち物となった。これは南部氏に再服従して以来、六年目の出来事。辛苦を味わい、それでも津軽衆はかつての意気を忘れず、再び刀を持つことができた。高々と館に掲げられた大きな “卍” の旗。多くの兵の背中に刺されているのは錫杖の旗ざし。晴れ渡る大空に、津軽衆の声が響き渡った。鳥どもが逃げずに一緒になって辺りで明るく騒ぐ姿は、まるで為信のこれからを応援しているかのようでもある。
・
浪岡城大広間にて待ち構えるは浪岡代官の白取伊右衛門。近づく喧騒を聴くと……ここぞとばかりに上座の御所号の身を両手でつかみ、下へと引きずりおろした。その様を見た久慈信勝は慌て、横たわる御所号の隣へ寄るが……次に目に入ったは襖が明けられた先。兄、為信の姿。どのような事態か全く飲み込めず、思わず御所号に問いかけてしまうが……御所号自身は信勝と目を合わせようとしない。“どうしてですか” と信勝は問いかけたが……すると御所号は仕方なしに口を開いた。
・
「もうよい。……これでただの農民に戻れるのだから。」
・
信勝は思わず御所号の体を強く揺さぶり、改めて問いかけた。
「もしや……御所号は知っておいでで。」
・
・
それも涙ながらに。
「討たれて、惨めに死にとうはない。」
7-2 天地が変わる
為信は襖の袂より、広間の奥まった方にいる弟へ大声で話しかけた。
・
「そういうことだ、信勝。」
信勝は御所号を捨て置き、兄為信をまじまじと凝視する……。為信はかわいそうな目で弟信勝を見つめた。兄の後ろには鎧兜を被った武者らが控え、広間へ入る指示を今か今かと待っているようだ。
・
・
……前の方へ信勝が気を取られていると、横より白取がずがずがと近づき、御所号の肩を力づくでつかんだ。白鳥の荒い扱いにも関わらず、御所号は抵抗することなく彼と共に襖の方へ。すんなりと為信配下の者らへ引き渡された。……そんな御所号に為信はわざと恭しく一礼をする。そして口を開いた。
「御所号の地位をお譲りいただき、誠にありがたきことで。あなたのお身柄は、大浦家が責任を持ってお守り申し上げまする。」
・
そんな威勢のよい声に対し、御所号はさぞくたびれた様な声で “あいわかった” とだけ応え、為信の兵らによって見えぬ方へ連れられていく……。そんな様子を見て白取は大いに笑った。
「これで浪岡北畠氏が元に戻るなどということはない。油川も明日には潰える。殿の天下でございますな。」
・
しかし為信は笑おうとはせぬ。キッと白鳥を睨みつけ、存外な行いに白取はその場に固まってしまった。
・
「白取殿。これからは私があなたのお上でございます。あなたの身分や所領は保証いたしまするが……せいぜい励まれよ。」
・
次に信勝の方へ歩み寄り、その場に力失い座っている彼の元へ膝をついた。為信の顔に表情はなく、結局はさまざまな感情こそあれど、どのような顔つきで話し出せばよいのかわからぬのだ。だがその顔は弟にとっては……末恐ろしくみえただろう。
・
・
”おぬしは、よう頑張った。もう苦労をせずともよい”
7-3 力は抜け
信勝は固まったまま。怒りたいのだが……耐えがたい疲弊感、徒労に終わったすべての事が嫌になり、結局は何もなしえずに終わる哀しさ、己を抜きにして事は進んでいく。
・
そんな信勝をよそに、兄の為信は矢継ぎ早に家来らへと指示を出していく。
「兼平、お前は民の動揺を鎮めよ。他国者がむやみに暴れぬよう、商家長谷川にも令をだせ。」
「金は今羽街道を、小笠原は大豆坂街道を押さえ、知らせが油川や横内に伝わらぬように封鎖せよ。森岡は梵珠山から北方に兵を散らばせ、怪しい者がすり抜けて油川へ行きつかぬように手を配れ。」
それぞれの家来らは “はっ” と威勢よく返事し、各々散らばっていく。彼ら全員を信勝は知っているが、忙しいためか信勝にわざわざ触れようとはしなかった。
そして……
「沼田。最後の頼みだ。御所号が落ち着かれたら、館野越へお移りいただけ。土地は用意しておるから、子孫代々そちらでお過ごしになればよろしい。特に当人には謀反の気はない。道すがら殺すなどということは考えぬように。」
・
沼田は少しだけ苦笑し、
「もちろんでございます。殿が御所号の地位を継いだのですから、彼もまた立派な御一門でございます。無碍なことは致しますまい。」
・
為信は頷き返し、沼田はさっそく奥の方へと消えていった。白取も浪岡城内の使用人らへ説明するためにその場を去り、主だった者で残るは為信と信勝……。
信勝は残る気力を振り絞り……兄を睨んだ。兄は真顔を貫き、信勝と相対する。
・
「……もしや同じ奉行衆の東殿を油川へ準備に行かせたのも……この企みのためでございますか。」
「その通りだ。残る奉行はお前と千徳殿のみ。千徳殿を企みには混ぜていないが、こうなってはご納得していただくほかないだろう。」
・
信勝の身体は小刻みに震え……無意識に拳を握っていた。
7-4 喧騒に消え
為信は弟の拳がギュッと握られるのを見逃さなかった。ならば弟は兄を殴るか。いや必死になって堪えているようだ。ただし今こそ絶えてはいるものの……何かの拍子に殴り掛かってきてもおかしくはない。感情を察するに余りある。
・
予想通り、信勝は必死に堪えていた。ただし次第に……殴ったら大変なことが起きるという当たり前の思考はもちろんのこと、疲弊感や哀しさが “殴ってどうなるのか” と訴えかけてくる。
為信も余計なことを言うまいと、弟に背を向けた。そして他の者らへ宣言する。
「よし。後続の兵らが付き、浪岡も落ち着き次第、我らは油川へ攻めかかる。もう少しで日は傾く。闇夜に紛れて山々に潜むぞ。」
・
兵らは途轍もなく大きな声で雄叫びを上げた。為信はその群れの中に吸い込まれ、姿はまったく見えなくなった。広間に取り残された信勝はただただうずくまり、やかましい男どもの声を聞くまいと耳に手をあてる。それでも容赦なく騒音は入ってくるので、気が狂うほかない。そのうち体のすべての力が抜け、その場に横たわってしまった。……畳の上は嫌に冷たく、激しく動く足の音も伝わってくる。しかし、もう動きたくはない。立ちたくはないのだ。すべてを無にしたい。何もかもが嫌だ。嫌だ嫌だ……。
・
倒れたまま、横にさしてある小刀を思い出したが……果ては抜く気力さえなかった。そのまま気を失い、目が覚めたのは全てが終わった後だったという。
・
・
・
さて浪岡に後続の兵らも着き、他国者や有志の士も加わり、大浦軍は総勢三千へ膨れ上がった。めでたい空気に包まれているだろう油川は、備えをろくにしておらぬはず。あとは情報が洩れることなく、静かに囲むこと……。油川へ続く抜け道は、明行寺に頼んである。城の手薄なところも存じておるし、城内にも手下の者を入れている。大浦本隊と戦う前に……すでに決着を見るかもしれない。
為信をたびたび苦しませた奥瀬善九郎……命は明日で最後。首級を上げれば第一の誉れ。
7-5 いた仕方なく
同日、油川明行寺。庫裏の一室で尼の妙誓は正座をし、手前に置く小さな仏様を拝んでいた……。心を落ち着かせようとして、ひたすら無を目指すものの……苛立つばかり。寺に戻ってからというもの、僧侶らは不審な動きばかり。住職である私に何か隠しているかのような、あからさまに目を背ける小僧もいた。
・
そこで本日この時。位の高い者らを集め、問いただすことに決めた。師匠の頼英ばかり当てにしても仕方ないし、私が “住職” なのだから私が全てを担わなければならぬのだ。
昼餉が終わり、未の刻ほどか。呼び出された数人の高僧らは腰低くして、妙誓の待つ一室へと入った……。
妙誓はたいそう不機嫌そうで、ぶっきらぼうに “そこへ座りなさい” と座布団ある方を指さした。とりあえずは言われるがままに各々座すが……もちろん彼らには妙誓の求めるところはわかっている。彼女は苛立ちながら言った。
「ここ最近のあしらいはなんじゃ。何か私がいけないことでもしたか。それとも言えぬことでもあるのか。」
・
高僧らはしばらく黙ったままだったが……廊下に人歩く音が近づいてきたのが分かると、眉をしかめつつ……畳に目を合わせながら頷く。妙誓 は“目を見て申せ” と文句を言った瞬間、閉めていたはずの襖は荒くも放たれた。そこには槍や刀を持った若い僧侶らがおり、許しも得ないままずがずがと部屋の中へ入ってくる。妙誓は思わずその場に立って……彼らから離れようと後ずさりをしてしまった。“何なのだ、お主らは” と叫ぶものの……次に飛んできたのは拳。紫色の袈裟の上から腹に向かって一発。妙誓は口から言葉にならぬ何かを吐き、そのまま気を失ってしまう……。倒れている彼女は数人で持ち抱えつつ……縄で身動きがとれぬように体を縛られ、その一室の角にある柱に結びつけられる。
・
寺でも戦は始まった。
人の道
7-6 仕掛けを
闇夜となり……晴れてこそいるが、月は一切見えぬ。代わりに星々が大いに輝き、すべてのものを照らし出さんとしていた。鳥は鳴かぬし、獣も寝静まる。そんな中で山を駆ける僧侶ら。彼らの背中には太い木の棒の束。しかも上の方には油で湿っている布が巻きつけてある。これに火をつけると……光り輝く松明と化す。ただしまだそうする必要はないので、今は嫌なにおいを放つ “でくのぼう” でしかない。適切なタイミングがあるのだ。
・
……どうやら数人の大浦兵が向こう側より来るようだ。そのことに一瞬驚きはしたが……申し合わせの通り話せばいいのだ。姿こそいまだ見えないが鎧兜で藪を進むので、草木とこすれる音で十分わかる。そしてこの時間に歩いてくる人は己ら僧侶を除いて、大浦兵しか考えられぬ……。
・
やっとで姿形が見えると、互いに目を確かめ合って敵でないことを確認し合う。そうしてからもう少しだけ近づき、伝えるべき言葉を口にした。
「私ども明行寺より参りました。住職である妙誓尼を縄にかけ申した。あとは指示を待つのみでございます。」
大浦兵はしきりに頷き、僧侶に対してこう応えた。
・
「わかった。これで……明行寺で意を異にする者はおらぬということだな。結構なこと。」
次に目が行くのは、当然背中の太い木の束。大浦兵は眉間に皺を寄せたが……答えを聞くなり納得したようで、次の句へ移る。
・
「先導も承る話、まことにあっぱれな話かと存ずる。しかも兵らのために松明まで用意したとは……しかしその必要はない。灯を付けると油川にバレるでの。気持ちだけ受け取っておく。」
・
・
大浦兵はそういうと、元来た方へ引き返していく。僧侶らは彼らの後姿を見て、音も聞こえなくなったところで……やっと胸をなでおろした。故を問い詰められずに済んだことへの安堵。この松明がすべてを成しえる上でのカギとなるのだから……。
7-7 血を流さぬため
「本当にいいのだろうか……。」
・
ある僧侶は言う。すると他の僧侶も悩みつつ、
「すでに浪岡が裏切ると定まっていた時点で、勝つ見込みはないのだ。戦を起こさぬためには、こうするほか……。」
「しかし我らは裏切るのですぞ。あの奥瀬様を。」
「それはそうだが……ほかにやり方あるのか。」
・
口々に不安を語り、それを無理やり押さえつけるように訳を並べては、話すことで己をも納得させようとしている。そんな闇夜ではあったので、特に風が吹くと否応なく寒い。春になりたての東風なので肌寒いのは確かなのだが、なにやら心寒さか底冷えというか……漠然たる恐怖。己らの手で明日の未来は全く違うものに変わる。その一つの担い手として我らが動いているのだ。
・
すると後ろの木々の陰より、まとめ役の僧侶が姿を現した。少しだけ話し声が聞こえていたようで、まずは大浦兵に聞こえることへの恐れを叱咤した。ただし彼もまた恐れを感じているのは同じである。
「我らは何も大浦に尻尾を振って、従ったわけではないぞ。だからこそ今、動いているではないか。」
雪が解けたばかりの山の中。乾ききっていない土の上を歩くので、草履はすでに泥まみれ。油断すると倒れてしまいそうな土壌を動くわけだし、加えて大量の太い木の棒を背中に担いでいるので、疲れを感じずにはいられない。
「大浦に従うだけなら、兵らを油川へ導きさえすればよい。だが我らはそうせぬ。油川に血が流れるからではないか。」
・
・
“あの妙誓尼を住職に据えてしまう頼英様だぞ。羊のように優しい顔をしておられるし、もちろん優しいお人だが、中には雷をもっておられる。……普段こそ出さぬがな”
・
血のつながった者を人質に取られたからというわけでは決してなく、ただただ衆生の命を救うための決断をしたのだ。なにも大浦にひれ伏したのではないし、ある意味で彼らに一泡吹かせてやろうという企みでもある。その意図を明行寺に住まうほとんどの僧侶がわかっているので、皆々頼英の言うとおりに動いている。
7-8 策に対する策
大浦家中の溜まった鬱憤を、奥瀬殿の首級を上げることで解消しようとしている。戦を以って大浦家が再び津軽の王者たることを宣言するのだ。もちろん油川には多くの民が住まい、商都としての機能がある。その重要性を大浦家でもわかっているので、町に手を懸けないために、城へつながる抜け道を寺に案内させようとしている。城の将兵だけを相手すればよいのだから。そして ”武” を見せつけるということは、後々に油川町衆を治めていくためには大切なこと……。あの滝本を追い出した彼らなのだから、抗うことのできない力を示す必要がある。
・
明行寺はその意図を根底から覆す。頼英はそのように決断をした。そこで僧侶らに松明に用いる太い棒をたくさん用意させ、ある策を実行しようとしている。……そのために酷いことであるが、住職の妙誓には一日だけ静かにしてもらう。後からお主にはお主の役目があるのだから、我慢してくれ……。
大浦軍は密かに兵を動かし、いまや本軍は鶴ヶ坂の山中にまで来ているだろうか。我らがいる田沢森まで到着するまでに支度をしてしまい、一斉に仕掛けなければ……
油川の民を避ける気持ちが大浦にあるからといって、民を戦乱に巻き込んでしまう可能性がないわけではない。それに兵の命も人の命と変わらぬ。だからこそ我らは行わなければならぬ。……闇討ちなど、絶対にさせぬ。
・
そのように各々が考えながら支度をしていた。……次第に寺に残る僧侶らはもちろんのこと、他にも銭で雇われた者らが続々と山の中へ入ってくる。併せて二百人にでもなろうか。その多くが油川の事情をそんなに知らぬ行商人や船の漕ぎ手などで、来るだけで銭を出してくれるのだからと深く考えず来た者ばかりだ。
僧侶らは彼らにねぎらいの言葉をかけつつ、最初に ”半分” の銭を渡していく。次には担いできた松明用の太い木の棒を三本ずつ各々に配り、広く長く並ぶように指示を出す。海のある方へ顔を向け、……遠目にはもちろん城が見える。油川の輝きも。
・
僧侶らは入り混じる想いを抑えながら、黙々と支度をしていった。
・
・
そばには土の盛り上がったモノも用意し、すぐに火をかぶせて消せるようにもしておく。間違って木々に燃え移ってしまわぬように。そして一本がダメになったら控えのもう一本。長く明るさを保ってこそ、この策は成功するのだから。
7-9 光を放つ
山の中は油のきつい臭いが漂い、嗅覚が鋭い者はきっと悶絶するだろう。現に船手伝いでやってきたという小五郎という者は吐き気を催し、草の上で横たわっている。……だが彼の苦しみは今しばらく続くだろうが。
太い棒の先には、油で湿させておいた布が巻きつけられている。それに僧侶らは順番に火をつけていく……。さあ光よ、油川まで届け。星の明るさには当然勝つし、かえって月のない夜でよかったとも思える。この否応なき暗さに人為的に灯された火は、山すべてを光源となす。
赤い煙は高々と上がりゆき、嫌な臭いもさらに漂う。これまでの油臭さに加わり、さらには焦げ臭さ、煤を肌にかぶり、衣は細かい黒の粉を浴びる。しかし片手には松明を持ち続けるのが銭をもらう条件。熱さは目の前から伝わるが、我慢してくれ。
・
・
…………
・
・
その明るさは闇夜に輝き、油川の者らは“何事か”と騒ぎ立てはじめる。町には遠地より商売にきた者や船を動かす者が多いので、彼らは結構夜遅くまで起きているので、当然ながら変化に気づきざるを得ない。油川での短い夜を楽しもうと酒で酔っているので、なおさら騒ぎ立てるのだ。すると静かに寝静まる在来の町衆も起こされてしまい、同じく事態に気付く。何も知らぬ者は “何かのお祭りか” と平和ボケして訊くが、夜に何かするなど一切聞かぬ。しいて言えば奥瀬と大浦の婚儀のために、長い行列が夜が明けたら油川へ着くことになっている。その祝いのために我らは準備をしていたし、それ以上のことはまったくわからぬ。
・
・
いや……、それでもありえぬ。為信が戦を仕掛けるなどと申すことは。浪岡に白取氏がいる限り、“為信” がもし裏切っても浪岡で戦が始まるはず。それに奥瀬と大浦は今まさに血族とならんとしているときに……ありえぬではないか。
理解が及ばぬし、思考が停止する。
7-10 看破しこそすれ
ただし奥瀬善九郎は落ち着いていた。他の者が好きなように騒ぐ中、冷静に山の方を見つめる。
・
“ざっと光の多さを考えると、松明の持ち手は二百ほどでも、兵全体では五百ぐらいだろうか”
“油川へ直接攻めてくるのであれば、浪岡にも何らかの調略は済んでいよう”
・
“しかしだな……火の揺らめきがない。夜討ちするならば点ける意味はないし、おそらくその場から動いてもいない”
・
・
奥瀬は全容までわからないものの、何やらおかしいことを見抜いていた。さすがは油川を治める武将である。我の激しい油川町衆が穏やかに暮らせることは、やはり彼の力によるところが大きいのだ。
彼は油川の本館から出でて、周りで騒ぐ兵らにまず “落ち着け” と一括。普段は見せない般若の形相に一同たじろぎ、瞬く間に静まり返った……。そして暗闇の中に、奥瀬の姿は冴える。
・
・
「いいか。夜討ちといえど、相手は五百程度。我らが今から支度をすれば十二分に討ち払える。さあさあ戦の支度をせよ。婚儀の舞台など捨て置け。」
・
そうだそうだと兵らは気を引き締め、急ぎ武器庫へと足をせかす。他にも馬の納屋へ向かう者、女であれば炊事場へ向かって、戦の前に握りでも食べさせてやろうと考える。各々がそれぞれのやるべきことのため、人が城内で入り乱れている。そんななか城をでて何やら遠くへ去る者もいたり……つまりは敵方なのだが、予想外の動きに為信方の間者も急ぎ伝えに走る。彼にとっても山に火を掲げるなど伝え聞いておらぬのだから。
奥瀬は軍配を持ち、もたもたしている者には直接口で指示を出す。かつ全体の動きによどみがないか観察し、そして次には真西の山を見る。……やはり火の揺らぎがない。何か裏にあるぞ……とありとあらゆることを考えてみるが、結論は出ぬ。見えているモノは事実。事実なのだが……あれは何を示すのか。
・
すると荒れ狂う城内へ、小走りに入り込む老僧があり。
・
・
頼英だ……。
・
→→第八章へ←←







