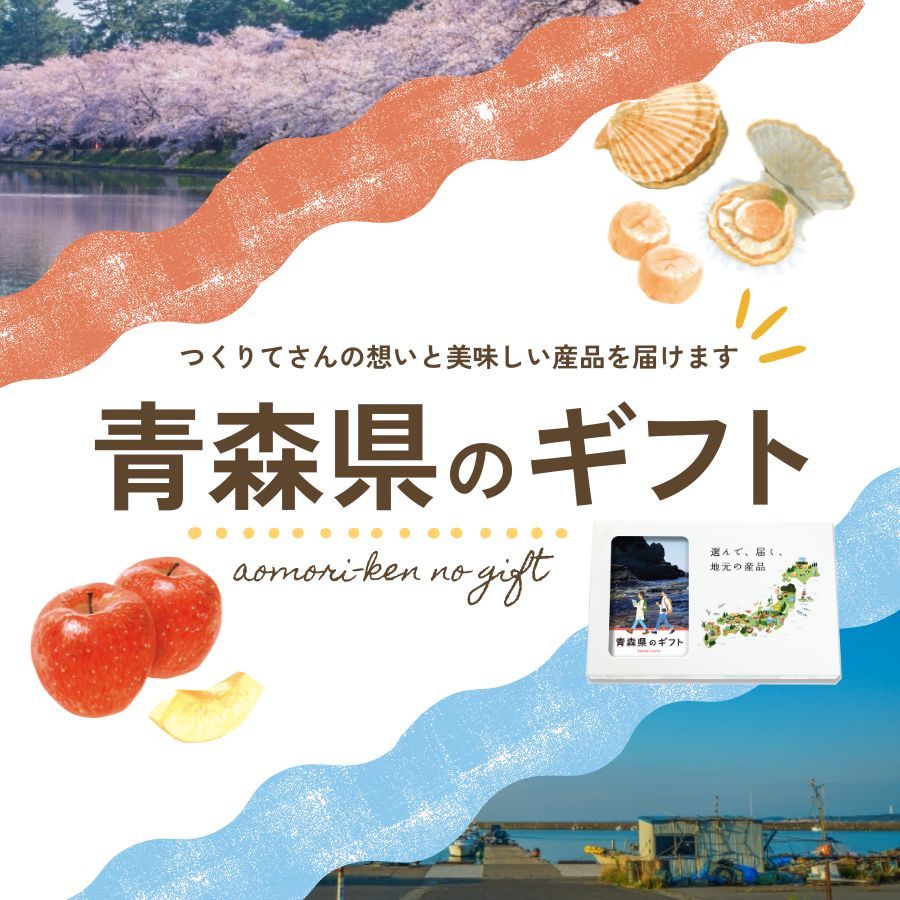【小説 津軽藩以前】 プロローグ 相川西野の乱 永禄十一年(1568)秋aomori-join.com
【小説 津軽藩以前】 プロローグ 相川西野の乱 永禄十一年(1568)秋aomori-join.com

→→最終章へ←←
エピローグ
・
津軽為信の戦いは続いた。
領域を着実に拡大し、民の安寧のために働いた。
一方で為信を”悪”と考える者……滝本重行は徹底して抗い続けた。大光寺城が陥落した後も南部信直を説得したり、あろうことか敵方の安東愛季も巻き込んで為信を幾度となく追い詰めた。特に六羽川合戦において、為信は死んでおかしくなかった。そこを田中という武将が身を挺して救ったと伝えられている。
さらに滝本は津軽家の内側にも仕掛けた。大光寺家臣に……森岡という者がおり、実は津軽家臣の森岡と親戚である。密かに滝本はその繋がりをたどり、病床の森岡信治へ伝え続けたのである。”為信は疑い深し。鼎丸と保丸を殺したのは奴の計画だ”
最初は彼も信じなかった。だが変貌した為信のやりかた……卑怯な戦さの数々。万次党などに代表される下衆どもを用いて敵方の民をたぶらかしたり、家々に火をつけたりひどい有様。さらにいえば為信の近くに座す”沼田祐光”とかいう信用ならぬ人物。これらをみると、かつての大浦家とはかけ離れてしまった。……いや、すでに大浦家ではなく、津軽家なのだが。
……何度も言われると、いっそうそのように思えてくる。するとここで滝本が言う。証拠があると。それは沼田が仲間に送った手紙だった。確かに奴の字。殺害の計画について書き記しているではないか。
森岡は板垣ら近しい者らを集め、出家した戌姫の元を訪ねた。かつての大浦家を取り戻すために、改めて俗に戻り、先頭となる婿をめとってほしいと。
・
・
……だが、戌姫は拒否した。
・
・
”私は主人を不幸にした。いま私のできることは、あらたなる不幸を増やさないこと”
だからこうして戦で親を失った子供らを寺に集めて、僧侶らと共に育てているのだと。これはもちろん子供らのためであるし、なによりも恨みを主人へ向かわせないためである。罪を主人に背負わせないためである。
・
・
森岡や板垣らは閉口した。そのうち森岡信治は病没し、もやもやとしたまま信治の想いは、息子の信元へと受け継がれた。信元も決してこのままではいけないと考えている。彼は板垣らと常々語らい、津軽の地を正道へと直す機会をうかがい続けた。
・
するとどうであろう。為信のやり方に異を唱える者が一人いた。為信の嫡男、信建である。信建は疑問に思った。父は卍や錫杖の絵柄を軍旗に用いる。しかしそれはうわべのことで、神仏を信じている姿を一度も見たことない。同じ人命であろうに、勝つために容赦しない父のやり方……。
ならば、真剣に仏門の教えを父に説いてみようか……いや、だめだ。仏門が命を救う道ならば、なぜ僧侶である乳井らは敵を容赦なく斬り殺す為信に従っている。……ならば、耶蘇会というものが大坂にあるらしい。その教えを研究してみよう。
・
・
為信に反感を持つ者同士。互いに近づくのは自然なことであった。信元らは信建と親しくなり、津軽家中で大きな勢力を持ち始める。
・
・
為信も家中の不穏な空気を察した。そこで関ヶ原への出陣前、先手を打った。信元を殺すよう、小笠原に命じたのだ。……小笠原は老骨を打って、役目を成し遂げた。その仕事を終えると、跡を残さず消え失せる。その後の彼を知る者はいない。
このことに、板垣らは激怒した。為信が遠地へ出陣したのち、仲間らと共に当時の津軽家本拠である堀越の新城を攻撃した。そして見事のっとったのである。かの地は結果的に二度も災いに見舞われたが……大坂の信建が戻りさえすれば、津軽は正道に戻る。
・
・
だが、関ヶ原の大きな戦いは一日で終わった。
・
・
残された板垣らは自害する。最後まで正義だと思いながら、あの世へ去った。
・
・
為信と通じ合うことはできなかった。
・
・
…………
慶長十二年(1607)十月、息子の信建が死去。同年十二月、為信もこの世を去った。
その真相は、為信が信建と二人で酒を呑みかわし、瓶に毒を入れていた。後への憂いをなくすためにとった策であり、己への罰でもあったという。
・
・
…………
・
・
為信の死後、次代を担ったのは三男の信枚と家老の兼平綱則。亡き兄の遺子との騒動もあったが、なんとかこれを収める。民が安心して暮らせるよう、領国経営を真剣に取り組んだ。そして父の偉業も記録に残すことも大切だと考えたので、家来に命じて藩史編纂も始めた。
すると、彼らは言う。鼎丸と保丸のことを書くのはやめたほうがいいと。なぜかと問うと、為信が大浦家を乗っ取ったなどということはあってならない。加えて言うなら戌姫ともずっと仲が良かったとすべきであるし、小笠原に涙をのませて森岡を殺させたというのも酷すぎる。
だが信枚は命じる。ありのまま書けと。家来らは仕方なく従い、完成までもう少し。
・
・
…………
・
・
寛永四年(1627)九月。弘前城天守閣に雷が落ちた。
倉にあった火薬に引火し、爆発音とともにすべてが砕け散った。藩史も同じである。
…………五十年たち、改めて藩史を作ろうという動きがでた。すでに為信存命中のことを知る者はおらず、さまざまな資料を掻い摘んでなんとか作ろうとする。このような経緯があるので、津軽の歴史が正しく伝えられていないのは当然である。
→→続編 津軽藩起始 浪岡編←←