【小説 津軽藩起始 油川編】序章 堪る不満 天正九年(1581)春
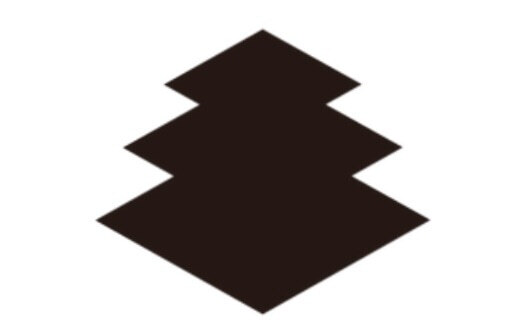
→→第八章←←
再会
9-1 かつてのように
明行寺本殿の壁を、小さくて丸い何かが貫いた。それは両側の木の壁を通り過ぎ、果ては隣にある土蔵の壁にめり込んで終わった。人の頭よりも高いところに残るは丸い銃弾……反対側を見返せば、北隣にある浄満寺本殿の屋根に上がっている武士が数名。手元を見れば火縄を携え、再びこちらへ向けんがために弾を込めている……。憎さのあまり、こちらへ向けて発砲したか。
そして両寺の間を隔てる柵より向こうを垣間見ると……町衆でごった返しているようだった。明行寺が為信に寝返った敵ならば、浄満寺は奥瀬の菩提。町衆のれっきとした味方……。そして彼らは群れを成してこちらへと近づき……なにやら唱え始めた。
・
“モロモロー”とまさに読経の如く息を併せ、こちら明行寺へと“圧”をかけてくる。これは油川独特のモノで、例年一月十一日に船霊祭という航海の安全を願うお祭りがあるのだが、その時に使う掛け声だ。本来は早朝より船頭が家々を廻り、“モロモロ(=諸々のこと、いかがですか?)″ と呼びつけ、家の内側から ”ドーレ(=どれどれ、いらっしゃい。)“と言って彼らを招き入れて酒などを振る舞う風習だ。それを天正七年(1579)の正月、油川に留まっていた滝本重行を追い出す際にその祭りを町衆が利用して、彼を油川から追放したという過去がある。此度は……為信に通じてしまった頼英に会わせろと、もしくは差し出せという意味合いで唱えているのだろう。
・
もちろん明行寺の者が “ドーレ” と返すわけはなく。だがこのままでは……招いていなくとも、柵を越えて寺の中へ入ってくるだろう。そうなれば妙誓が縄で縛りつけられている様を見られるし、我らはきっと殺される……僧侶らをとてつもなく震え上がらせた。早く城に詰める大浦兵へ助けを求めた方がいいのでは……。しかしそれは頼英の意に反する。もし呼んでしまえば……血が流れる。せっかく我らが苦心して大浦軍による夜襲をくいとめ、平和裏の内にことを収めたのに……それを崩してはならぬ。
現に屋根の上からこちらへ銃弾が飛んできているのだぞ。しかし頼英様へ聞いても答えは同じ。ならばどうするか……いや私が責任を持つと、その中でもある程度地位が高い僧侶が言った。顔はたいそう引きづっているし、あとから破門されるかもしれぬ。しかし……そんなことも言っていられまい。
周りに反論する者は一切なし。選ばれた僧侶は急ぎ南側の柵を乗り越えて、油川城へと駆けた。
9-2 理性ではなく、感情。
明行寺の門前で僧侶らと押し問答している者らと、北隣の浄満寺より柵越しに “モロモロ” と一斉に唱えて心を脅かす者ら。彼ら町衆の威勢はよく、続々と人が集まってくる。特に浄満寺にはかつて油川城で奥瀬善九郎に仕えていた郎党らが集結し、その数は五百に膨れ上がってしまった。いくら城主の奥瀬氏に戦う気がなかったとて、彼らは戦いたかったのだ。一泡浴びせたかったのだ。その舞台を失い……油川城は引き渡されてしまったが、ここでなら戦える。不満ある町衆も味方だし、いくら為信でも町衆を敵に回せば油川を治めることはできまいて……。
・
……明行寺の求めに応じて未の刻ほどか、油川城に詰める大浦軍三千兵を割いて兼平綱則率いる五百が寺に入った。門前で僧侶らと喧嘩していた町衆は、蜘蛛の子を散らすようにして逃げる。ただしその中の幾人かはそのまま隣の浄満寺へ駆け込み、さらに寺に立てこもる人数は増した。しかも浄満寺にはすでに町衆らが武器や食料やら、油川を戦いで取り戻すためとばかりに無償で持ち込んでおり、派手に事を起こす気で満々だった。
・
寺の屋根に座る武士は十人ほどに増え、南隣の明行寺へ火縄を向けていつでも放てるように備えている。ただし向こう側に大浦軍が入ってしまったので、もし撃ってしまえば……それは戦闘開始を意味する。それはすなわちで “死” を意味するのであるが、理性が保てるのであれば、寺に立て籠もるなどするはずがない。これまで善政を敷いてきた奥瀬氏への恩情、謀略によって彼を追い出した為信への恨みと憎しみ。町衆の己らが持つ力への自信。行動することの勇気。この場合は勇み足かもしれぬが、感情のまま動いているので、理性など働いていない。それでも若干の思考能力は失われていないと見えて、わざと力を向ける矛先を大浦軍の入った油川城とはせず明行寺としたのは、とてつもなく滑稽な話。結局はなんらかの問題となる行動を起こせば、どこであれ大浦兵がやってくるのは当然なこと。対決するタイミングが若干早いか遅いかの違いでしかない……。
9-3 再会
明行寺を守るために参上したのは兼平綱則の率いる兵五百。主だった構成として本拠兼平村の兵二百と所領田野沢より百。他は野良の者ら二百だ。その“野良”の中には不埒者だとか身寄りのない他国者がおり、あの男も当然の如く混ざっていた……。
その男らの一党は庫裏を偶然にも守ることを任されたので、土足でずげずげと建物の中に入った。そこにいる僧侶らは突如として野蛮な者らが押し入ってきたことに驚いたが、一応は味方であるし止めるわけにもいかない。
ただし誰もが顔を下にして、“私がしたことではない” と言っているかのよう。頼英様はすでにここより離れて仏殿にて兼平様と行動を共にされておられるし……。もちろん大浦軍にとって彼女が縄で縛られていてもなんら不都合なことはないが、なんとなく仏門に仕える身の上としてなにやら不適切な気がしてならぬ。事前に聞き及んでいた話では、彼は同じ真宗とも聞く。さらには石山本願寺に仕えていた者にこの様を見せるとなれば……恥でしかない。
そのような恐れを抱かせつつ、その男 “生玉角兵衛” は野蛮にも草履を脱がずして廊下を歩む。配下の者らもそれに倣って……いや仲間故、同じような考えの者らが集まっているので、自然と同じような行為を取っているのだ。そうして堂々と庫裏の中を闊歩していると……聞いたことのあるような声。あの “キツい” 声はしっかりと耳に焼き付いている。あのように侮辱されては……沽券に関わる。己の威厳をズタズタにされたことは、生涯忘れぬであろう。
・
顔をしかめさせて先を歩くと、向こう側に一人の尼僧。……柱に縄で縛られているのは、まさしく妙誓。あの尼小僧だ。どのような経緯でこうなったかはわからぬが、おおよそ予想はつく。どうせ煩く宣って、他の僧侶らにしてやられたのだろう。……となれば面白い。かつて俺を悪人扱いし追い払った奴が、今や正反対の立場にいる。しかも俺らがこの寺を守るのだから、この尼小僧も俺らに守られるべき立場の人間……。
笑えてくる。そうだ、お前たちも笑えるだろう。そうだそうだ。声に出して大いに笑え。そしてこいつに聞かせてやれ。耳の穴をふさぐのならば、手をはねのけてでも……そうか。そういえば手も縛られていたのだな。相当受けるぞこりゃ。
・
そして野郎どもの騒音を黙って聞く妙誓尼。悔しさのあまり、唇を噛む。
9-4 戦端
……夕方になると浄満寺に籠る敵が勢いづくことを防ぐため、大浦軍は明行寺に詰める兵五百以外にもさらに七百を浄満寺の周りに配置。町衆や奥瀬残党がさらに加勢せぬよう目を光らせた。さらには油川で新たに拠点と使われそうなところを先に抑えるべく、熊野宮に三百。さらには油川よりでる街道筋にも兵を置き、行きかう人の動きを徹底的に監視。こうなると武装を固めた兵らの物々しい雰囲気に、騒がしかった町衆は鎮まりざるを得ない。一方で浄満寺に籠る者らは未だ七百ほどにいるので、あちらの喧騒というモノは嫌でも外へ聞こえてくる。だが次第に……日が沈むにつれ “モロモロ” と唱えなくなったし、いくらか落ち着いてきたか。ただしこれは “戦の前の静けさ” というべきか、変な緊張感が辺りを漂う。弓を握る者の手は汗で湿り、火縄を持つ者は地板を濡らす。
隣接する明行寺と浄満寺共に敷地は1㎢と広いものの、どちらも町の中にある無防備な施設でしかない。同じ真宗でも摂津の石山本願寺みたいな要塞ではないし、火縄を横に向けて撃てば、間を隔てる木の柵を飛びぬけて、向こう側の建物に穴が開く。そこで急ぎタンスや竹束など銃弾避けになりそうなものを両寺の境目に置いていく。……この作業自体は互いに日の明るいうちに済んだようで、暗闇に包まれた今となっては、不気味な静かさしか感じない。
・
そして……戌の刻(午後八時)の頃か。先に手を出したのは浄満寺側だった。屋根に上がったままだった将兵らが一斉に明行寺の仏殿目がけ……一斉に射撃した。今度は最初のようにわざと上を狙おうとはせず、下の ”人の高さ” へ向けて発砲。誰もが驚くであろう爆音。辺りの木々に寝静まっていた鳥どもは慌てて飛び去り、カラスはその汚い声を懸命に鳴らす。雪がやっと解けたばかりの季節なので、後に残る木々には葉などついていない。その哀れな姿は少しばかりの怖さを醸し出した。
上を見れば……夜の暗さよりも黒い鳥が天空を飛ぶ。未だ喚き散らし、……再び元いた木々に戻ろうとすべく辺りを漂うが、再び爆音が当たりに鳴り響いた。これではかなわぬと彼らは西の山の方へ。油川城を脇に見つつ、田沢森、さらには金木や加瀬の方へ飛び去っていく……。
9-5 覚悟はあるか
兼平は仏殿の場外にて兵共に “放て” と掛け声を出す。すると柵の向かい側、浄満寺に向けて三十丁もの火縄で銃撃する。ジリジリと音を立て……皆で火蓋を切れば、弾は一瞬にして飛んでいく。まったくもって夜中であるので、柵ごしにあちらの様子はまったくわからぬ。ただしあちら側からは女子供の驚く声も聞こえるようで。慣れぬ音に怯えているか……しかし手を出したのはそちらだ。覚悟して籠っているはずなのだから……。生半可ではなるまいぞ。戦とはそういうことだ。
・
火縄を打ち終わると、今度は後ろに控えていた弓隊が立ち出で、矢をあちら側に放つ。鉄砲とは違い矢は頭上から降り注ぐので、真正面に竹束やタンスを置いて弾避けにしていたところで、あまり効果はない。外に出ていた者らは急ぎ建物の中や裏に隠れて、そこから鉄砲を撃つなり弓で射るなりして応戦。浄満寺の屋根に侍ている火縄を持つ者ら、続けて明行寺を狙わんと撃ちかけてくるし、ならばと兼平、あれほど狙いやすい標的はないぞと屋根の上を撃つように鉄砲隊へ命令。いざ撃つと瓦によって弾かれ、もしくは粉々になって割れる音が重なって、頭の中に嫌な響きが突き刺さる。加えて互いに矢の行き来は激しく、恐らくは矢の尽きるまでやるだろうか。
・
そのうち浄満寺で勇気がある者は柵の前へ居立ち、乗り越えて明行寺へ攻め入ろうとする。一人が続くと二人三人とイノシシ共が参ろうとするが……彼らにはもちろん容赦なく火縄やら弓矢の餌食になってもらう。それでも同じような者らがまた何人も現れて、こちらへどんどん進み出でる。
悲鳴を上げ、次に声は途絶え、新たに積み重なっていくは屍。それでも意地をみせんと、血を流すことを厭わず、勝つことを信じて攻めていく。大浦兵からしてみたら不気味でしかない。……ただし生玉角兵衛のような真宗の者から見たら、わからぬわけでもないが。もちろん同じ門徒で争うのは心を痛めるし、できることなら避けたい。だが我らには禄を与えるべき仲間がいるし、遠地より連れてきた家族もいる。勝ち馬に乗ることが最上と割り切っている者ばかりだ。そのためにはいくらでも悪事に身を染める。
・
戦は続く。新月の終わったばかりの細すぎる月が天井に上がっても、砲撃や矢の風を切る音は辺りに響き渡る。そんな中、軍配を握り続ける兼平は思う。
……浄満寺は併せて倍近くの兵に囲まれているはずなのに、勢いはあちら側にある。……手ぬるいのは判っている。寺を囲んでいる我らが本気を出せば、一斉に攻め立てれば落ちるのは当然の事。だがそれは……大浦家がこれから油川を治めていくことを考える上で、一番の悪手だ。元油川城兵と共に、二百人ほどの町衆もあちらに籠っている。彼らを殺してしまえば……さらなる恨みを買うことになる。だからこそ明行寺からの反撃はするものの、それ以上のことを避けている。
ただしここで長く混乱が続けば、南部氏がどのような動きをしてくるかわからぬ。……小笠原殿や森岡殿にも相談の上、やるのならやるで早急に決めねばならぬ。
・
はたして我らに、その覚悟はできるか。
まつろわぬ民
9-6 生か死か
兼平の隣にて侍る者。突如として心の臓を抱えて、前のめりに倒れこむ。声をだし最初こそ悶えたが、すぐに何も宣わなくなった。ただし非情なことだが彼に構っている暇はなく、横で構えている兵らは火縄を持ち、上めがけて撃ち続ける。……浄満寺の仏殿の屋根に座るは十人ほどの銃手。未だ何刻にもわたり我らを狙ってくる。特にあそこには大将首がいるぞと敵もわかっているのだろう、兼平周辺を目掛けひたすら弾を放つ。そのたびに壁の陰や竹束に身を隠し、隙を見て反撃する。
屋根の兵の存在は特に邪魔なので、下から上へ狙い続ける。しかしこれでは埒が明かぬと兼平、瓦が割れる音がするばかり。そこで何人かをこちらの寺の屋根に上がらせ、奴らを撃ち落とせと命じる。一方で柵の方を顔を向ければ、こちら側へ乗る越えようと向かってくるイノシシ兵ら。二十人三十人もそこに積み重なっているにも関わらず、次から次へと立ち向かってくる。……真夜中なので血みどろの姿を見ずに済むが、……彼らに “死への恐れ” というモノはないのだろうか。矢も尽きることなく頭上から降り注いでくるし、仕返しとばかりにこちらからあちらへも撃ち返す。互いに悲鳴を上げながら、隣の者が言葉を発しなくなったとしても抗い続ける。わざと目を背けながら、己の腕が真っ赤に染まろうとも、無益にも戦い続ける。
・
……とそのうち、丑の刻ほどになったか。さすがに夜中ずっと戦っていたので、浄満寺側にも疲れがでてきたか。漠然と感じられていた勢いはあまりなくなったように見える。矢こそ飛んでくれど、数は少ない。数が尽きたか……それとも腕が上がらなくなったか。我らもさすがに疲れた。屋根の上にて構える互いの銃手も狙う姿勢こそとるが、そのままでいるばかりだ。うるさい音も鳴りやんだ……。頃合いを見計らい明行寺仏殿の場外で指揮を執っている兼平の元へ、浄満寺を囲む兵を指揮している小笠原が、持ち場を離れて密かに参上した。
自らの使い慣れた火縄を持ち、屋根に上がらせよと申す。
9-7 序盤
ジリリと音を立て……放たれたその銃弾は、向こう側の屋根を目掛け一直線に飛んでいく。その弾はまさしく敵兵の胸のど真ん中を貫き、胴丸ごと細長い穴を開けさせた。一瞬にして気を失い……仰向けに倒れ、そのまま屋根を転げ落ちていく。ガラガラと瓦を鳴らしながら、果ては姿が見えなくなったと思えば、下の方からドスンと鈍い音がする。
小笠原の近くの兵ら、“やった” と威勢よく声を上げるが、小笠原は寡黙なままぶっきらぼうに手を隣へ差し出し……弾をよこせと言わんばかりだ。いちいち火薬と弾をいれる手間こそあれど、慣れてしまえばこれほど強い武器はない。再び小笠原は続けて次の狙いを定め……再び火ぶたを切る。すると当人にとっては当然の如く、再び敵兵に命中する。
・
我らは向こう側にいる敵兵らと撃ち合いをしてきたが、互いに当たらぬばかりで無駄な仕合をしてきた。それを小笠原様ときたら……撃つ数だけ当たる。三発目も同じだった。これでは堪らぬと向こう側では考えたのだろう、敵兵らは急いで屋根から下りようとしているようだ。……これまで十人ほどで狙っていた敵方だったが、まったく誰もいなくなる。火縄こそ撃つことをやめないが、タンスや竹束が控えている所でないと安心できぬ……と思うのが当然。この小笠原の活躍で、明行寺は当分の ”邪魔” は排除できた。であれば次に考えることは……いかに敵方の戦意を削ぐか。
そして詰めていた熊野宮から森岡も参上し、仏殿にて兼平・森岡・小笠原の大浦三家老が軍議を執り行う。だだっ広い仏殿より兵らを外に退け、三人しかいなくなったその建物の内はとても肌寒い。行灯の光を真ん中に置き、ただそれだけの様なので……加えて言うならば奥に座す仏像がこちらを睨んでいるので、緊張感というモノが半端ない。民を疎かにしてはならぬぞと、当たり前のことを当たり前のように訴えかけてくるような……。ただしその民が火縄や槍を持ち、こちらへ戦を仕掛けてきているのだぞ。
森岡は下手な緊張感を無くすため、わざとため息を大げさについた。続いて兼平も小さなため息を。小笠原は……腕組みをしたまま茣蓙に座す。
9-8 考えは一つ
「もちろんこのまま攻めかかれば倒せない訳ではない。ただし、後の事が難しくなるが。」
兼平は二人の顔を窺いながら話す。さすがは為信の重臣だけあって、深く物事を考えることのできる者ら。三人集まれば文殊の知恵とも申すし、何か良い案が浮かぶかもしれぬ。すると森岡が言う。
「油川の町衆は、あの滝本をも追い出したというぞ。この件でしくじれば、油川を治めることができなくなるのは自明の理。」
横で小笠原は静かに頷いた。そして森岡は続ける。
「なれどこのまま浄満寺の件を放置しておけば、見くびられることは確実……誰もが見て正しい手順を踏んで、攻め落とすのがよかろう。」
兼平は相槌をうつ。
「うむ。先ずは降伏の使いを送り、拒否されたら周りより一斉に火縄の音なり矢を浴びせるなりする。そして再び使いを送り……ここでよき回答がなければ、今度こそ攻め込まざるを得まい。周りで見ている町衆が逆らう気を失せるほどに……。」
森岡は思わず口をにやつかす。“同じことを考えているではないか” と申し、次に兼平と森岡は小笠原の方を向いた。すると “仕方なかろう” と一言。
・
もう決まってしまえば、後は殿の元へお伺いに行かねば。三人はそれぞれ持ち場を信頼のある部下に任せ、油川城の本陣に向かう……。城の南に広がる湿地帯より霧が立ち込め、風が偶然にも北に向かって吹いたので、城全体が白く包まれている。その中を馬に跨り、三人は進む。横にわずかに揺られつつ、それを心地いいと感じるか、酔いが回る気持ち悪さと思うかは人それぞれだろうが、この場合……彼らはどうであろう。先の見えぬこの戦い、何を決着とみるか。
霧なればいずれ晴れるだろうが、我らに待つは繁栄もしくは滅亡か。この油川が、試金石となる。
9-9 悪者は誰か
「ならぬ。」
薄暗い城内の広間に為信の声が響いた。ただしこれは浄満寺に籠る兵や民らを殺すなということではない。大浦三家老はただならぬ物言いに押されひれ伏しつつも、これを譲る気はない。……他の家来衆も見守る中、兼平が初めに言葉を発する。
「しかし誰かが責を負わねばなりませぬ。無論、最悪の事態を迎えるなどと決まりこそせぬが……もしそうなった場合、我らが恨みを一身に浴びる覚悟でございます。」
・
これに対し為信は、またも声を荒げる。
「では悪者はお主らか。お主らが勝手にしたこととすれば、町衆は納得するか。そういうわけではなかろうて。」
兼平は異を唱えようとするまえに、今度は森岡が話し出す。
「かといって殿が命じたということにしてしまえば、恨みは大浦家全体に向かいまする。ならば我ら家来衆の誰かが被ればよいのです。そこで我らが被ると申しておるのです。」
・
「許さぬ。私が志を失ったときに支えてくれたのはお主らではないか。そんなお前たちに汚名を着せるわけには参らぬ。」
・
しかし……と兼平と森岡は顔を見合す。小笠原は……腕組みをし、黙って思案したままだ。
「そうだ。私こそ汚名を着るのがふさわしい。かつて噂になったろうに。小笠原殿の娘が多田殿へ嫁ぐのを、横取りしようとしていたとかなんとか。」
・
・
それを当の小笠原殿の前で言うか……。しかもこの場所で。
・
「真か嘘か別として、他にもあるぞ。エゾ衆が襲われるところを黙って見過ごしたとか何とか。義父の息子を計略で殺したとか。……そしてこの度、再び南部を裏切った。まさしく穢れ役は私だ。」
・
広間は静まり返ってしまう。ただし気持ちとは裏腹に夜の闇は今にも抜けんと、外の霧に薄い光が差し込み始めている。この場所ももう少しで明るくなるか……。
ここで一人にやけて笑い出す者あり。三家老の横で侍ていた沼田祐光である。手元に置いてある扇子を開き、わざと口元を覆いながら話し出す。
「ならば……ここは白取殿にでも指揮をとらせるのはいかが。彼も南部を裏切って、此度の戦を起こした張本人ですぞ。どうでしょう、お手前は。」
・
沼田は白鳥へそのいやらしい笑顔を向けた。……急に名指しされた白取は狼狽えてしまい、すぐにモノを言い返すことはできなかった。だろうの……と沼田は彼をバカにしつつ、為信へ体の向きを変えた。扇子は畳の上に置く。
「誰が汚名を被るや噂が悪いなど、一致団結した大浦家の前には論議不要なこと……。これまで殿が行ってきた政治に、領内の民は感謝してもしきれませぬ。自信をもっていいことかと存じます。ただし油川の町衆に対する領主奥瀬の政治も、大変よきものでございました。これを忘れて大浦に尽くせというのは、難しい話……。しかれども大事なのは戦の後。我らがこれまで行ってきたことを油川にも施す。これを徹底するしかございませぬ。此度のことは残念ながら避けようならず。己の頭でも考えつかぬ事。こればかりは無念でなりませぬ。」
9-10 地獄へ入る
日は完全に開け切った。しかしながら霧はさらに立ち込めて、城の辺りだけでなく油川の町の方への流れいき、浄満寺や明行寺の辺りも霞んでいる。加えて空気がひんやりとした冷たい朝。誰もが眠らずに疲れはてており、手で目ヤニを取りつつ、近くに流れる天田内川で顔を洗うのだ。そうして気を再び引き締めて、持ち場へと戻る。次に自分の代わりに今度は別の者が川へと向かい、朝餉を喰らう。……包囲されている側からすれば、このようにはいかないだろうが。
予定通り朝のうちに、大浦軍より使者が浄満寺へ派遣された。戻ってきた使者が言うことには、寺に籠る者らは所詮大将を決めてもいない烏合の衆である。ただし共通の意志のもと動いているようで。はっきりと “従わぬ” と言い渡されたという。昨晩長きにわたり戦った勢いのまま。疲れこそあれど士気は未だ高い。これは絶対に挫かなくてはならぬ……。
・
ならばと霧が抜けた巳の刻ほどか。隣の明行寺ならびに浄満寺を包囲する大浦軍併せ兵千五百は、浄満寺へ向けて一斉に矢を放った。外側から壁を越えて境内へ。止むことのないその矢の嵐に、籠る者らは慌てて建物の中へ避難する。……確かに中へ逃げてしまえば矢に当たることはない。しかし風が揺さぶられる音は中の者らを十分に怯えさせた。いつしか障子は破れ、木戸には何百本もの矢が刺さり、地面には無雑作に落ちている矢の哀れな姿が散らばる。その横には逃げ遅れた兵や民の体が横たわり、すでに声も発せぬ彼らは、生きている者らの心に十分な陰を落とす。
今にも攻めて来るのか、来ないのか……。矢が飛んでくるばかりで来ないようだが……。
”南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏……”
中に籠る者。誰もが口ずさみて、難の過ぎ去るのを待つ。
・
・
そのうち矢の降りやまぬ外を思い、誰かが叫んだ。
”南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、これを何遍となえれば、極楽浄土へ行けるやら”
油川の辻辺で、かつて尼の妙誓が皮肉を込めて唱えていた言葉……。真宗ひいては仏門全体をからかっている。当時はむりやり出家させられたばかりで、非常に荒れていたころだったはず。南無阿弥陀仏を繰り返し唱えるだけで、もしくは経典をそらんじることで幸せになれるのかと、師匠である頼英に生意気にも食って掛かったことがあった。その光景を……この者は印象深く覚えていたのだろう。
・
・
現に我らは攻めたてられて、幸せになどなっていないではないか。死んだところで果たして極楽浄土へ行けるのかと。世の中のすべては……嘘でまみれている。
・
→→最終章へ←←









