【小説 津軽藩起始 油川編】序章 堪る不満 天正九年(1581)春
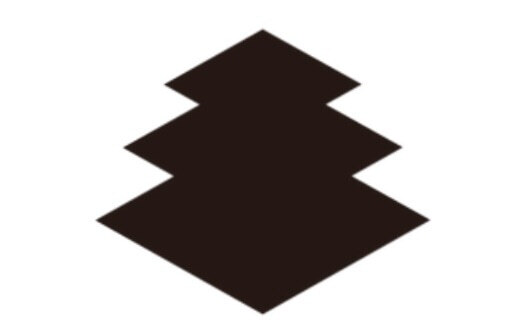
→→第一章へ←←
心の在処
2-1
白取氏は外ヶ浜横内の堤氏の家来にして、同じ外ヶ浜の原別の領主である。善知鳥(青森)平野の東端を抑え、街道筋の野内宿を統括する役割を担っていた。後に野内は江戸時代に入ると、大間越・碇ヶ関と並んで津軽三関と呼ばれる重要な拠点となる。
夏の盛りながら……北国の海沿いは寒い。土地は広いといえど、風に直接あたるので作物は育ちにくく、凶作続きもままある。そこに此度のこと。浪岡は津軽平野の北端、山の狭間に入る先っぽにあり、ちょうど北風が山に遮られる土地柄だ。同じ寒いにしても、夏は盆地のように暑くなる。原別と比べると確実に過ごしやすい。そこで “私が浪岡に入る” と立候補したのだ。主君である堤氏から言われていることには、あと三年無事に治まったならば、一族郎党ごと浪岡に移せばいいと内約を得ている。
こうして意気満々に浪岡へ入ったのだが……かつての在来の民は各所に散らばってしまい、戻ってきた者は半分以下。残りの土地はかつて為信が引き入れた他国者が耕している。この二つの住民の仲は悪く、激しい喧嘩こそしないが、いがみ合っている。加えて長年の南部と大浦の闘争により、土地は豊かだが耕す人がおらず、放棄されているところも多い。しかもいまだ他国者の心は為信にあると見えて、もし戦事が起きたならば兵の徴収に応じず、逆に浪岡へ逆らうかもしれぬ。そういった危うさが確かにあった。他国者を束ねる存在として大戸瀬や鰺ヶ沢の有力者がいまだ居座り、西浜よりさらに他国者を浪岡に引き入れている始末。どうらや為信の重臣である兼平の手の者や商家長谷川が担っているようだが……。
・
次第に浪岡の在来民の肩身が狭くなる。彼らの性格はどちらかというと物静かで、おそらくはかつて領主だった高貴な浪岡北畠氏によって感化された部分もあるだろう。それに対し他国者のどんどん押していく強さ。今でいうところの ”フロンティアスピリッツ” とも言うべきか。そのうち全員が追い出されるかくらいの圧で……。
戦を起こさないだけではなく、この両者の仲を取り持つのが浪岡代官としての早急の課題だった。
2-2 鬱陶しや
そんな折、自分の下に付いた奉行職である久慈信勝なる者が提案してくるのだ。昼夜問わず、事あるごとに話しかけてくる。
「多数を占める他国者を介入するには、その先にある大浦家を侮ることはできませぬ。何事も協力していくのが肝要……。何も私の兄が為信だから申しているのではございませぬ。私自身はれっきとした南部家臣、長兄は久慈氏の御当主でありますから。」
言いたいことはわかる。だが大浦と仲良くして隙を見せると、再び浪岡が奪われてしまうやもしれぬ。それだけは避けねばならぬ。
「そして大浦家がしているように、在地の者と他国者を同等に扱わねばなりません。無碍にすることなければ、他国者とて主に逆らう謂れはありませぬ。」
……現実としてどこまで出来るだろうか……在地の者が逃散し、そのあとで他国者が入った。そこに因を発し、残る(あるいは戻った)在地の者は他国者を信用しきれぬ。元住民の持ち物を奪い取った輩という見方しかできない。白取自身も同じ考えだった。さらには主君である堤氏は、もし軍役が課せられたならば、他国者から多くとればよいと考えておられる。特に止める気はないし、奉行職の面々で異論なければその通りにするつもりだ。
ここで浪岡の体制を説明するが、まず傀儡としての御所号である山崎政顕を戴き、その次に代官の白取伊右衛門がいる。その下に奉行職の三人おり、一人は久慈信勝、もう一人は為信の同盟者だった浅瀬石の千徳政氏だ。千徳は実際のところ為信に従属している身の上だが、名目上は為信との同盟者いうことだったので、南部に為信が再従属して以降は同じ南部家臣として浪岡の体制に取り込まれた。ある意味で為信を介せずに直接浪岡に出仕させることにより、大浦と千徳を分断させるのが狙いである。千徳家中では為信に取り込まれていた経緯を考えれば不服なところだったので、特に息子の政康は受け入れるように進言。こうして千徳は奉行職についたのだ。最後に糠部名久井の東重康がおり、為信に必死に抵抗を続けた田舎館の千徳政武と血縁である。ちなみに千徳氏の本家は浅瀬石で、田舎館はその分家だ。
このように奉行は三人いるが、”異論” とは申せ堤氏、さらに上の南部氏の意が通る。建前のために浪岡へ集めているに過ぎない。
2-3 馬鹿か、お前は
奉行職の久慈信勝は自分に力があるかのように錯覚し、代官である白取にしきりに話してくるのだ。そしてしまいには……
・
浪岡四日町の私邸へなんとも仰々しく首を下げに来る。夜中の屋敷前にずっといられても仕方ないので、自ら手燭で持ち歩く方を明るくし、もう片方の手で彼を迎え入れるのだ。……元をただせばこの屋敷は商家長谷川から提供されたもの。屋敷や財物を贈ることにより、浪岡での商売を続けることを許されていた。
・
……信勝は言う。
「他国者からは日々の不安を聞かされております。何でも……不作であれば他国者から米を多く取るとは本当ですか。同じ浪岡の民であることには変わりないでしょう。」
・
……白取もここまでしつこいと、イライラしてくる。元々短気な性があるので、それでも代官となったからには抑えねばと頑張ってきた。だがもう……
「どうか白取様。時に白取様には娘がいらっしゃる。その子を大浦方の重臣の御子息でもいかがでしょうか。こうすることにより……。」
・
・
気付かぬうちに、白取は信勝を蹴り飛ばしていた。……それは鬼の形相で、何もかも許せぬ。そして刀の鍔に手をかけ……いや。白取はカッとなる性質ではあるが、気が引けるのも早い。一時の癇癪さえ過ぎれば……落ち着いて判断はできる。殺すほどではないだろうと。……そして “話を続けよ” と。汗気の信勝は再び口を開いた。
「……はい。浪岡と大浦が手を結んだところを見せれば、他国者から見れば後ろ盾である大浦が浪岡と仲良くなるのだから、自分たちにも悪いようにはせぬだろうと、黙って耕作に励むことかと存じ上げます。」
・
そんなことか……馬鹿らしい。白取は信勝の方に顔を向けるのをやめ、後ろざまに言葉を発した。
「あいわかった。お主が他国者を深く考えていること。そして心は浪岡より為信にあることも。よってこれより横内へ出向き、一切のことを主君に伝える。追って沙汰を待て。」
灯りは消え、すべてが暗転する。
2-4 偽りの輿入れ
その頃合いは真昼ながら、とてつもなく暗い日であったという。白取は外ヶ浜の横内へ参上、館の一室にて主君の堤に報告する。
……この主君と家来は非常に気が合うようで、喜ぶところ怒るところがまったくもって同じだったという。白取の話を聞くなり末恐ろしい形相と化し、特に無理やり落ち着く必要もないので、丁度手元にあった筆を高々と上げ、勢いよく襖へ向かってぶん投げた。……墨が付いているので、斜め一線に色が付く。続けて茶道具なども壊そうかとも思ったが……そこは忍耐を強いられたかつての経験があるので、昔に比べて落ち着くのも早くなっていた。逆にいらぬ思考法を身に着けてしまったようで……不敵の笑みを浮かべる。その顔は白取の初めて見るところの面構えであった。
「ならば、別にお前の娘でなくてもよいだろう。偽物を送ってやれ。」
白取は……最初こそ驚いたが、これこそ生意気な信勝に一泡吹かせることができると思い、同じように悪そうな笑顔を浮かべた。
「せっかくなら為信の家臣と言わず、為信の側室としては。そうだな……最近流れてきたという出羽の娘はどうだ。没落した大商人の出であれば、素養はしっかりとしているであろうし、供回りを家中に潜り込ませれば大浦の情報が筒抜けだ。」
二人して笑ってしまった。堤が笑いだすと、続けて白取、そして脇に侍っている従者らも。出羽……最上郷の訛りは何とか理由をつけよう。さっそく大浦家へ送り込め。これで彼の言うように他国者も鎮まり、彼自身もしつこく纏わりつくこともなくなろう。
それ、油川よりその娘を呼べ。さあ銭にて売られる寸前だぞ。そこを救ってやるのだから感謝もされよう。
笑いが止まらない。……信勝はもちろんこういった経緯を知らぬし、沼田が彼より先に知ることになるのも少し遅れてから。こうして白取の娘とされるものは、為信の側室として送られていく……。
2-5 運命をば
夏の盛りの日……。北国の短い夏に、これでもかというくらいに蝉やら他の名の知らぬ虫が鳴く。汗が静かに頬をつたい、扇子で仰ごうにも一時に風を起こすばかりで、結局は暑い。だから諦めてしまって、汗をそのままに本などを読む。為信はそんな感じだったが、他の家来衆は忙しそうに “婚礼” の準備をしている。
……使いが大浦城の西ノ丸に到着。長い烏帽子をかぶった正装の八木橋は、恭しく首を下げた。
「原別の白取家より、側室となられる栄子様ご到着。」
・
……式自体は明日なので、前入りして支度や各所に挨拶をする必要があろう。為信は “うむ、わかった” とだけ伝え、下に置いてあった書物を手に取って読もうとする。……家来がすべてやってくれているので為信が何かするとかはないのだが……どうも適当な感じを受ける。八木橋は若干の違和感を持ちながら、伺いをたてた。
・
「それで……姫にお会いになりますか。」
やはり側室になる娘なのだから、式の前日に顔合わせをするのが普通だ。だが為信は静かに首を振り、口を開いた。
「これから小笠原のところへ行かねばならない。なんでも小笠原は娘にいまだ嫁として送ることを伝えていぬようで……私自身が伝えようと思ってな。」
・
真顔でそう返した。何だか……己の婚礼より家臣の事を優先させる、一見よいことにも思えるが……少し会うだけでもよいではないか。姫に会うのは夜でもいいわけだし……今は日の高い未の刻(午後2時)。いかにもそのこと自体を軽く見ているような……。
いや、これはもしや
「……正室の徳様を慮ってのことですか。」
・
そう八木橋が問うと、為信は不思議そうにしつつ言葉を返した。
「いや、あ奴は昔から “武家の習い” というものを知っている。”運命” を受け入れることに慣れている故、きっと大丈夫ではないか。」
悪評
2-6 決まってはいるが
その夜、為信は小笠原とその家族を城下の長勝寺に呼び、主君として命を伝える。いや本来ならば為信当人が伝えなくてもよい話。家族内で小笠原が娘に申し聞かせればいいだけの事だった。それをわざわざ……いらぬ手間をかけて自ら話す。もちろん小笠原が寡黙であまり話したがらないという性をもっている。でも同じ家族なのだから、そのくらいは伝えてもらうべきところ。
詰まるところ、為信はその娘に会いたかったのだ。未だ諦めきれず……かといって会ったところで、先に繋がるというわけではないのだが、顔を見れるうちに見ておきたい。側室の輿入れを差し置いてでも。
……境内にホタルが入り込む。ぼんやりと輝くその光が一つ。つられて他の光も寄ってきて、池の周りにて動き回る。まばゆく遊ぶさまはかつての童心を思い出したりする。
その様を開け放たれた襖から見つつ、為信は……娘に対して申し聞かせる。
「どうか多田玄蕃という男に嫁いではくれまいか。三々目内の館主で、そのあたりの土地を治めている若い者だ。共に六羽川合戦を戦い、生き残った運良き男だ。」
娘は……隣にいる父と母を見る。父である小笠原は……黙ったまま一言も発しない。母は……すでに聞かされていたのもあるが、笑顔を作ると同時に、なにやら哀しげな表情もする。もちろん想像はつく。せっかく離れ離れだった父と暮らし始めたのに、すぐに嫁いで行ってしまうとは……。どうであれ、娘の答えは決まっているのだから、悩むこと自体無駄なのだが。
「はい……。お受けいたします。」
為信は一つ頷く。そして再び娘に話す。
「うむ。もし嫌だというなら、断るのも悪くはない。もし断っても他の嫁ぎ先はあるだろうし……心を落ち着かせるまでの刻が必要なら、遅らせればいい。私でよければ話の相手になろう。」
2-7 運命のいたずら
側室となる栄子は白無垢の花嫁衣裳を身に着け、外ヶ浜からきた従者らを引きつれて城門をくぐる。その姿に悪しきところはなく、品の良さは皆々わかるところ。なのに為信はつれなく、式が終わるなり自室に戻ってしまった。こなさねばならない様々なことがあるのはわかるが、何も今日でなくてもよい。前日も会っていないそうだし……興味がないのか他の気のひかれることがあるのか。ちなみにこの時はまだ誰も栄子の正体を知らない。
栄子は……次第に哀しくなった。没落商人の娘が売られていくところを助けられ、一旦は武家の養女に。そして嫁がされては無碍にされ。故郷とは違う土地で知る人もおらず、心を打ち明ける者はいない。その様子を正室の徳は……黙ってみていた。夫の不自然な様、栄子のわざと会話を避けているようなそぶり。これは故郷の出羽訛りをできる限り出さないためと後からわかるのだが、女の勘は特に鋭い。どちらにも違和感はあり、その元を突き止めなくては……。
そこで親しい侍女に主人為信の動向を探らせてみた。するともしや……他の娘を強奪しようとしてまいか。
今でこそ徳は為信の正室として重きをなしているが、かつては側室ですらなく ”人質” として大浦家に入った。そこを主人は……憎き主人は……、そのように思ってはいけません。久しぶりに起きたこの感情は、忘れていたあの瞬間を思い出させた。命を落とすかの凶刃に為信が襲われた夜、何を思ったか為信は徳を求めた。その陰で不幸な女を一人生み、岩木山の向こうへ追いやってしまった。徳は……運命のいたずらか、為信の正室となって今に至る。これは幸運なことなのか未だわからぬ。子は二男一女設け、皆丈夫に育っている。幸せ……なのか。でも私はこれで十分かもしれない。
でも新たなる不幸を作らせたくはない……。このままでは栄子さんが惨めな思いをしてしまう。
2-8 悪評
徳は密かに書状をしたため、兄の千徳政康へ人を送った。為信と仲睦まじく良妻賢母と誰からも思われている徳は、その裏で為信へ反旗を翻す。表の理由としては、新しく入った側室を不幸にさせぬため。加えて言うならば、狙われている娘を為信のものとさせない……思い通りにさせるものか。裏……本音は、これまで主君として完璧だった為信の崩れるところを見たい。はっきりとそのように考えていた訳ではないが……確実に徳の無意識下はその想いで動いている。
ありったけの虚言、または本当の話を膨らませ、その書状は実家の浅瀬石千徳へ。兄の政康は父の政氏とは違い、義兄の為信を相当憎んでいる。檄文に……乗せられて当然である。
政康はたいそう驚き、“為信がこのようなことをしようとしている” と家来にばら撒いた。友好のために多田氏に嫁ぐ娘を、あろうことか為信が強奪しようとしている……。これは津軽の為にはならぬし、すでに決まった縁談を覆そうとする暴挙も許せない。……ならば多田玄蕃殿には、早急にその娘を連れて行って頂きたい。大事にならぬうちに……。
家来に話が伝われば、領民にも噂は広まる。為信はおかしくなった。戦がなくなった途端に緩みだし、果ては他家に嫁ぐはずの娘まで手を出そうとしている……。さらに尾びれがついて、“娘は嫌がっているのに、執拗に求められている” と。
確かに為信はあの後も相談にのるとして、幾度となく小笠原の娘と会っていた。手出しこそしていないが、何かの拍子に関係が変わるかもしれぬ。嫁いできたばかりの側室の存在を無視してまで、そうなることを為信は望んでいた……。何度も会えば、次の展開が待っているかもしれぬ。でも……と踏ん切りがつかぬうちに、月日は経つ。次第に夜に騒ぐ虫の種類も変わり、鈴虫などが鳴き始めた。
そしてその日は来た。小笠原の娘が嫁ぐ日取りは正式に決まる前、つまり為信がわざと遅らせていたのだが。多田玄蕃は自ら大浦城に参上し、娘を迎えに上がった。その姿は堂々としていて、誰の目にも凛々しく映ったという。
2-9 誤解
その刻は日高く、城内の隅々まで外の光が差し込んでいた。夏の陰りを感じさせず、多田の立つ姿の後ろには、色濃く影ができあがっていた。
大浦城の大広間。為信を上座に、重臣らが横にて座している。多田玄蕃は立ったまま、為信に喧嘩腰に話し出す。
「祝着至極に存じます。今から花嫁をもらい受けます上、こちらへ連れてきて頂きたい。」
為信はいまだ事態を呑み込めぬ。一方で多田の言葉は続いた。
「殿は六羽川合戦で本陣にて共に戦った間柄。その時は殿を殿として見ておりました。しかしこのままでは殿に従うことはできませぬ。」
「多田殿、落ち着かれよ。婚儀のことは進めておるし、……これまで出仕してこなかったのは、そちらではないか。」
多田は首を振る。
「いや、それはあくまで殿が “偉大なる” 殿でなくなったからだ。もちろんわが父の多田秀綱は事実上裏切ったかもしれぬ、いえ裏切っておりました。多田家の大いなる恥です。」
玄蕃はそこまで言い切ると、果ては息が続かなくなったと見えて、口を大きく開けて息を吸った。そして続けざまに、さらに大きく叫ぶかのように訴える。
「しかし私は違う。最初から今まで殿を裏切る気など一切ない。出仕しなくなったのは……殿の緩みが甚だしく、夢や希望もないと見える。弟君の言いなりに戦を終わらせ、夢や希望を失われた。そして此度の事……。」
唾を呑む。
「今度はあろうことか婚儀の決まった娘を、横からさらう気だともっぱらの噂。しかもその娘とは、私の妻となるべき相手だと……。もちろん殿には逆らいませぬ。しかし此度のこと。この日を以て婚儀となし、三々目内へとお迎えに上がりました。さあ、今こそ花嫁をお連れ下さい。」
2-10 本当の忠臣
い、いや。それは誤解だ……。
「何が誤解だ。それとも誅殺でもなさるか。このように殿に向かって家臣が大声で叫んでいるのです。どうぞお殺し下さい。……ただしその後であなたがどうなろうが、知ったことではない。」
続けざまに話そうとするところを、横で聞いていた乳井が止めにかかった。続けて森岡がその場に立ち、多田を背中から腕をつかみ、目の前から引きずり降ろそうとする。森岡は……”許さん。多田はやはり信用ならぬ” とドスの利いた声を放ち、すると乳井は森岡に “余計なことは言うな” と首を振った。そして多田の前に乳井が立ち……
「同じ平賀の郎党だ。私がじっくり話を聞くから、一旦は下がろうぞ。」
その言葉に舌打ちをする多田。……この場にいる家来衆で一番歳の多いのは乳井だ。為信とは違って、風格なのか威厳というべきか、やはり彼の言葉が一番効くのだ。
多田は最後に小笠原の方を見た。小笠原は未だ座ったままで……何やら考え込んでいるような……無言なので、結局のところはどう思っているのかわからぬ。そうして多田は森岡に捕まえられたまま大広間を去ろうと……その後ろを念のため兼平が付き、心の収まらぬ為信の脇には八木橋が侍る。その実、為信と八木橋、そして多田は六羽川合戦の本陣において生き残った数少ない同志……。こうも険悪になると思いもよらず、連れていかれる後姿を眺めるしかなかった。
そして襖は放たれ、閉められるのか。その時だった。小笠原は連れていく森岡を呼んだ。森岡はその場で立ち止まり、小笠原の方を向いた。多田は……顔こそ向けないものの、じっと耳を澄まして聞く。
小笠原は……慣れぬ調子ながら、口を開いた。
「殿ではない。私が……遅らせたようなものだ。だから、殿ではない。」
親と娘、離れ離れで生きてきたのが、今やっと共に暮らせる。言葉足らずではあったが、言わんとしていることは全ての者に理解できる。荒立っていたその場の空気はしんみりとしたものへと変わり、目線は小笠原へと注がれた。
「殿が遅らせたのは……きっと私を思ってのこと。」
「待たれよ。今、娘を連れてくる。」
広間に暖かな日差しがさす。斜めに入る線状の光。窓の格子より入るそれは、立ちゆく小笠原の背を大人物のように際立たせる。結果として為信は、小笠原に救われた。
これより先は多田も大浦城へ出仕し、大浦(津軽)家のために尽くしたという。
ただし悪評は消えることなく、伝承として現代に残る。
→→第三章へ←←









