【小説 津軽藩以前】 プロローグ 相川西野の乱 永禄十一年(1568)秋
【小説 津軽藩起始 浪岡編】第一章 松源寺の会見 天正五年(1577)初春
【小説 津軽藩起始 六羽川編】序章 水木御所成立 天正六年(1578)秋
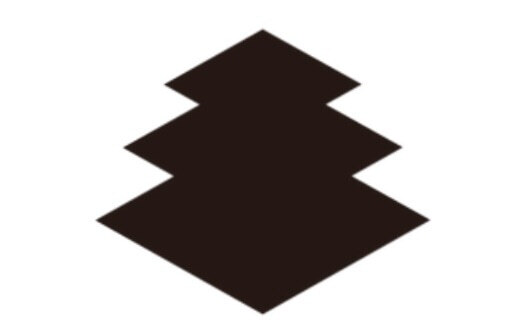
家族の事
1-1 昔は昔。
「父上。今日はたいそう朗らかで、よき頃合いでございますね。」
……城の屋形の縁側にてくつろいでいると、彼の息子が話しかけてくる。六歳になった平太郎は為信の長子だ。大きな病にかからず、よくぞここまで育ったものだと感心する。
・
「ああ。小笠原に稽古をつけてもらうか。学問は日の晴れぬ時でよかろう。」
・
平太郎(信建)は満面の笑みで返し、自然と為信の顔も緩む。どうも息子は座っているよりか、体を動かす方が好きと見える。……遅れて平太郎を追ってきた次男の総五郎(信堅)もたいそう可愛らしい限りで、このような日々が続いてほしいといつも思う。娘の富子も三歳のうぶな姿を見せてくれるし、三人をここまで育て上げた徳姫には感謝しかない。もちろんこれまでの経緯を忘れてはいけぬし、わざと蓋をしてしまったこともある。さすがにあの事があったときは、“忘れてなるものか” “不幸の上にこの平和がある” と嫌なくらい思ったものだ。しかし時は残酷で、何度も念じていても次第に薄れゆく。かつて戌姫という妻がいたことなど、普段は思い出さない。もちろん奴が悪いのであるし、殺傷など許されることではない。だからこそ蓋をした。山向こうに移し、姿自体が見えぬように……。
と、久しぶりに頭の中をよぎった。同じことを何か月前に思い出したかなどいちいち覚えているはずもなく。為信は再び平太郎へ目線を移し、子供の背中に手をあてて小笠原の来るであろう方へ歩ませた。平太郎、そして総五郎は門が少し揺れ動いたのがわかると、一目散に駆けていく。「小笠原よ、はようはよう。」小さな二人は屈強な大人の手をそれぞれ掴み、稽古場の方へ進んで連れていく。遠くより小笠原は為信に一つ首を下げ、面を上げるとその愛想のない様を見せた。
そんな彼もしばらく前に家族を信州より呼びよせて、城下に住まわせているという。かつては諸国を浮浪した彼だが、やることはしっかりやっている。
1-2
私には二人の男子の他に、娘の富子もいる。後ろを小さな足で歩く娘の姿というものも、かけがえのない存在。こうして生まれたときから共に過ごすことも、今の世の中からすれば特別なのかもしれぬ。
・
かつて小笠原は妻子を縁者に預け、諸国を浮浪した。そうして津軽の地までたどり着き、最後にはわが家臣となった。こちらでの暮らしが落ち着くまで家族と離れ離れだったが、二年ほど前に呼び寄せた。もっと早く来させてもよかったはずだが……小笠原の中でなにかしらの “ふんぎり” というものがあるのだろうか。彼は十分に手柄を立てているし、誰も非難する者なるいるはずがない。もちろん “ありえぬ” 一件はあったが、それは決して彼のせいではない。いまさら何を遠慮していたのか。
……だからこそ、信頼におけるともいえよう。ふと気づくと、平太郎と総五郎の二子が去った後の門前に、一人の若い娘がきょろきょろと目を泳がせていた。装いはきらびやかというわけではなく、どちらかというと粗雑な……いや農婦がここに来るはずもないし。城中であるのだから。
いつしか目が合う。為信もさすがに誰であるか気付く。
・
「もしや、小笠原殿の子女であるか。」
・
最初こそ娘は呼びかけられたことに慌ててしまい言いよどんだが、手元に持つ風呂敷包みに目を移しつつ、小さめな声で答えた。
「はい。父上が忘れて行かれたので……どちらへ向かわれましたか。」
「もうあちらの方へいったぞ。」
為信は小笠原の向かった方を指さした。すると娘は慌てて一礼をし、小走りにその場を去った。
・
娘の富子も、十年も経てばあのようになるのだろうか。なんとも気立てのよさそうな印象……。
今度、小笠原の家族を城に招いて語らってみようか。
1-3 揺らぎ
時が経てば感情というものは当然の如く変わり、遠く離れた人との縁は薄れ、常に接する人と仲良くなるのは当たり前である。それが自然とそうなったのか、意図的に離したのかは別として。すなわち為信にとっての戌姫はそれであるし、その想いを押しつぶすかのように徳姫を大事にしてきた。今や二男一女をもうけ、仲睦まじい限りだ。
だがふと別の女を求めたくもなる。しかし戌姫のこともあるし、中々踏み出せない自分がいる。それに小笠原の娘を側室にしてしまおうなど決めてしまっているわけでない。ただ単に語らいたいがために小笠原の家族を呼ぶだけだ。
そうだ。すでに子を設けているので、側室を取る必要性も薄い。あとは己の快楽か、趣味か、はては暇つぶしか。いやいや上に立つ者なのだから、筋が通っていなければならぬ。家来衆の示しもあろうし……、いや。もちろん当時の一般的な概念からいえば、大将が側室を取るということに不自然さはない。その上で特に小笠原は十分なる功臣であるから、その娘を取ればお家はさらにまとまり、強固になる……。
いやいや、何をすでに側室を取るつもりでおるのか。もしや徳姫に飽きたのか。そうなのか。男の性というものは……あれだけ己や子供らに尽くしているというに。徳姫では心全てを委ねることはできないか。その隙間を別の女で……。
そうこう考えていると、ふと我に返った。事を難しくする必要はない。主君が家来の家族と語らうくらい、ありうること。
そして足は大浦城下の長勝寺へ向かう。日は岩木山の向こうへと沈みかけ、辺りは次第に暗くなっていく。少ない供回りを連れ、ずっしりと重い門を開き、横に建っている庫裏へと向かった。……大きな馬が松につなげられているので、小笠原とその家族はすでに来ているはず。
1-4 会食
灯には冷たいものがあれば、温かいものもある。複数ある松灯台に点けられた明かりは、為信の目には小笠原と妻、そして娘をぬくもりを以て包んでいるようにも見えた。
いくら離れ離れに暮らしていても、強い思いがあれば覆すことができる……。為信の思った前説はすでに成り立たないのだが、小笠原だけを例外として分けておくことにする。
為信を加えた四人が小さな一室にいるのだが……夏の暑い時なので、襖は開け放たれている。月はたまに雲に覆われるのだが、とても薄くほとんど無いようなものなので、暗いということはまずない。耳を澄ますと夏虫の声、廊下の奥に侍る従者の息。為信は目の前に座る小笠原の椀に、大瓶より酒を注ぐ。トクトクと音を鳴らし、小笠原はその様をいつもの無愛想な顔で見つめている。すると隣より妻が声をかけた。
「何か言いなさいよ……。さすがに殿の前ですから。」
小笠原は黙ってうなずいたが、特に何を話すわけでもなく、そのまま椀を口にした。
「わかっておる。小笠原殿なのだから、言葉がなくともよい。」
・
少しだけ妻は呆れた。娘はその顔を見て、きっと面白かったのだろう。薄っすらと照らされたその透き通った手で口を押えつつ、顔を崩した。声ははっきりとしないが……笑っているのだろう。
信州での暮らしは大変貧しかったと聞いている。そうでありながら、なんと品のある娘に育ったものか。やはり彼の血なのか、“道を極める”という意味で受け継いでいるのだろう。ともに夕餉を共にして、非常によくわかる。あと言葉が少ないという点もそうだ。
もう少ししたら、また呼ぼうか。回を重ねれば……娘の口数というのも増えてこよう。興味はある。かつ己は自由にできる立場だ。申し訳も付く。止める理由もない……と気づかれぬように、心の中で盛り上がる。
1-5 関係なく
そして城に戻り、子供の顔を見ようものなら……きっと罪悪感が湧くだろう。そこで自然と二ノ丸へ行かず、わざと本丸へ向かった。高いところであれば幾ばくかは涼しいだろうと嘯くために。
後ろを歩く従者は、なんとなく察している。かといって止める謂れはないし、ただただ己の任を果たすのみである。曲輪を隔てる土塁にかかる橋を黙って渡っていると……背に迫る気配を感じた。刀の鍔に手をかけ……もちろんすぐ抜けるように。為信も一端の武者なので、やはり気づく。だがすぐに敵でないことも悟った。従者よりは少しだけ早く。
・
「殿、よろしいでしょうか。」
その声は落ち着いている。為信より少しだけ背が高く、最近は口の上に髭を生やし始めた。小袖肩衣は他の者とそんなに変わらぬが、なにやら儒学者のようにも見えたりもする。あながち間違いでもないが……昔は易をやっていただろうし。
「おお、沼田ではないか。何かあったか。」
「私も本丸へ参りますゆえ。」
・
そして耳元で小さく伝えるのだ。
・
・
(秋田にて、変事がありました。)
・
・
・
為信もさして顔を変えぬ。一応は従者にも悟られてはならぬ。このように沼田が夜に参ったところを見ると、まだ出回っていない話だろう。ただし従者のほうも何やらあると勘づいたようで、「急用がございますれば」と申すなり、渡っていた橋を引き返していった。為信は……沼田へ言う。
「今日はの……気分が良きままに寝たいのだ。」
沼田は苦い顔をしつつ、「それは残念です。」 と情け無用に応える。為信としては……笑うしかない。沼田は……真顔に戻り、事を伝えた。
・
「安東が比内の浅利勝頼を誅殺しました。早道によると、潜ませていた兵を混乱に乗じて城へ入れ、領国を乗っ取ったようです。」
弟の腐心
1-6 なし崩し
天正十年(1582)旧暦五月十七日、比内浅利氏当主の浅利勝頼は長岡(大館)城にて殺害された。当時は城内にて酒宴が開かれており、蝦夷地より当主就任の挨拶にきていた安東家臣の蠣崎慶広を接待するためだった。蠣崎氏は海側だけでなく奥地も見聞することを望み、ならばと同じ安東従属下の浅利氏領国に向かわせたという。
ただしそこに企みがあり、浅利家臣の片山氏は安東と内通。以前より浅利勝頼は反骨の意図を示していたため、酒宴の席にて殺害しようと。蠣崎氏が伴ってきた安東の兵らによってその場の混乱は鎮圧され、さらには山に潜ませていた大軍によって城は占拠された。
実をいうと浅利氏は安東に対抗しうる勢力として南部氏や大浦氏に接触を図ってきた。ただし南部にはしばらく事を起こす意志はなく、大浦は力を無くし南部に再従属している始末。誰とも手を結べずにいた頃合いでの変事である。
……こうなると危ういのは津軽南方、平賀郡の動向だ。一応は南部氏より平賀郡は大浦領と認められていたが、実際に力の及んでいる範囲は狭い。大浦家臣の乳井氏や三々目内の多田氏ぐらいまでが勢力圏で、よくて宿河原まで。それ以降の川沿いはいわば大浦と安東の緩衝地帯。六羽川合戦の折、大浦(津軽)家に属した多くの勢力は安東によって攻め滅ぼされてしまったし、残ったのは安東になびいている国人ら。
しかも大浦家臣であるはずの多田氏も信用はできない。元をただせば六羽川合戦を滅茶苦茶にした要因は多田氏の面の良さであある。敵軍を平野部へ向けて素通りさせた責を負い、当主だった多田秀綱は大浦城内にて自刃させられた。父を殺されたも同然の多田玄蕃ならば、いつ安東に与してもおかしくはない。
・
・
いまだ津軽には詳しい報が伝わらず、比内には安東の大軍が入ったということしかわからない。これが勢いを持って津軽へと再び差し向けられれば……なし崩しに大浦家が滅ぼされる恐れがある。
1-7 頼りとなれぬ
変事の報が入って後、翌十八日には二千の兵を大浦より南方の堀越城に集結させ、事態の変化を見守った。……しかし何も起きず、安東方では比内を抑えるのに手いっぱいと見える。津軽への干渉は一切なかった。
そして浅利家中よりこちら側に逃げてきた者は百名に上り、その中には亡き浅利勝頼嫡男の頼平や分家の実義らが含まれていた。特に実義は六羽川合戦で安東方として攻め入ってきた大将の一人であり、捕えられたが殺されずに解放された。それが再び津軽へ舞い戻ってきたのだから皮肉である。そんな彼は泣きながらに訴えるのだ。
・
「何卒、何卒……比内の奪還を……。」
・
とは申せ、大浦は相当痛めつけられた。傷はまだ癒えぬ。本音では津軽の諸将は戦をやりたいだろうが、そんな無理くりの “じょっぱり” に任せてられぬ。そこでこのように申し伝えた。
「我らの一存では決めることができぬ。南部の殿様に図ることだな。」
“嗚呼”とその場にひれ伏し、隣の頼平はだまって俯くのみ。ひたすら我慢する。その様を広間にて聴く大浦の重臣ら、乳井と小笠原の二柱のほか、沼田、兼平、森岡、八木橋ら諸将。それぞれに思うところはあるだろが、誰が言いだしっぺになるか様子を窺う。
・
……誰も話しはじめないので、実義の嘆きのみがこだまし、なお一層の悲壮感を醸し出した。最後には耐えられなくなった乳井が襖に控える侍を呼び、この者たちを休ませるようにと促す。実義と頼平は……引き下がるしかなかった。
そして二人が広間より去ったのち、兼平が口を開く。
・
「多田殿は……来ぬのですね。」
・
為信は静かに頷く。そんな時、場をわきまえぬ閑古鳥が鳴いた。なにやら空虚な心地もする。……明日の我が身は彼ら。だからこそ、迫る危機を除かねばならぬ。
1-8 あの娘
小笠原は当然の如く黙ったまま。兼平や森岡は互いの顔を見やり、次いで八木橋に顔を向ける。八木橋は……その場の静けさもさることながら、このように目線を受けると何か言わねばならぬ切迫感にさらされた。そして口を開くのだ。
「多田殿をつなぎ留める……誰か年頃の娘など。」
すると森岡は小さめにため息をついてしまう。“誰のを” と応える。森岡はかつての先代に似て、若いながら底冷えするほどの怖さを備えている。以前に雷を落とされた八木橋にとって……思い出したくない記憶だ。
「本来ならば……一門衆にしてしまえば、これほど強いものはございません。ただし殿には娘はいれど、離すには若すぎる……。」
兼平は苦い顔をし、森岡は一笑にふした。三歳か四歳でしかない娘を、二十歳の立派な成人に嫁がせるわけがない。それを相手が望むなら……趣味を疑う。
「ですが……ならば一門でないにせよ、信頼が置ける重臣の娘ならば……こちら側に留めておけるのでは。」
八木橋が恐る恐るこのように続けると……為信は思わず小笠原の方を見てしまった。いや……しかし……。顔にこそ出さぬが、戸惑っているところに乳井が訊ねる。
「その “信頼のおける重臣” という意味は、この場にいる面々だという解釈でよろしいか。」
八木橋は即座に “はい” と応え、広間にいる者らを怯えながら顔色を窺う。乳井はそんな八木橋に言った。
「私の乳井家では生憎だが、子は男子しかおらぬ。兼平殿と森岡殿は子が生まれたばかりで、幼すぎる。八木橋殿は……早く嫁をお取りなされよ。」
為信は本音を覆い隠すが様に、わざと笑った。沼田も “当家は子がおらぬ” と答え、果ては一人しかいなくなる。
1-9 良き縁談
もう小笠原の家族しかいない。誰もがわかる。しかし事情を皆々知っているので、強く言えるはずもなく。長く離れて過ごしざるを得なかった家族と一緒に暮らし始めたばかりなのに、すぐに引きはがすような真似は……避けたい。
・
周りが思い思いに悩む中、小笠原は目を瞑り……そして開く。一言、“わかり申した” とだけ言い、少しだけ下に俯く。顔色こそ隠せているが、やはり堪えているか。そこで乳井は
「お日柄のこともあるだろうし、今すぐという訳ではない。同じ津軽なのだから、いつでも会えるではないか。」
と隣の小笠原の肩を叩くのだ。無意味に近いが。
・
一方で為信はというと、その娘とは親しくなる前であるので傷は薄い。大変惜しい限りであるが……大将と言えどこうなれば好き勝手できぬし、諦めるか……と天井を仰ぐ。この意味をその場にいる諸将は知りえないだろう。本人が言わない限りは。
・
再び小笠原が頷いたところで、沼田は周囲を見回しつつ為信の前へ進み出る。特に恭しく申すのだ。
「ここで娘子の話が出ましたので、お耳に入れたき儀がございます。」
・
他の者すべての目線は沼田へと注がれる。為信は “申せ” と応えたので、続けて沼田は言う。
・
「実は浪岡代官の白取様より、お話を頂戴しております。まだ内々の話にて、進むも引くも自由でございます。」
すると沼田は懐より書状を出し、一同の真ん中にて長い紙を広げる。末には “浪岡御所山崎政顕下、南部 堤家臣 白取伊右衛門” の字が。
・
・
浪岡御所は天正六年(1578)に大浦家が滅ぼして以降、一旦は大浦家の傀儡政権である水木御所に変わった。しかしこれも翌年の六羽川合戦で、御所号の北畠(水木)利顕が戦死。結果として大浦は南部に再従属に至ったため、南部氏は代わりに北畠遠縁の山崎政顕を御所号として傀儡政権を打ち立てる。その監視役が外ヶ浜の堤氏であり、代官としてその家臣の白取氏が浪岡に入っていた。
1-10
皆々書状に気を取られているうちに、沼田は為信に耳打ちをする。
「弟君も頑張っておられます。ひたすらに兄の事を思いながら。」
・
沼田は為信に微笑み、為信は……驚きのあまり、すぐに言葉を返せなかった。沼田はまったく刻を与えずして、書状の袂へと身を返した。
・
「これは南部と大浦の、末永い平和を願うものである。特に堤氏は大浦氏より娘をもらった過去があり、然れどもすれ違いで災難にあってしまった。その恨みを水に流し、新たなる世を築くため、先方より殿の側室にと仰せだ。」
・
誰もが狼狽えている。特に森岡などは “相手方がこのようなことを申すはずがないだろう” と沼田に迫った。確かにそうなのだ。森岡の思い浮かべるところは実際に当たっていった。ちなみに為信弟の久慈五郎為清は大浦家より去った後、南部家臣として浪岡に入った。その際に “信勝” と名を変える。こうすることでわざわざ浪岡を訪問しない限り、同一人物とバレることは無い。特に大浦家中の人間から恨みを買っているので……命を守るためでもある。風の噂で聞いても、為信の他の弟とでも思ってくれればいい。
その信勝であるが、ひたすらに南部と津軽で戦が起きぬように心を配り続けた。そして必死の説得や介入によって、堤氏重臣の白取の娘を為信の側室にすることに成功したのだった。……普段は浪岡の奉行職の一人として、密かに沼田とだけやり取りを続けた。沼田にとってもかつての若い頃の至らぬ為信を見るようであったし、この繋がりはいずれ新たなる転機を生むかもしれない……。
・
再び大浦家、いや津軽家として決起する時がくる。自身も他国者である沼田にとって、手っ取り早く身内に利するためには、戦争で土地を奪うこと。その場所こそ浪岡であり、その向こうは外ヶ浜。浪岡代官の白取を味方に付ければ……勝てる。
・
沼田と信勝、二人の思惑は完全に異なるが、婚儀を進めることで一致をみた。
→→第二章へ←←











