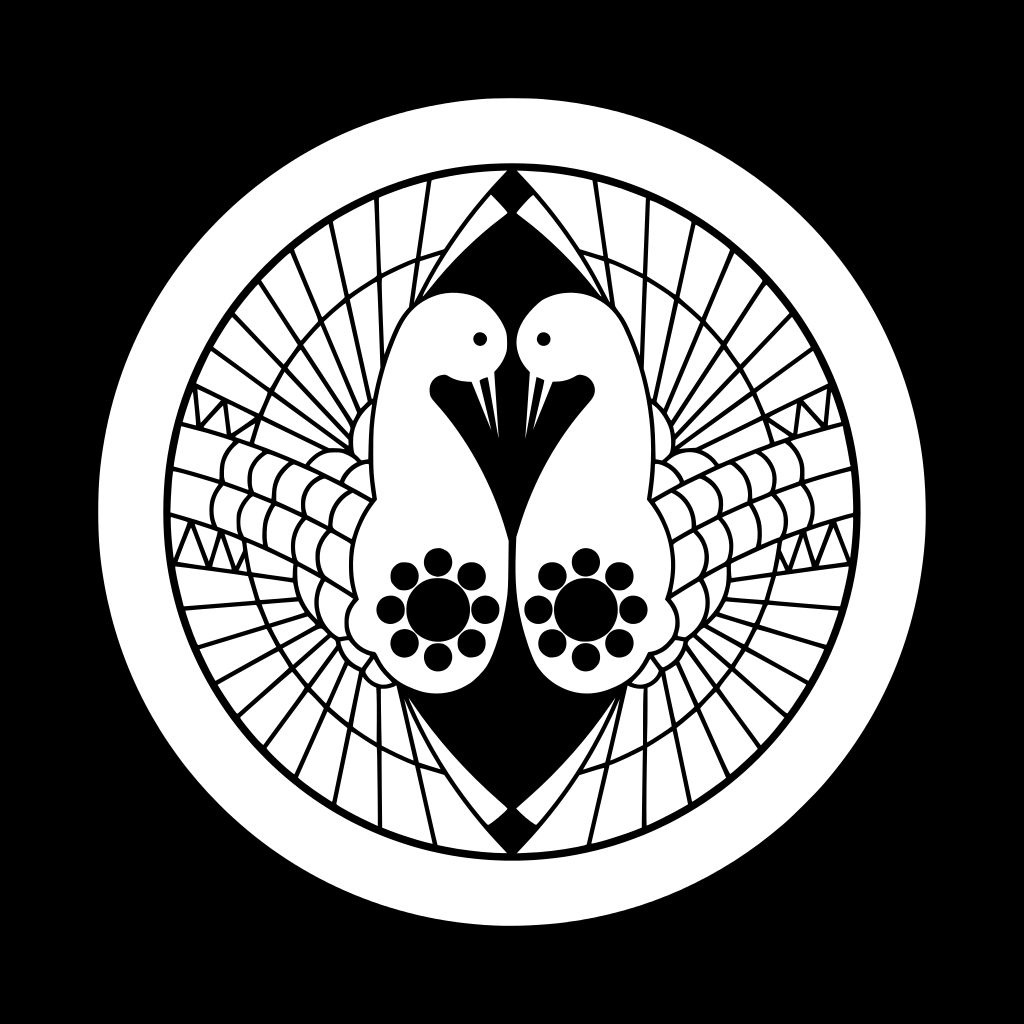
・
慶長五年八月十五日 南部領稗貫 雄山寺
少々肌寒さが出てきた、穏やかな日和である。
その老人は、落成して間もない寺を参詣する人波を、端でぼんやりと眺めていた。
背は高いがぴんと伸びている。髪もまだまだ白く肌も張って若々しいが、刻まれた皺の深さは彼の生きた年月の長さを感じさせた。
そんな、どこにでもいそうな老人の下に、一人の若武者が近づいてきた。
「御父上、こちらにおいででしたか」
「おお、重左衛門か」
息子――正確には養子――の北重左衛門直吉(きたじゅうざえもんなおよし)は少々呆れ顔のようなものを浮かべながら近づいた。
「いきなり城から抜け出さないでください。探すのが手間でございます」
「何日かに一度はここに参らんと落ち着かんでな」
老人――北松斎信愛(きたしょうさいのぶちか)はにこにこと答えた。
好々爺だ。その実、南部氏の要衝たる花巻城の城代として周辺を支配する領主であることなどみじんも感じさせない。
この寺は信愛の息子のひとり、愛邦(ちかくに)の菩提寺だ。信愛がこの地に来てすぐに作らせた。日を明けずこの寺に来ては、愛邦と、もうひとりの息子である秀愛(ひでちか)の菩提を弔うのが、信愛にとっての習慣になっていた。
「どうした」
「城にお戻りください。最上表と上方で異変があったとのことです。お屋形様から書状が」
直吉は書状を差し出した。
信愛は目を見開くと、書状を荒々と受け取り、ぐっと顔を近づけて読み取る。そして低くうなるように命じた。
「……直吉、不来方と三戸の留守居にも飛脚を――上方で謀反じゃ」
荒れるな、と信愛はため息をついた。
半月ほど前、上杉氏を征伐するために徳川内府が留守にした隙を突き、上方で対徳川の兵を起こしたとする書状が南部氏をはじめ、上杉征伐のため最上氏の領地に集結した奥羽諸侯の下に届いた。
毛利を中心として宇喜多や小西・石田、なにより豊臣の奉行衆など、西国勢の多くがこの決起に与し、討伐される直前だった上杉氏もこれに加わった。
上杉領国へ進軍していた徳川内府は謀反を鎮圧するため道半ばで引き返し、討伐に参加するはずだった奥羽諸侯には解散を命じた。
奥羽諸侯は泡を食った。上杉は五大老の一として奥羽最大の勢力を誇る大大名だ。徳川内府率いる軍勢があればこそ対抗できる相手だというのに、それが来なくなってしまったのだ。
徳川からの解散の命を幸いに、奥羽諸侯は最上領から一斉に撤収を始めた。その中には南部氏もいた。
「殿の帰国はもう少しかかりそうじゃな」
城に戻って使者の口上を聞いた後、評定の間で信愛はため息をついた。最上から秋田・仙北筋と大回りしての帰国である。時間がかかるのは仕方ない。
「御父上、此度の戦、拙者には上杉に有利と見ますがどうお考えですか」
直吉は問うた。ふむ、と信愛は書き損じの紙を引っ張り出して、日ノ本の地図を描き、京都の所に丸を付けた。
「徳川と上方の戦次第じゃ。上杉との戦いなど端戦さにすぎぬ。徳川殿と上方衆、どちらが優位を築くかで何もかもが変わる。徳川が勝てば上杉は負け、上方が勝てば上杉が勝つ」
「我らはそれを待つしかないというのですか」
「左様、両者の決着がつく前に我らが『潰されない』ことを第一に動かねばならん」
我らが上杉を滅ぼせるならまた別だがな、と信愛は苦笑する。
「上方の戦が決着つかず、その間に上杉が攻めてきたらなんとします」
直吉が打てば響くように疑問を返してくる。若いが頭の回転は速い。才気だ、と信愛はそれを快く思う。
信愛は書状をひらひらと振る。
「御屋形様は上杉と通ずる事も考えているようじゃ。どうせ帯刀(楢山義実)の入れ知恵であろう。悪くは無いが伊達に感づかれておっては意味が無い」
「伊達が気付いていますか?」
重左衛門は目を丸くした。思いもよらない事であった。
南部と境を接する伊達は、徳川との関係が深い。まだ動きを見せていないが油断ならない相手だ。
「ここしばらく、伊達が妙に低姿勢じゃろう、あやつら、我らが上杉方と見て事を荒立てぬようにしているのよ。気づかれているぞ、これは」
伊達の‘耳’は侮れない。草(密偵)も優秀な者たちを揃えている。伊達の低姿勢はつまり、南部を敵に回さぬようにするためだと信愛は喝破していた。
同時にそれは、南部氏の動きが読まれているという証拠でもあった。
(お屋形様回りの重臣どもめ、先走ったことをしおって)
どこで漏れたか知らないが、どうせ上方からの書状に動転して不用意な動きをしたのであろう。
伊達は既に徳川方として上杉との戦端を開いている。南部が上杉方になれば、伊達は上下から挟み撃ちを受ける。南部は伊達に比べれば小勢とはいえ、二方面から攻撃を受ければ苦しいのは伊達だ。
「しかし、だとすれば上杉が安泰な限り、伊達と戦は起きませぬな」
「逆じゃ、伊達は今上杉とは戦いたくは無いだけで、勝てるとなれば動くぞ。徳川様と上方の軍勢、どちらが勝つのか次第で旗幟を決めるつもりだ、我らと同じようにな」
上杉に与すると見られたら、徳川からも敵と思われかねない。南部としてはそれは避けねばならない。逆もまたしかりだ。
「だからこそ、今は各地の情報をなるべく早く集めながら、変転があればすぐ動けるようにしておく事が肝要なのだ」
「どちらが勝つと思いますか?」
「知らぬ。だが、諸侯の動きをよう見ておけ」
信愛はやれやれとため息をついた。
「このような面倒にまた関わらねばならんとはな。やはりお屋形様の願いなど聞かずに隠居しておけばよかったわい」
「何をおっしゃられますか。お屋形様直々に慰留されたのでしょう」
直吉は信じられない言葉を聞いたかのように声を荒げた。重左衛門は『忠義者』信愛に妙な憧れを抱いているのだ。
「御父上のことは忠臣の鑑だと皆言うておりますぞ。そのようなことを申せられるな」
信愛はその言葉に、呵々と嗤った。
直吉は若い。昔の信愛が何と呼ばれ、嘲られていたか知らぬのだ。
「私は忠臣ではないぞ、そう言われたわい」
「誰がそのようなことを」
まるで問い詰めるかのような直吉に、信愛はふん、と鼻を鳴らした。
「前のお屋形様よ」
慶長四年五月六日 陸奥国南部領糠部二戸 福岡城
その日は北尾張守信愛にとり、主君との最後の対面となった。
「おお、来たか、信愛。入れ」
そろそろ汗ばみそうな暖かな陽気の中、福岡城の奥亭の部屋で、その男は信愛を呼び入れた。
南部大膳大夫信直(なんぶだいぜんたいふのぶなお)――北奥のさらに奥を支配する武家・南部一族の長は、病床で横に伏せったまま、信愛に顔を向けた。
まるで枯れ木が寝ているようだ。自分よりも若いはずなのに、顔は血色も悪くやせ細り、目ばかりが爛々として気持ち悪い。
「いつ見てもお前は血色がよいな」
「そういうご家督は相変わらず青黒いですな。お加減はどうですかな?」
「今日は悪くない。久々に腹も痛まん。だが腕を動かすのもおっくうだでな、蚊に食われてもひっぱたけん。難儀なもんだ」
信直の顎に、蚊に刺されと思しき小さな腫れがあった。信愛はそれをぼりぼりと掻いてやる。その皮膚は老いに負け、ぐにゃぐにゃと柔らかい。
「お前と会うのも、今日が最後になるかもしれん」
お戯れを、とは言えなかった。信直の衰えは激しい。病の身を押して上洛し、そして帰国してからというもの、彼は伏せってばかりだ。
長くはない。南部の誰もが思っている。
「寂しくなりますなぁ」
だから、信愛は本心の一部だけを呟いた。
元々心の細い部分がある方だ。身も心も、南部の家督という重責によってかんなのように削れたのだろう。大名の当主とはそういうものだ。
毀誉褒貶がある方ではある。だが、南部の国を作ろうと必死だった事だけは、信愛がよく知っていた。
「……先日な、息子の名を利正から利直に変えるよう命じた。俺の一文字をやるかどうか、最後まで悩んだんだがな」
死に際して当主の一字を息子に譲る――その意味は明白だ。
「これからは、利直様をお屋形様と呼ばねばなりませんな」
「ああ、俺は隠居だ。晴政公の嫡子になって三十五年、実際に家督を継いで十九年。月並みだが、疲れた」
深々と吐かれた溜息が重たく落ちる。
「私はまだ、一層忠義を尽くさねばなりませんな」
信愛は信直を安心させるように言った。為政者として多くの臣下を率いねばならなくなる利直の行く末にとって、重臣の支持は必要不可欠だ。信愛の言葉はその意を含んでのことだった。
だが、その言葉を信直は鼻で笑った
「好きにしろ」
「好きにしろ、とは」
「言ったとおりだ。お前はいつだってそうだったろう。ただ己と己が家のために動いていた。俺の後も好きにやればよい。俺はお前を止めん。いや、止められん」
いつものようにな、と信直は皮肉気に笑った。
「今日貴様を呼んだのはな、後事を託すためではない。俺が恨み言を吐きたかったからだ。昔話に付き合え、信愛」
「拝聴しましょう」
信愛はあぐらをかいた。
こうやって君臣二人、語り合うのはいつ振りだろう。信愛は妙な懐かしさと寂しさを憶えた。
「お前、晴政公と俺が争った時のことは覚えているか」
「ええ、老いたりとはいえ、忘れるわけがございませぬ」
もう三十年ほど前の話だ。長らく男子の生まれなかった当時の当主晴政(はるまさ)に実子晴継(はるつぐ)が誕生し、それまで家督後継者とされていた養子・信直は廃嫡された。信直は嫡子の座を自ら降りたが、讒者によって叛意ありとされ、窮地に陥った。
その信直を助けたのが、信愛だ。
「誰も頼るものがない俺を、お前が拾った。落ち目の家が落ち目の俺をかくまって何をしたいのだと思ったもんだよ」
「思えばあの頃は貴方も私の家も、ボロボロでしたな」
信愛は懐かしげに眼を細めた。
北家は、南部氏の宗家である三戸南部氏、その譜代たる御一門の一つだ。今でこそ南部十万石の内、花巻地方の八千石を支配し、さらに他の一族の所領を加えれば優に二万石に迫る大族となったが、信愛が家督を継ぐ頃はずいぶんと落ち目の家だった。
同じ御一門の南氏との争いで所領を削りとられ、和睦の証として信愛は南氏当主・南信義の娘を娶ることになった。爾来十数年、北家は南氏の風下に甘んじた。
「貴方と晴政様の争いは、わが家にとって好機でした」
「そうさな、お前が目指したのは北家の復権であって、俺の復権ではなかった。俺を当て馬にうまくやったもんだよ」
信愛が信直をかくまった時、信直には既に家督の目は無かった。晴政を滅ぼせば別かもしれないが、信愛はその手を採らなかった。信愛は有利な条件で和睦し、北家の権威を高めるつもりだった。八戸を味方につけ、晴政が容易に北家を滅ぼせぬ状況を作り、信直の赦免を勝ち取る、という形で和睦した。
信愛は賭けに勝った。戦が終わり、晴政は信愛の嫡男秀愛に自分の娘の一人を娶わせた。南家がやったことを、今度は北家が宗家に対してやったのだ。
それだけではない。信愛は南部家内でさらにその権勢を高め、元服する晴継の烏帽子親をも務めた。
次期当主の烏帽子親を勤めるということは、その後見になるに等しい。
北家は信愛によって復活したと言っても過言ではない。
が、その間、信直は放置された。八戸にかくまわれ、自らの所領である田子に戻った後も敬して遠ざけられた。
「晴継様に加冠するお前を眺めながら、俺はお前をどう殺すか考えておったよ」
「ははは、おそろしいこと。思えばあの時が人生の絶頂と思っておりました」
「俺はあの時が人生のどん底だったよ」
「ですが、晴継様は身罷られた」
晴政が死に、そして晴継が当主になって一年もたたずに晴継は死んだ。疱瘡だった。
信直を廃してまで家督に付けた子が死んだ。南部家中は混乱に落とし込まれた。
これは信愛にとっても想定外だった。
そこで急遽担ぎ上げたのが、信直だった。
自領にこもっていた信直を引きずり出し、九戸党はじめ反対派を強引に押さえ込んで、彼を家督に就けた。
誰もがその電光石火に驚いた。信直自身ですらも、その動きの速さに舌を巻いた。
「お前にとっては俺や晴継様など、代わりのきく御輿だったわけだ」
「何のことやら」
憎々しさにかすれた声に乗せて、信直は信愛を睨む。
「俺はその時気づいたんだよ。お前が義や理よりも、力を追い求める亡者だとな。お前の忠臣面が、いつも憎くて仕方なかった」
「左様でしたか」
信愛は否定しなかった。
信愛の人生は、北家をどう立て直して大きくするか、ただそれに費やされた。担ぎ上げる主君を変え、それでも脇目も振らずに信愛はその道を進んでいった。
信直の下では豊臣との外交を一手に引き受け、戦場で息子や親族を何人も失いながら彼を支えた。
今の南部があるのは、第一に信愛の功が大きい。そして功を上げれば上げるほど、信愛の家も大きくなった。
その代償として変節の軽侮や誹りも受けた。多くの者から憎まれた。
そして何より信愛に振り回されたのは信直だ。その言葉は、受け止めねばなるまい。
「弟に、政信に娘を寄越したのも、俺の代わりになる御輿を作っておくためだったろう」
「利直様はまだ若く、晴継様のようなことが起きないとも限りませんでしたからね。御輿ではなく、備えですよ」
「よく言うわ。俺より御しやすいと目をつけていただけであろう」
「政信様は素直な方でしたからな」
「素直で良く学ぶ奴だった。……だが、結局死んだ」
信直の弟政信は、津軽郡代として津軽に派遣されたが、津軽為信によって殺された。
「残ったのは御輿の俺と、肥え太ったお前の家だけだ。晴継様も政信も、出来者は皆先に逝ってしまった」
信直は信愛から目を離し、庭を見た。
そこには一本の焼け焦げた小さなりんごの木が生えている。
この福岡城は元々、信直と信愛の最大の敵対者となった九戸党の当主・九戸政実の居城だった。この城が落城した時に、あの木も半ば焼け、それでも葉を伸ばし実を成らすその風情を信直が愛して切らずに残しておいたものだ。
その木をじっと見つめながら、信直はぽつりと言う。
「信愛、お前は才気も器量もあった。無かったのは、御輿自身になる事だけだ」
信直の眼尻から力が消えた。遠くを見るような瞳は、虚空を見つめているように見えた。
「信愛、お前のおかげで南部は大きくなった。だが、こんな不出来な御輿でなければ、もっと上手くやれただろう。政信を死なせて津軽を失うこともなかったし、秋田を攻め損じて愛邦を死なせることも無かった。一戸で秀愛に手傷を負わせて早死にさせることもなかった」
心の内に押し隠していたものをいきなり衝かれ、信愛は言葉を返す機会を逸した。
「利直が担ぐに足る奴だと思ったら、きちんと担いでやってくれ。あいつは悍が強いが、それさえ御せれば良い家督になるだろうよ。ダメなら捨てて構わん」
信直はもう一度信愛を見てにやりと笑った。その笑みは妙なほど若々しく見えた。
「お前のおかげで楽しい人生だった」
信直が目を閉じた。
言葉はかすれていたが、信直の言葉は耳の遠くなった信愛にもはっきりと聞こえた。
「お前のおかげで南部はここまで大きくなった。お前が作った国だ。誇られよ」
「もったいないお言葉でございます」
「来世では、御輿ではない、誠に認められる主となるから、その時はまた、組ませてくれ」
信直はやがて寝息を立てはじめた。
信愛は信直を見つめたまま手を伸ばして、止めた。そして初めて自分の手が震えていることに気付いた。
そして言葉を呑みこみ、静かに自分の主に頭を下げた。
この日から数か月後の慶長四年十月五日。
南部信直は死んだ。享年五十四歳。
葬儀は二戸で執り行われた。
仮にも国持ち相当の当主故、葬儀は大々的で領国を挙げてのものになったが、それはとても静かで穏やかなものだった。
法体の念仏が終わると、遺体は城から野辺に運ばれ、荼毘に付された。
茫々と枯草が広がる野原で、雪がほろほろと舞う中、主が燃えていく炎を眺めながら、信愛は涙を流した。流れると思っていなかった涙だった。
それを見た者たちは痛ましげに信愛へ同情を寄せてきた。『信直公第一の忠臣』の落胆を思ってなぐさめの声をかける者すらいた。その視線を心中蚊虫のようにうっとおしく感じながら、信愛は別の感慨にとらわれた。
(俺を蔑む奴は、居なくなったのだなぁ)
信愛の正体を――栄華を求める亡者である信愛を知る者なら、信愛の涙を「何を白々しい」とあざ笑い、あるいは「面が厚い奴だ」と蔑んだだろう。ほんの二十年前であれば、同情ではなく敵視の視線が信愛を刺しただろうが、それも今はない。
舅だった――そして敵でもあった南信義は死んだ。
時に手を組み時に敵対した御一門の東政勝も既にこの世にない。
九戸政実なら面前で思い切り顔をしかめるくらいはしたかもしれないが、彼も死んだ。
南部の一家中を構成する八戸家の当主・八戸政栄はまだまだ生きているが、根が真面目な彼は信愛を蔑むことも同情もせず、ただ「お疲れでございました」と伝えるだけだった。できた奴だ。
葬儀がつつがなく終わった後、信愛は剃髪し、隠居を申し出た。だが、次期当主利直はそれを強くとどめた。
「北殿なくして南部領は安んじません。今少し、力をお貸しくだされ」
信愛は俗世にもう興味が薄れていたが、その慰留を受けた。
信愛の胸中にあるのはただ、あの日の信直の言葉だけだった。最後の言葉がひっかかったまま隠居をするのは、何か心を咎めたのだ。
慶長五年九月十九日 南部領稗貫 花巻城
襲撃の報が届いたのはその日の夜明け前だった。
「伊達領から複数の兵が侵入しています」
信愛の側役を務める熊谷藤四郎は報告を手早くまとめて、寝ていた信愛を側女に起こさせて説明に入った。
「安俵・学間沢・田瀬。いずれも遠野へと繋がる場所が襲撃を受けています」
「江刺殿が守っておられるところだな。いずれも無事か」
「敵勢とはいまだに合戦中でまだ詳らかではありませんが、江刺勢は小勢、後詰を求めております」
「出さんわけにはいかんが、こちらも手勢がおらんな……」
兵の大半は上杉攻めに同行してこちらに残る兵は少ない。稗貫の大迫近辺の備えとなる乙部兵庫の一隊と、重左衛門に預けている一隊が唯一まとまった兵士だ。
「一揆勢の意図を何と思う」
「遠野との連絡を絶ち、我らのいるこの城を狙っているのでしょう」
「この城が落ちれば南部領の南境を全て制することができるからな」
田瀬や安俵を占拠すれば和賀・稗貫と遠野との連絡が絶たれる。その上でこの要である花巻城が落ちれば、和賀・稗貫の二郡も一揆勢の手中に落ち、南部と関係の良くない遠野も非協力に転じ、伊達につく可能性が高くなる。そうなれば南部十郡中三郡が敵の手に落ちる。
和賀・稗貫は九年前、豊臣の仕置――奥羽平定を潜り抜けて手に入れた領地だ。あの、奥羽の誰もが敗者となり、得るものわずかな争いで、信直と信愛が尽力してようやく得た領土だ。
それが今、全て失われようとしている。
「この花巻城に兵をまとめて籠城すべきではないですか」
不来方や三戸に応援を頼み、留守居の兵が増援としてくるまで持ちこたえる。ひと月も待てば利直の軍勢も戻ってくるだろう。
「いや、兵を動かす」
信愛は断じた。
「江刺殿の手勢が崩れればこの地を維持することも怪しい」
「……伊達は動きませぬか」
「いや、そもそもこの一揆とて伊達の煽りやもしれませぬ。なれば他にも軍勢を準備しておるやも」
者どもの懸念はもっともだ。
この一揆も九分九厘、伊達の手立てだろう。一揆勢すら擬態した伊達勢とも限らない。
理由は分からぬ。だが、伊達は徳川が勝つと確信する何かがあったのだ。二つの戦線を抱える危険を侵してでも、南部を『上杉に味方した敵』として倒すつもりなのだ。
「悩ましいが江刺勢への救援が遅れて遠野境を奪われる危険は看過できぬ。安俵や田瀬が奪われれば、それこそ一揆勢や伊達勢の足掛かりをむざむざ与えてしまうことになりかねん。そうなればもっと危険だ」
信愛は机の上に置いた地図を指し示しながら腹案を披露する。
「重左衛門の組を二つに分け、一隊を田瀬に回す。敵の主力がどこかまだわからん、各地に物見を出す。江刺勢にはもう一隊をさらに分け、少数でいいから物見がてらの増援を送る。撃退できるようであればよし、出来なければ江刺勢と一緒に引いて重左衛門に合流しろ。苦肉の策だが今はどうしようもない。乙部の兵たちは次に伊達の動きが出た時に動かす」
「花巻城はいかがされます」
「備えだけはする。今のうちに町衆を城に籠められるよう、準備をしておけ」
信愛の号に勢いよく諸将が動き出す。信愛も動こうとして――体が思うように動かず、よろめいて尻もちをついた。
自身にぎょっと驚く。幸い、周りの者は信愛の様子を見ていなかった。
老いたのだ、と体が語っているようだった。信愛の胸に急に不安がはびこる。
もはや自分が肩風切って生きられた時は終わる。そしてそれは、今日明日かもしれないと突きつけられたようだった。
(俺も、いずれ去る側なのだな……)
それから、次々に厄報が飛び込んできた。
「志和で斯波の旧臣たちが蜂起した模様!」
「大迫で一揆が起こりました! 城を守っていた田中殿が討死との由」
「乙部殿の手勢を大迫に向かわせろ!」
ただでさえ少ない兵を割いていく。城内に残る兵はどんどん少なくなっていき、既に十七名にまで減ってしまっている。
「いかんな……」
敵は見事に流れを作っている。どれも偶然とは考えられない。
「伊達越前守政宗、並程度には戦上手のようじゃなぁ……」
信愛はもはや敵を確信していた。
これだけの仕込み、恐らくずいぶん前から準備はしていたのだろう。いつでも南部と戦が出来るように。
綿密に下ごしらえをして足元を固め、最良の刻を作り出して挑む――羨ましくなるような戦い方だ。信愛とて力を振るいたいが、肝心の手勢がないでは成すこともままならない。そして、敵が狙うならば今において他ない。
(負けるかもしれんな……)
老いてなお衰えない信愛の思考が、冷徹に悲観的な未来を想像させる。
(まあ、伊達が相手なら悪くないかもしれんな)
二十日の夕暮れ時のことだ。
一人の中年の女が、馬に乗って城に飛び込んできたのだ。
「軍勢を見たと」
「はい、和賀様の紋を掲げておりました」
女は昆土佐の妻と名乗った。元は南部久慈氏の一族だという。
「昆土佐殿?」
「和賀の重臣ですな、豊臣の仕置きで和賀氏が滅亡した時に、詰め腹を切らされたとか」
「我が夫は和賀の御家がおとり潰しになった時、南部と図って和賀家が小田原に参陣出来ぬようにしたのだとあらぬ疑いをかけられたのです」
「そんな話はついぞ無かったがなぁ」
当時まさに南部氏の枢要にいた信愛は聞いたことがないと首をかしげる。
「ええ、北様に私は何の遺恨もございませぬ。私はむしろ和賀家のほうが憎い。御家に尽くした夫を殺した和賀が」
女の目は涙と怒りでぎらぎらしていた。
「――それより、その軍勢の数は分かるか」
「数百はいたかと思います」
「重ねて聞くが、間違いなく和賀の軍勢だったのだな? 伊達勢ではなく」
「はい。見知った顔が何人かおりました」
「ふむ……奥方、よう伝えてくれた。その孝心には必ず報いよう。下がってよい」
「はい! ありがとうございます」
信愛は女をのけた。ありていにいって、気分が悪い。
「……忠臣を騙る者の末路か……」
笑う。俺もあの女の夫のようになるか。
「何を笑っておられます。今この城には兵がほとんどいないのですぞ」
熊谷藤四郎の焦り顔に、またさらに笑いがこみあげてくる。
「士分は何人おる」
「十七人のみです。その手勢を含めても数十名といったところで……」
今この時、北松斎と十七人の士卒に、南部の命運がかかっている。
「……たかが数百、しかも伊達の軍ではなく、和賀の残党だと。ははは……」
「殿……?」
「――――おのれ、おのれおのれぇ!」
信愛は壁を何度も刀で殴りつけた。鞘が割れ、刀がむき出しになる。それでも叩く。
「と、殿!」
主君の狂乱に周囲が狼狽する中、信愛は怒鳴った。
「伊達のクソども、この俺をなめ腐りおって!」
「殿、殿、お安じあれ!」
「伊達の連中、たかだか数百の一揆ばらで、この俺の、首を取れると値踏みしおった!」
伊達は大国だ。南部は土地は広くともその力は伊達の三分の一にも満たない。もとより雑魚としか見られていないのだ。しかも最上領を発った南部軍の本隊はいまだ帰国の途にあり、この地にいる兵はあまりに少ない。
伊達の主戦場は南の上杉だ。南部との戦など片手間の戦に過ぎぬ。だからこそ和賀の残党とその援軍などという中途半端な兵しか出してこなかった。万が一露見した時に言い逃れするための見え透いた小細工だ。
それが信愛の逆鱗だった。
信愛は、蔑まれてきた。
それは仕方ない。無節操に主を変え、自家の安泰と栄華を求める権力の亡者として生きてきたのだ。
だが、侮る者だけは絶対に許さなかった。
「俺をコケにしたのが命取りだ若造め!」
十七人? 百人足らず? それが何だと言うのか。城を守る人数としては充分だ。
「上方かぶれの伊達の公家侍めが。俺と、俺のご家督が泥にまみれて勝ち取ってきたものをかっさらおうなど百年早いわ。この期に及んで俺の邪魔をするくそたわけどもを全員ぶち殺してやる!」
(そうか……)
信愛は唐突に思い立った。自分が何を成さねばならないかも。
(やってみせようじゃねえか)
信愛の腹は決まった。
信愛は集まってきた家臣たちを前に向き直った。
「皆の者聞け! 一揆ばらがこちらに向かっておる。我らは援軍が来るまで守りきる。一日、ここを守れれば我らの勝ちぞ。武名を上げる好機と心得よ!」
『応!』
士気は悪くない。よし、と信愛は笑い、彼らに語りかけた。
「貴様らの中には、豊臣の仕置きやあるいは我ら南部との戦いで家を亡じた者もおろう。旧主に対する忠義を全うできず、無念にほぞを噛んだ者も多かろう」
信愛の言葉に何人かが目を細めた。花巻城の信愛家臣団は在地の者が多い。この地域を治めていた和賀家や稗貫家、奥の斯波家は滅亡し、家臣は離散した。主君を失った彼らを地域の安定のため積極的に登用していったのが信愛だ。
「今ここで負けたら、旧怨を捨て俺に仕えてくれたお前たちの忠義をまた無為にし、お前たちを力足らずの不忠者とすることになってしまう。私はそれを絶対に避けたい」
おお、と感嘆の声が漏れ聞こえた。
「私もまた数十年、南部家に、いや、前のお屋形様、信直様にお仕えしてきた。南部家を思うその想いに私は忠義を尽くしてきたと思っている」
自分でも信じていないことをすらすらと言える自分におかしくなる。目の前で神妙に聞いている者たちも。
「だが、むざむざ一揆勢に城を明け渡したではお屋形様の御恩に報いる事が出来ぬ。信直様が築き上げてきたこの南部を守り、老いさらばえた私が信直様の臣として最後まで生をまっとうするために、どうかお前たちの力を貸してくれ!」
信愛の檄に、兵たちが叫び声をもって返答する。
信愛は矢次はやに指示を飛ばした。
まず、かねてより話を通していた町衆を集めて本丸に籠めた。反乱防止であり、陣夫として使うためでもある。
さらに、本丸の土塁と城壁に征旗を多く掲げさせた。こちらにまだ兵がいると騙すためだ。小細工だが、小細工は怠らないことが大事だ。
信愛は側女に手伝われ甲冑を着込む。元々は稗貫の者共が城に残していった甲冑だ。その胸元には『天照皇大神宮』の文字が他の二神と共に象嵌されている。
天照大御神は虚言を吐く神とされている。第六天魔王が日本の国土を滅ぼさんとした時、偽りをもって欺いたからだという。誓紙に名を入れようものなら受け取りを拒否されてしまうような、嫌われ者の神だ。
(私にお似合いの神だ)
信愛は天を仰いだ。空はもはや暗く、星空がきらきら瞬いている。
「おい信直。お前の忠臣のひと働き、天からとくと見てやがれ」
「来たぞ来たぞ!」
物見の怒鳴り声に、信愛は自らも櫓に上り、敵の軍勢を遠望する。
軍勢はかがり火を焚きながら、花巻城へどんどん突き進んでいる。
「二の丸と三の丸は刻を稼ぐだけでよい、頃合いを見て捨てよ。我らは本丸を守りきる」
花巻城はもともとこの地を以前支配していた稗貫氏の主城だ。数十人で守るにはあまりに大きく、守りきることができない。
軍命を届かせる太鼓の音がする。三の丸の城門に取り付いているのだろう。軍勢の声とともに、城門のきしむ音すら風に乗ってかすかに聞こえる。
皆が不安そうに信愛を見上げるが、信愛はその視線を不快と不遜な顔で鼻を鳴らす。
「何をじろじろ見ておる! さっさと動け、動かねば勝てるものも勝てんぞ!!」
信愛の老人と思えぬ大喝に人々は慌てて動き出す。だが、その動きに迷いはなくなる。
――我が殿が、南部の要が勝利を確信している。これを疑うなどなぜできよう。
鬨の声がだんだん近づいてくる。
三の丸は抜かれ、二の丸も既に踏み込まれた。
「南門で押さえる、油断するな。西門からは機を見て横合いから兵を送れ」
本丸に通じる門は南と西にあり、一揆勢は南へ殺到していた。信愛もこちらに兵を集中させ、南門で先手を担う敵兵たちを信愛のわずかな兵たちが門前で必死に防戦する。時折、敵が南門に注力する隙を伺って西門から兵が飛び出しては、夜陰に紛れて横合いを突き、相手をかく乱する。が、
「奴ら、西門の備えに守りを固めてきました。これ以上の伏撃は危険です」
「そうか、西門は締め切ってしまえ」
南門前は狭い。今は、守り切れている。だが、なかなか勢いが強い。
(このままでは、抜かれる)
(なにかないか。敵の‘穴’は)
「おい、敵はどうなっておる」
信愛は夜目の利く側女――浦子に戦況を問う。
「門前は激しくやり合っており、お味方も苦戦しております。その後ろは……」
浦子は首をかしげた。
「……どうも動きが鈍うございます」
ほう、と信愛は敵のかがり火を頼りに目を細めた。
確かに門前に比べて、敵の動きが鈍い。人数が詰まっているようでもないが、腰が引けている。門前で戦っている者たちとは明らかに挙動が違う。
「後ろにいるのは地下人どもだな、和賀の連中、人がいないので地下人まで引き込んだか」
おおかた稲刈りが終わって暇になった連中を語らって引っ張り込んだのだろう。ますます舐めてやがる。
信愛は浦子ともう一人の側女松子に鉄砲を準備するよう命じる。
「玉は籠めんでいい。ただし素早く錆薬(火薬)を籠めよ」
「は、はい」
信愛は銃を敵の後ろに向けて
撃つ。
撃つ。
撃つ。
「遅い! 早く籠めよ」
「はい!」「はい!」
信愛は何度も撃つ。空鉄砲のつるべ撃ちは、南門に高らかに響き渡る。
「殿、なぜ玉を籠めませぬか?!」
各所の連絡役を務める熊谷藤四郎が戻ってきて、困惑をあらわに言う。
「ほれ見よ、敵の後ろを」
藤四郎は怪訝に目を細め、そして気づく。
「動きが……止まった?」
かがり火が動かなくなった。いや、それどころか後ろに下がる者さえ見受けられる。
「戦慣れしとらん地下人が足を止めおったのよ。これでたとえ南門の連中が働こうと、後ろが続かんでは攻めるも難しい」
後方の異変は、門前の敵兵にも影響を与えていた。
明らかに攻めの圧力が弱まった。武士と地下人が、分断されようとしている。
「地下人ども、まだ本丸に兵がいると勘違いしとる。これで夜が明けるまでは騙せよう」
戦は日をまたいで続くが、どちらも決め手を欠くようになった。だが、人数が少ない分こちら側の兵は疲労が激しい。信愛はその中をひたすら叱咤激励した。
(待てばよい。刻を稼げば、やがて――)
空気が一段と寒くなった頃、物見櫓の者が叫んだ。
「お味方です! 重左衛門様です!」
物見の指差す方向に目を向ける。ゆらゆらと動く松明の光が見える。信愛の遠くなった耳にも、風に乗った馬蹄の音と、オウオウ! という掛け声がかすかに聞こえた。
「来たかぁ!」
信愛は喝采を上げた。
「よし聞いたか皆の衆! 重左衛門が戻ってきたぞ、これで勝てる!」
鈍っていた信愛の兵たちが目に見えて奮い立ち、逆に和賀勢がますます浮足立った。
信愛は櫓から相手を見る。重左衛門の軍勢が一丸となり、城下から猛然と距離を詰める。一揆勢はそれでも数に勝るが、城攻めを続けるべきか重左衛門の軍勢を迎え撃つべきか、迷った。
その逡巡が命取りだった。
「敵が、敵が引いていきます!」
一揆勢は城から引いていき迎撃の姿勢をとろうとしたようだ。敵の侍たちが城門から引いていくが、引いた兵たちと、どう動けばいいか分からない後ろの地下人たちが衝突して、少なくない混乱が起こっている。
「ほれ、ここが切所ぞ、敵の後ろをつつくぞ! 数は少なくとも邪魔する事は出来る」
信愛は檄を飛ばした。一揆勢を城と重左衛門の軍勢で挟み撃ちにする好機だ。
兵たちが追撃を開始する。和賀勢の混乱はさらに広がっていく。
「連中、引き際が下手だ。やはり調練が足りんな」
少数とはいえ後ろから攻撃してくる城勢に動揺し、一揆勢は準備が整わぬまま勢いづいた重左衛門らの攻撃を受けることになった。
戦で名にし負う南部衆である。隙は見逃さず、崩れた隊列の隙間をまるで奔流のようにこじ開けそのまま一気に蹂躙した。
前が崩れれば、整わない後ろもたやすく崩れる。一揆勢は次々に崩れていった。
一揆勢から退き太鼓が乱打される。潮が引くように一揆勢は後退を始める。
重左衛門は深追いせず、ある程度で追撃を切り上げ花巻城に入城した。
「御父上! ご無事でしたか」
「助かったぞ重左衛門」
「田瀬に向かう途中、城の方が騒がしいと気付きました。間に合ってよかった」
直吉はほっとして笑顔を浮べた。年若い息子なりに心配してくれていたようだ。
「もうダメかと思いました」
「老人を侮るでないわ、この程度の戦、何度となく付き合っておる。こんな端戦で負けてお屋形様に迷惑はかけられんではないか」
信愛は息子の肩をがしりと掴んだ。
「――お前に感謝せねばならん。お前のおかげで俺は信直様への忠義を全うできたぞ」
その言葉に重左衛門はおお、と感極まったかのように震えた。おおかた信愛の‘忠義’に感激でもしたのだろう。
「さすが御父上です。この戦、御父上の武名と忠節は轟きましょう」
「浮ついたことを言うな重左衛門、まだ戦のさなかぞ。さっさと守りに入らんか」
はっ! と直吉は嬉しそうに外へ駆け出していった。
信愛は若々しい直吉の背中を眺めた。かつて自分の主君――信直にもあのように若い時期があった。
そしてその隣には、自分がいたのだ。
「好きにしたぞ、信直」
信愛はにやにやと空を仰いだ。藍色の空がだんだんと白じんでいく。遠く、早池峰の山並みから、太陽が顔をのぞかせていた。
虚言の神の朝だ。
「これで俺は忠義者として後の世に名が残る。貴様はさぞ嫌な顔をするだろうな。あの世で貴様のしかめ面を眺めさせてもらうさ」
信直様。ご家督様。
貴方様は決して不甲斐ない主などではありません。
貴方があればこそ、私は我が儘にやることが出来た。
その結果が今の南部なのです。
貴方の成功も失敗も、全て私の責なのです。
私ひとりでは何も出来ない。そう、私は貴方が無ければ何も出来なかった。ここまで登りきることが出来なかった。
南部の家老として力を発揮できたのは、貴方が私の主君であればこそ。
あなたは御輿などではない。私の誠の主君でありました。
あの時伝えられなかった言葉を飲み込んで、信愛は笑った。
「忠義者の化けの皮、死ぬまで羽織ってみせるさ」
さて、もうひと仕事しなければ。
信愛は甲冑を叩いて歩き出した。
・
・
帆船ハッカ

戦国時代の陸奥南部氏および北東北諸氏に興味を持つ歴史オタ。普段はツイッターで小説や雑考察を書いてます。 twitter.com/kotosakikotoko









