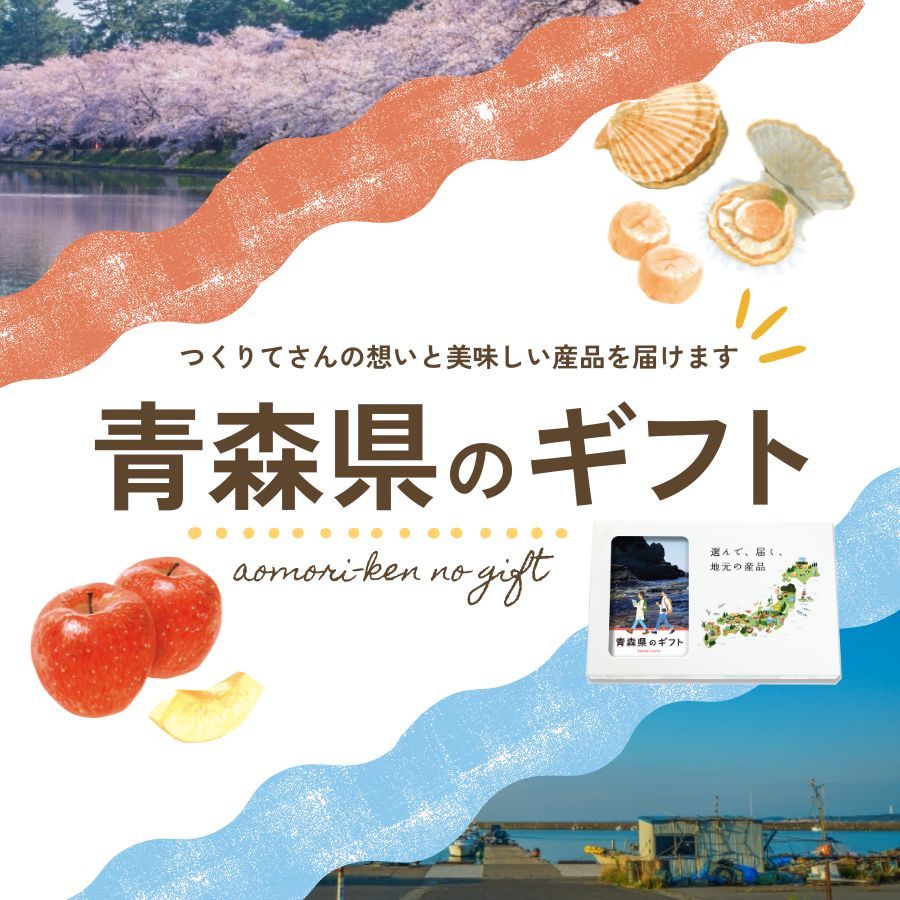**この記事はAIを用いて作成されています**
・
くじら餅の歴史と起源
・
くじら餅の起源については諸説あり、京菓子として創始されたという説や中国からういろうと共に長崎経由で伝わったという説があります。1683年に書かれた『料理塩梅集』に「くじら餅」の名が登場していることから、少なくとも江戸時代初期には存在していたことが分かっています1。青森県の津軽地方へは、北前船によって京都から山形県の最上地方を経由して伝わったとされています23。
名前の由来についても様々な説があり、鯨の塩漬け「塩くじら」に見た目が似ていたという説や、昔は現在より大きなサイズだったためくじらに例えられたという説、また「久しく持つ良い餅」という意味の「久持良餅(くじらもち)」が語源だという説などがあります45。青森県の浅虫温泉では、1907年(明治40年)に初代吉兵衛が津軽鯵ヶ沢で習得した製法をもとに、日露戦争で傷ついた軍人たちの療養食として「久慈良餅」と名付けて製造を始め、これが地域の名物として定着していきました67。
・
青森と山形の味の違い
・
青森と山形のくじら餅は同じ名前を持ちながらも、味や食感に明確な違いがあります。青森のくじら餅は水気を抑えた羊羹に近い外観で、甘すぎず、ちょうどよい弾力の歯ごたえが特徴です1。特に永井久慈良餅店のものは、津軽米粉とこし餡などから作られ、くるみの食感がアクセントとなっており、もっちもちの食感が楽しめます2。
一方、山形のくじら餅は水分量が多く見えてもっちりとした食感で、白砂糖味、黒砂糖味、しょうゆ味、みそ味など多彩な種類があります13。特にしょうゆ味は甘じょっぱさが、みそ味は噛むごとにみその旨味が感じられる独特の風味が特徴です1。また山形では桃の節句に食べる習慣があり4、腹持ちが非常に良いことから、かつては非常備蓄食としての検討もされたほどです1。両地域のくじら餅は、同じ名前でも水分量による食感の違いが最も明確な相違点と言えるでしょう。
・
鰺ヶ沢の鯨餅
鰺ヶ沢の「鯨餅」は青森県内のくじら餅の中でも最も古い歴史を持ち、江戸時代の書物に記された京都の伝統菓子が北前船によって伝えられたものです12。白と黒の二層になった外観が鯨の皮の断面に似ていることが名前の由来とされています1。原料はうるち米、もち米の粉、小豆、砂糖というシンプルな素材で作られ、モチモチした食感と上品な味わいが特徴です1。
かつては鰺ヶ沢町内に4、5軒の鯨餅店がありましたが、現在では「本舗 村上屋」1軒のみが明治創業以来、鯨餅だけを専門に作り続けています13。この鰺ヶ沢の鯨餅の製法は浅虫温泉の永井久慈良餅店の初代吉兵衛翁によって習得され45、後に「久慈良餅」として浅虫温泉の名物になりました6。鰺ヶ沢の鯨餅は、北前船文化の一つとして青森県の食文化に深く根付いた貴重な伝統菓子と言えるでしょう7。
・
永井久慈良餅店の伝統
・
永井久慈良餅店は明治40年(1907年)に浅虫温泉で創業し、100年以上にわたり伝統の味を守り続けています1。初代吉兵衛翁が郷里の津軽鯵ヶ沢で習得した鯨餅の製法を基に、「いく久しく慈しまれる良い餅であるように」との願いを込めて「久慈良餅」と名付けました12。
当店の久慈良餅は、上質の津軽米を製粉し、こし餡・砂糖などを混合して蒸し上げた薄い小豆色の蒸し菓子で3、ところどころに入ったクルミの風味とむっちりとした歯ごたえが特徴です42。保存料・添加物を一切使用しない昔ながらの製法にこだわり15、賞味期限は製造から7日間と短いものの42、青森市民なら誰もが知る郷土の味として親しまれています6。夏場は食べる前に30分ほど冷やすのがおすすめとされています2。
他にも菊屋もち店でも販売されており、「甘さ控えめで後味すっきり」「昔ながらの味」と口コミでも評価されており、永井に比べるとしっとり、ねっとりした食感との違いが感じられます。
・