【小説 津軽藩起始 油川編】序章 堪る不満 天正九年(1581)春
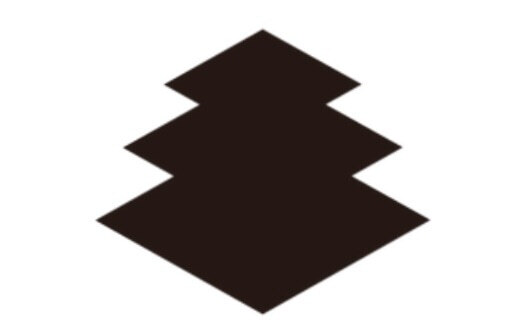
→→第二章へ←←
力の向かう所
3-1 夢は、もはや夢。
この頽落では、再び戦にいこうなど考えるはずはない。殿は色事にうつつを抜かし、以前のような真剣味が感じられぬ……。為信の評は特に他国者の間で悪くなっていた。どれが真でどれが嘘かなんてわからぬが、このような話が流れる時点で、昔とは違うのだ。
・
“大浦家”として戦を起こす気がないのなら、我らはどうなる。戦こそ土地を手っ取り早く奪えるいい機会なのだ。なにを防風だ治水だと世迷言を……。何十年かかる夢物語を言われても、もううんざりだ。
……我らは津軽の殿様を求めてやってきた。最初の頃はどんどん戦を仕掛け領土を広げていたし、防風と治水にも期待を持っていた。ところがどうだ。戦はなくなり、防風と治水もやってみると大概時間がかかりすぎる。
・
では“津軽”を見捨てるか……。日ノ本を探して他に、他国者に寛容な土地はあるか。さらに北ならば誰が来たとて大歓迎だろうが、何分苦労をしていると聞く。ならばどうせよと。
・
・
……ここは浪岡、長谷川三郎兵衛の屋敷。以前あった四日町(現、字天王)の屋敷は代官となった白取伊右衛門に譲り、自分らは新しく横目町の端(現、字浪岡)に移った。ここは浪岡町屋の西の果てで、体よく繁華街から追い払われた格好だ。しかしそれでも扱う商品は多く、他にこれほどの大きな商人はいないので、多くの民がやってくる。結果として賑わいがこちらへと移動し、城の周りが次第に廃れていったのは後の話……。
商家長谷川は単に商品を扱うだけでなく、まだ浪岡北畠が健在だったころより、為信の調略の拠点でもあった。そして彼らは西浜出身という立場を生かして、積極的に他国者を浪岡へ流し、浪岡近郊に住まう他国者をまとめ上げていた。同じ西浜に勢力がある兼平配下の者も出入りし、南部支配下に戻ってしまった浪岡を監視し大浦家へ逐一報告している。
3-2 ”まつろわぬ民”とは?
長谷川三郎兵衛の屋敷は、夜な夜な他国者や不埒者の鬱憤を晴らす場として使われた。昼間は商店として、夜は賭け場として機能する。……今や浪岡が南部直轄領へと代わり、為信時代の過ごしやすい暮らしはない。南部の代官様にこびへつらい、ことあるごとに税を納めなければならぬ。しかも聞くところによると……在来の者はそのようなものを取られていないらしい。さらに彼らは何かと我らを敵視する。浪岡は実質……二分されてしまった。
屋敷の奥の納屋で賽子を転がすは生玉角兵衛。茣蓙に胡坐をかいて待つは野郎ども。角兵衛の後ろで目を光らすは……ヤマノシタ。……賽の目は ”六” を示し、その数を見た野郎どもは……笑う者、泣く者、地団駄踏む者さまざまだ。
その表情の一つ一つをヤマノシタは臨み、気づかれぬようにニヤリと面白がるのだ。彼は他国者や不埒者を束ねる長の一人で、浪岡に根を張って四年年経ったか。その短い間でもお上が二度変わり、人の激しい移り変わりが感慨深い。そして新たにやってきた者がここにも一人……角兵衛だ。
角兵衛は畿内にて本願寺に付き、織田に破れた。摂津より遠く津軽の地まで流れ着き、ヤマノシタに囲われている。その性格は厚く、彼を慕って何人もの同志が津軽へと渡ってきた。つまりは面倒見の良い男……というところが気に入っている。表は豪快にやってのけるが、裏では仲間へ非常に細やかな気配り。だからこそ彼はヤマノシタのお気に入りだ。
そんな角兵衛は賭け事が引けた後、各々が申す鬱憤に対してこう応えた。
「戦を外に仕掛けるのはダメ、かといって他所にいっても苦労は同じ……ならば内側に向けてみよ。」
野郎どもは角兵衛へその汚らしい顔を向ける。
「摂津の人間から見れば、奥州人は十二分に狄だ。北奧は特にそう。だが来てみてわかったことが……お前たちも私と同じ日ノ本の民だった。”まつろわぬ民” では決してない。ただ……この津軽の中にも、米や銭を一切納めぬ奴らがいるのお。」
3-3 蝦夷
野郎どもの一人が笑いながら話し出した。
「それは……エゾ村のことか。」
「ああ、そうだ。あいつらは平原に家を持っているくせに、その周りの土地を耕そうとしない。川沿いに陣取っているやつらもおり、さぞ恨めしいではないか。」
“恨めしい……”
その言葉を聞いて、角兵衛と同じ他国者らは大いに騒ぎ出した。“確かにそうだ” “なぜそのような存在がある” と。一方で津軽出自の不埒者らはピンと来ていない。その中の一人が言うには……
「なあ。恨めしいも何も、彼らは狩や漁などして暮らしている。たまに物々交換に来るくらい、殿にも大きな獲物を献じているぞ。」
角兵衛はその言葉に対し、ゆっくりと長く首を振る。
「いいや、それはお前らが見慣れているからだ。狩をするだけなら山奥に住めばよい。摂津ならそうだ。マタギは人里より遠く離れたところにいる。漁であれば湊沿いの商家の立ち並ぶ前に船をつけ、田畑のど真ん中ではなく町屋で暮らしている。これが”常道”というものだ。……そしてここにたどり着いた他国者は多くなった。あの土地をお譲り頂いても、バチは当たるまい。」
酒もほどほどに入っているので、他国者を中心に多くの者が “そうだ、そうだ” と賛同する。かえって在地の者は慌ててしまった。
「いや……しかしエゾ村から嫁をとった者、または入った者もおるし。風俗こそ違えど田畑を耕したり、我らとそんなに変わらない者もおる。それに、あ奴らが昔から暮らしている土地ぞ。これまで我らは仲良くしてきた。……それをそちらさんのマタギと同じように言われても……の……。」
すると角兵衛、強めに言い返す。
「ならばお前たちに聞くが、どこからが狄でどこまでが “俺ら” なのか。誰もが信心している仏門にも頼らず……このさい宗派などどうでもよい。日ノ本の民でない者を追い払い、我らが土着する。」
日ノ本は有史以来そうしてきた。今更、何を恐れている。
3-4 力を振るうならば
黙って聞いていた野郎頭のヤマノシタ。頭上の出来物を取ろうと髪の毛をかきむしり、すると否応なくフケが出る。手の爪に少しついた白いものを息を吹きかけ、遠くへ飛ばす。そのつまらなそうな仕草に気付いた角兵衛は、なぜお頭は至極落ち着いたままでおらすのかと疑問に思った。そこで恭しくヤマノシタへ寄り、一つ尋ねる。
「お聞きの通り、私の考えはこうです。他国出身の同志も納得してくれています。しかし頭は浮かぬ顔をしておらす。それはなぜでしょうか。」
鼻で笑ったヤマノシタ。仕方なしに口を開く。
「要は力を持て余しているのだ、お前らは。力の向きが外へ行くならば、以前のように御所号が倒れるほどのことが起きる。だが今回は内側へ向かう……“外” へいけないのだから、“内” を喰らうしかないのだろうさ。」
正直なところ、どうでもいいとも思えてしまう。成すがまま、成るがまま。ヤマノシタの生き方はこうだ。明確な意思を持って動いたかつての首領である万次とは違う。ならばなぜこうして頼られる立場になったかというと……最後には己の身を自由に使えと。つまりは神輿として。さらには窮地に陥った仲間をどんな理由であれ援ける。これが彼の信条だったからだ。
ヤマノシタはこうもと言った。
「ここで俺が止めても、同じような考えの他国者が土地を奪い始めるに違いない……。そして最後には為信が倒れる。乱れるに乱れ、最初はエゾ村だけだったものが、普通の農村へ牙が向かい、果ては城を奪うことになる。……盛り上がれば、そういうことだ。」
その言葉を聞いて、角兵衛は戸惑う。そんなことをするつもりはないと必死にとりなすのだが……
「危うくなったら俺を頼ればいい。逆にこれがきっかけで為信が倒れるのなら……それも運命だ。」
3-5 はみ出た存在
狄の住まうエゾ村は、パッと見ただけで違いは判らない。家々の形は同じだし、人の顔形も他国者からすれば見分けつかぬ。よーくよく覗くと住まう人の風俗が違い、角兵衛などの摂津の人間からすれば歪な文様がたまに見受けられるくらいで。しかし彼らは年貢を納めていない。日ノ本のシステムから逸脱した存在が “狄” なのだ。代わりに我らが土地の所有者になり、津軽の民として米や労役を果たすのだ……。
大義名分を振りかざし、荒武者と化した生玉角兵衛の一団は、津軽にあるエゾ村の一つの様子を林に隠れ窺うが……。やはり戦国の世とあって、相手もそれ相応の武備を持っているようだ。毒矢の扱いは我らより手馴れておろうし、横に付ける太刀は我らの物と同じ……火縄だって獲物を仕留めるために使う。油断ならぬ。
家々の入口を覆う暖簾のような布掛け、その独特な文様の先より出るのは、さほど我らと変わらぬ顔の狄の奴ら……。海を渡ると顔形の違いは際立つというが、津軽の狄は本当に見分けがつかぬ。ここで角兵衛にも少しばかりの罪悪感が芽生える。……いや、これは我らが生きるため。“狄” という賊を倒し、土地を平らげるが我らが使命。……しかし仏門に頼る身なれば、特に私は本願寺より “休西坊“ という法名も頂いている。狄が仏門に帰依するならば我らと同じところで暮らせばよいし、同じように田畑を耕し年貢を納め、労役を果たせ……。
荒武者どもは夜になるのを静かに待ち、人の往来が鎮まるのを待つ……この場合、交易で出入りのある在来の者は敵ではない。“狄” でない。彼らを巻き込んではならぬ。ひたすら刻が経つのを目を瞑って待った。その場に座し、次に両手で太刀を鞘のまま握り、硬い地面につけ、全重心を前の一点へと傾ける。小刻みに実が震えるのを抑えるためだったが、次第に揺れが大きくなっていくような気もしたが、これは一団を率いるわが身にかかる責の重さのためか。
……そして日は落ち、村の人々は眠った。
フクロウが一声鳴いたところで……角兵衛は采配を振り下ろした。
蝦夷荒
3-6 罪はない
突如として暗闇に響く鬨の声。何が起きたと寝ぼけまなこで起き上がるエゾ村の民。そして家々の口から出てみると、すでに荒武者らによって村が蹂躙されている。隣の小屋は火をかけられ、真昼のような明るさ。怒号と悲鳴がこだまし、エゾ衆は一方的に倒されていく……。襲う側である角兵衛らからすると、やはり彼らは自分らとは違う存在なのだと思って安心していた。なぜならいくら哀しい声を聞いても、言葉の意味が一切わからぬ。そこで犬や猫と同じだと考えれば……罪の意識を感じずに済む。
エゾ衆の男は勝ち目が薄いながらも勇敢に戦い、荒武者の幾人を倒した。争っているうちに他の村へ女子供を逃げさせ、さらに数の多い敵へと向かっていく……。
鮮やかな赤い色は村の全てを覆い、その上にはどす黒い煙が夜空の星を隠す。下を見れば野郎どもの争う声、鎧のかち合う音、刀が交わる生死の境が間近にある……。よろめいて横に反れれば、たちまちこの世から意識が消える。動かなくなった物体だけがその場に残り、その “モノ” を勝者が踏みつけて先へ進む。
いまやエゾ衆の魔よけの意味を持つ文様も、火の粉によって見るにいたたまれぬ酷さ。そして灰になって尽きる。架空の魔物を防げても、実際に目の前にいる敵に効果はなし。屋根から矢を射る者、家々の隙間から鉄砲を放つ者もいたが、後ろから迫る火の勢いは甚だしく、前へ進もうが下がるにも逃げ場はない。家は柱から折れ、屋根の上にいた者は身ごと落ち、鉄砲を放つ者は崩れてきた壁に押しつぶされた。
表では荒武者どもが闊歩し、残党を殺していくのみ。卑怯な手を使った彼らは、その目的通りにエゾ村の一つを潰すに至った。ただし村から逃れた者も多く、他のエゾ衆へと一気に話が伝わっていく。そしてこれは六羽川合戦以降……仮初の平和を維持してきた津軽を戦乱へと再び戻す……。一応ここで断りを入れておくが……これは他国者の一つの集団が勝手に起こした出来事であり、大浦家が命令したことではない。だが他国者を多く取り込んでしまっている大浦家に、これを正しく罰することができようか。
3-7 迫る悲劇
津軽にはエゾ村が大小含め百近くある。これらは全て和人と穏やかに暮らしてきた。互いに血縁関係を持っている者もいたし、次第にその垣根もあいまいなものになりつつある。それでも ”アイヌ” としての文化と誇りを捨てない村もあったし、津軽衆もわざわざそのことに干渉することがなかったので、至極平和だった。
しかし戦国の世に至り、中央より流れてきた他国者が大数をなす。彼らは大浦家に力を貸す代わりに、土地を求めた。戦に勝てば敵の所領が恩賞として与えられ、不埒者に成り下がっていた彼らは定住者に変わっていった。さらには大浦家も人を求め、新たなる耕作地へ積極的に人をあてがった。……だがそのシステムは、大浦家が南部に再服従することで決裂した。津軽に人が集まりすぎ、防風と治水による開墾だけでは足りぬ。外を獲れない以上は……中を喰らう。これは弱肉強食の世界で生きてきた流れ者=他国者の当然なる原理である。
生玉角兵衛とその他国者の一団がエゾ村を襲ったことを契機として、他の者らも我先にとエゾ村を狙い始めた……。彼らは我らとは何もかも異なる “狄” なのだから、襲ってもいいのだと。これは在来の者にとって決してできぬ発想だ。
当然だが他のエゾ村の者らはこの事態に驚き、襲ったのが誰かもわからないし、同じことが起きまいかたいそう不安がった。そこで村々の頭が代表して二十名は大浦城へと向かった。ゆっくりと町の様子を見ながら……険しい顔で城への道を進む。城の袂に住まう町衆は……何事かと固唾をのんで見守る。……その様に子供は怯え、思わず泣き出してしまう。道を歩むエゾ衆の一人がそれに気づき、わざと子供を笑わせようとニタっと笑ってみた。……この時はエゾ衆にも余裕があった。もちろん村を焼くほどの狼藉だし仲間が多く死んでしまっている。許すわけにはいかないが……まだ彼らはこれから起きるであろう騒動に気づいていなかった。事が起きたのはまだ一回のみだったし、話を聞いただけの襲われていない者らすれば、わが身の外で起きたような出来事。大切な仲間の事なので怒ってはいるが、まだ事態を呑み込めていないというか……。もちろん不埒者の集団を捕まえて殺し、今後このようなことがないように取り締まってほしいと伝えはするが、これまで大小こそあるが諍いはあった。今回の訪問は、折角だから久しぶりに皆で挨拶も兼ねようくらいの意味合いも含んでいる。
・
・
・
地獄は、目の前。
3-8 嘘っぱち
エゾ村の頭たちは、城内の大広間に通された。ただし上座には誰もおらず、対面して武門の男一人と落ち着いた色の絹を着た男……深みのある茶色……正確には朽れた葉の色と紺色の帯。歳相応に皺を持つ穏やかな老人が待ち構えていた。
隣の武門の男より、あたかも権力を持つのはこの老人のようにも思える。そしてその二人に侍るは通辞。エゾ村と津軽衆は違う言葉を持つ集団だが、さすがに同じ土地に暮らす者同士であるので、若干のイントネーションは判る。だがこの場合は無駄な誤解を避けるため、大浦家側で用意したという。
・
・
さて、武門の男が第一声。
「私、大浦家臣で譜代の兼平綱則と申す。」
次に横を見やり、続けて話す。
「そしてこちらにいるのは、商家ながら昔より当家に並々ならぬ貢献をしておらす。鯵ヶ沢の長谷川理右衛門殿です。
理右衛門は穏やかにエゾ衆へ会釈をした。エゾ衆もつられて頭を下げる。兼平は長谷川の化け面を少し見て……さてと再びエゾ衆へ顔を向けた。
・
「話は事前に承っておる。この度の主犯もすでに知れた。この理右衛門の嫡男は三郎兵衛殿と申し、浪岡で分家し商売してなさる。そこでお抱えの生玉角兵衛という浪人が率いる集団がしでかしたと聞いた。」
そこでエゾ衆の頭の一人は “こちらに彼らの身柄を引き渡してほしい” と伝えるが……
・
・
「ところが角兵衛が申すに、大浦領内のエゾ村に盗賊が逃げ込んだらしい。我らはそれを追っていたが、エゾ村の者は彼らを匿ってしまった。公然と刃を向けてきたので、わが身の危険を感じ、争うに至った。そこ過程で火が村についてしまったことは申し訳ないと。」
・
……そのような話は聞かぬ。誰も申していない。エゾ衆の頭たちはその場に立ちあがり抗議した。だが兼平は……浮かぬ表情をしたまま。目を合わせようとしない。
3-9
兼平も十分にわかっている。だが人との繋がり、絡み合う利害。特に兼平氏は本拠の兼平村とは別に、西浜の田野沢(=大戸瀬漁港)も勢力圏だ。いつしか鯵ヶ沢の商家長谷川と合同で他国者の引き入れを行うようになっており、言わば他国者の利益の代表者でもある。特に六羽川合戦以降、深浦が安東領になったおかげで、目と鼻の先まで安東領に変わった。(現代の深浦町の領域ではなく、港町の集落としての深浦と思ってほしい)緊急時に対応する武力として他国者が入用なのだ。
エゾ衆の言い分はわかる。他国者が嘘をついているのもわかる。だが馬鹿正直に “嘘” を見抜くわけにはいかぬのだ。罰するとしてもそれは軽いもの……。なにもエゾ衆にその身柄を引き渡し、むざむざと殺させるわけには参らぬ。何も利が欲しいわけではないが……それで家の者は食っていけるのだ。
もちろんエゾ衆が交易でもたらす利も見過ごせない。彼らは北方との繋がりを以て、珍しい動物の毛皮や食べ物などを仕入れてくる。それら商人は商家長谷川にとっても重要なモノ。理右衛門はどのようにお考えであるか……と、兼平は隣の理右衛門をチラリと見る。
・
すると理右衛門はたいそう穏やかに、エゾ衆へこう伝えた。
「角兵衛というやつは生粋の乱暴者故、他の者はそうでもないから安心なされよ。彼も教え諭せば同じ津軽の民になりえる。赦してはくれぬかのう……。」
・
“しがらみ” ということでいえば、エゾ衆と商家長谷川は商品取引で密接に関係している。エゾ衆は持ってきた商品を商家長谷川に売り、代わりに和人の産物を得ているからだ。なので兼平に強く文句を言えても、理右衛門にはどうもしり込みしてしまう。……そして理右衛門は同じような口調で続けた。
「ただし他国者が狼藉を働いてしまうは、落ち着いて暮らせる場所がないからだろうの。そこでじゃ。エゾ村に自由に他国者が出入りすることを許してほしい。そして耕しておらぬ土地を彼らに貸し、代り彼らから産物をいくらか貰えばいい。どうであろうか、草ぼうぼうにしておくよりかはいいと思うが。」
3-10
“蝦夷荒”という現象が為信治世の津軽で起きたらしい。あまり知られていない事実だが、津軽にはエゾ……つまりアイヌが多く存在し、各々エゾ村を営んでいた。その存在が危ぶまれることがあったからこそ、大浦家に対して反乱を起こしたのだ。
・
商家長谷川と兼平より今後のことを聞いた他国者ら。そのほとんどが土地を借りることを望み、誰もが雪崩をうってエゾ村へ向かった。……ただし一部の者は大変横暴で、エゾ村へ堂々と押し入り、食料は盗るは娘を奪うなどと狼藉を働いた。もちろんエゾ衆は“約束が違うぞと”いきり立つ。
・
そして津軽衆を含め、和人……を信用できなくなったエゾ衆は、武器を持った。
・
入植する誰もが都合の良いようにとらえ、その顛末はこの様だ。結局は他国者からすればエゾ衆は“狄”でしかなく、津軽衆以上に違う存在。風俗も違えば言葉もわからぬ、まるで動物のよう。角兵衛らからすればそのような目線となってしまう。だからこそ “土地を借りて耕してもよい” と許された時には、エゾ衆に感謝する心よりも、そこで暮らす彼らを教え諭そうという意識の方が上回った。残念ながら“この”あたりが津軽衆と感覚が違っていた。津軽衆……在来の民からすれば、同じ土地に暮らす仲間。風俗は違えど互いの言葉はなんとなくわかるし、さらには血縁がある者もいるほど。長い年月を経て、明確にどこからがエゾ衆でどこからが津軽衆か、その境界があやふやになっている村も確かにあった。それでも坂東や上方からやってきた他国者からすれば、明らかに違うように見えたのだろう。そして彼らを下に見た。その意識を持っているからこそ、“教え諭そう”という行動へとつながる。そして“教える側”なのだから、土地の耕作者としてエゾ衆に我らと同じように鍬を持たせようとした。エゾ衆の存在を軽く見たからこそ、先の村を焼く事件が起きたともいえる。
・
他国者らは兼平と商家長谷川が申したと建前を口にし、我が物顔で村へと入る。そしてエゾ衆をこき使おうとし、お前らは“教わる側”なのだから俺らに従えと……。
・
・
残念なことに、エゾ衆から見れば津軽衆と他国者は似た者同士。津軽衆とは近しいが、同じ和人でしかない。嘘をついたことに変わりない。生命の危機ならば……徹底的に抗おう。
・
・
こうしてエゾ衆は蜂起し、戦の収まった津軽に新たなる火種が生まれた。
→→第四章へ←←









