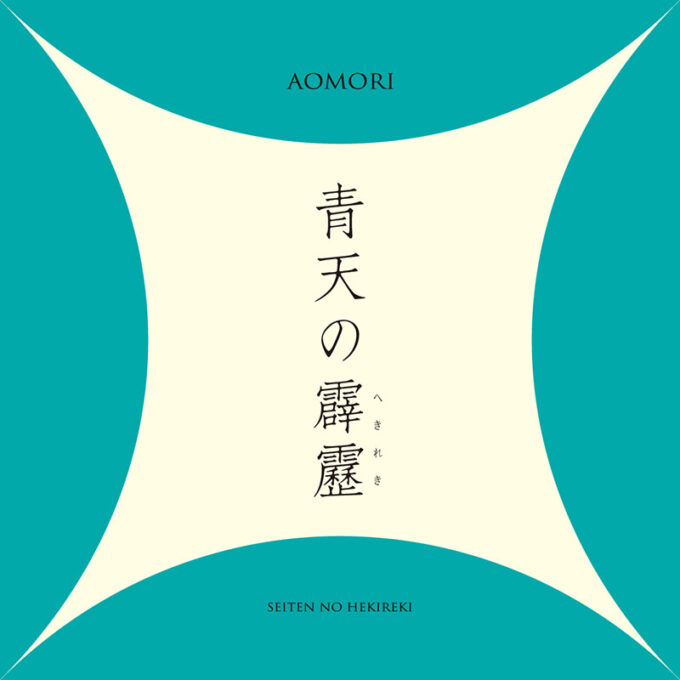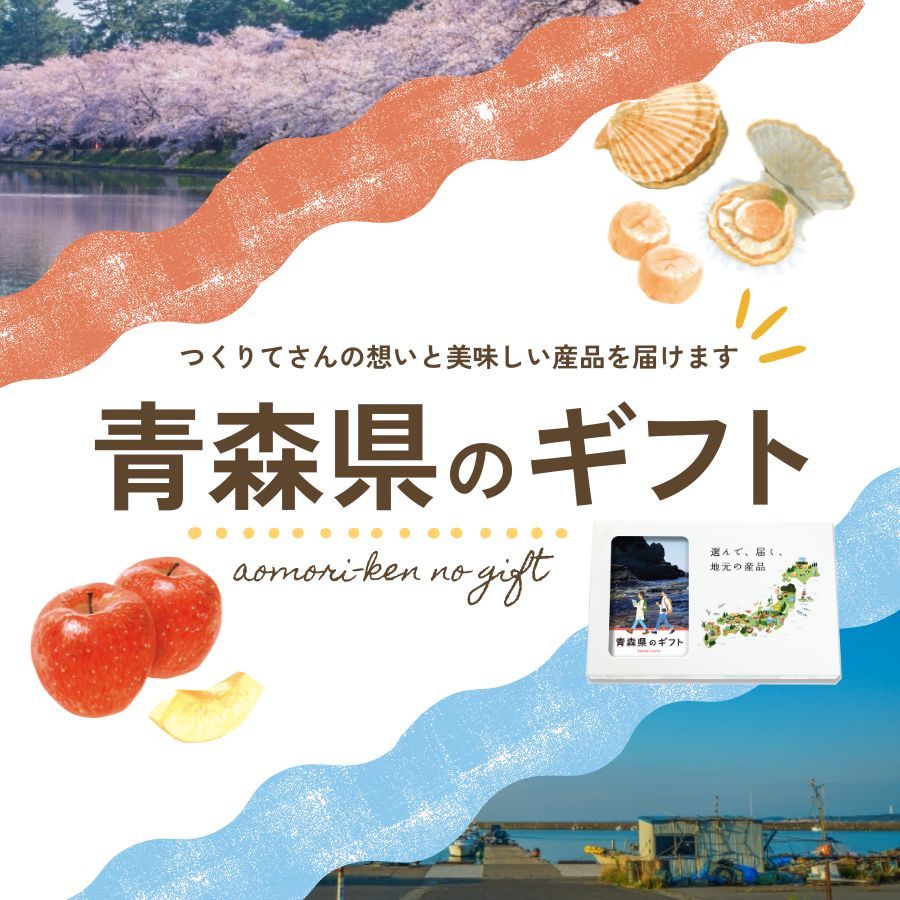青森県は、古くから米作りが盛んな地域として知られています。しかし、厳しい寒冷地という気候条件が、米の品質評価に長年影を落としてきました。そんな中、2015年にデビューしたブランド米「青天の霹靂」は、青森米の歴史を一変させる画期的な存在となりました。この記事では、その誕生から現在までの軌跡を振り返り、青森の農業がどのようにして全国トップクラスの評価を獲得したかを探ります。
・
青森米の課題と開発の始まり
青森県の米作りは、北国特有の低温との闘いの歴史です。津軽平野を中心に大規模な農業が展開されてきましたが、食味ランキング(日本穀物検定協会主催)では、なかなか最高評価の「特A」を獲得できませんでした。低温による生育の遅れや、食味の低下が主な原因でした。この課題を克服するため、青森県は2006年(平成18年)頃から、新品種の開発に着手します。目標は、耐冷性と耐病性を備えつつ、極めて優れた食味を持つ米を作り出すことでした。
開発チームは、数多くの交配を繰り返し、約10年にわたる試行錯誤を重ねました。親品種として「夢の舞」や「青系157号」「青系158号」などが用いられ、出穂期を8月上旬に設定することで、冷害を最小限に抑える工夫がなされました。
・
デビューと衝撃の評価
2015年(平成27年)、ついに「青天の霹靂」が市場デビューを果たします。名前の由来は、青森の「青」、広がる北の空を表す「天」、そして稲妻を意味する「霹靂」から来ており、「青天の霹靂」のように驚くほど美味しい米というニュアンスが込められています。
デビュー年産米は、食味ランキングで青森県産米として初の「特A」を獲得。粒が大きくツヤがあり、適度な粘り気と甘み・旨みのバランスが絶妙で、あっさりとした後味が特徴です。一口噛むと徐々に甘さが広がる食感は、冷めても美味しさが持続する点で高く評価されました。
この快挙は、青森の農業関係者を大いに勇気づけ、県全体の米作りに活気をもたらしました。試験栽培は平成25年から行われており、津軽中央や津軽西北地域の限定農家による厳しい栽培基準が設けられました。
・
継続的な成功と現在の地位
デビュー以降、「青天の霹靂」は食味ランキングで連続して「特A」を維持しています。2024年現在も、青森県のトップブランドとして君臨し、栽培は登録制の農家に限定され、品質管理が徹底されています。
他の人気米、例えば「つや姫」や「コシヒカリ」と比較しても、粒の大きさとさっぱりとした味わいが差別化要因となっており、海鮮丼やおにぎりなどの料理に特に適しています。
購入方法も多岐にわたり、JA全農の直販やオンラインショップで入手可能で、ふるさと納税の返礼品としても人気です。青森の米作りが「低温の壁」を乗り越えた象徴として、全国的に認知されるようになりました。
・
振り返って:青森米の未来への教訓
「青天の霹靂」の誕生は、単なる新品種の登場ではなく、青森県の農業史における転機でした。10年の開発期間を通じて培われた技術は、他の品種開発にも波及し、県全体の米品質向上に寄与しています。気候変動が進む中、耐冷性に優れたこの米は、持続可能な農業のモデルケースと言えるでしょう。青森の空の下で育つこの米は、今後も多くの人を驚かせ続けるはずです。もし機会があれば、ぜひ一度味わってみてください。
・