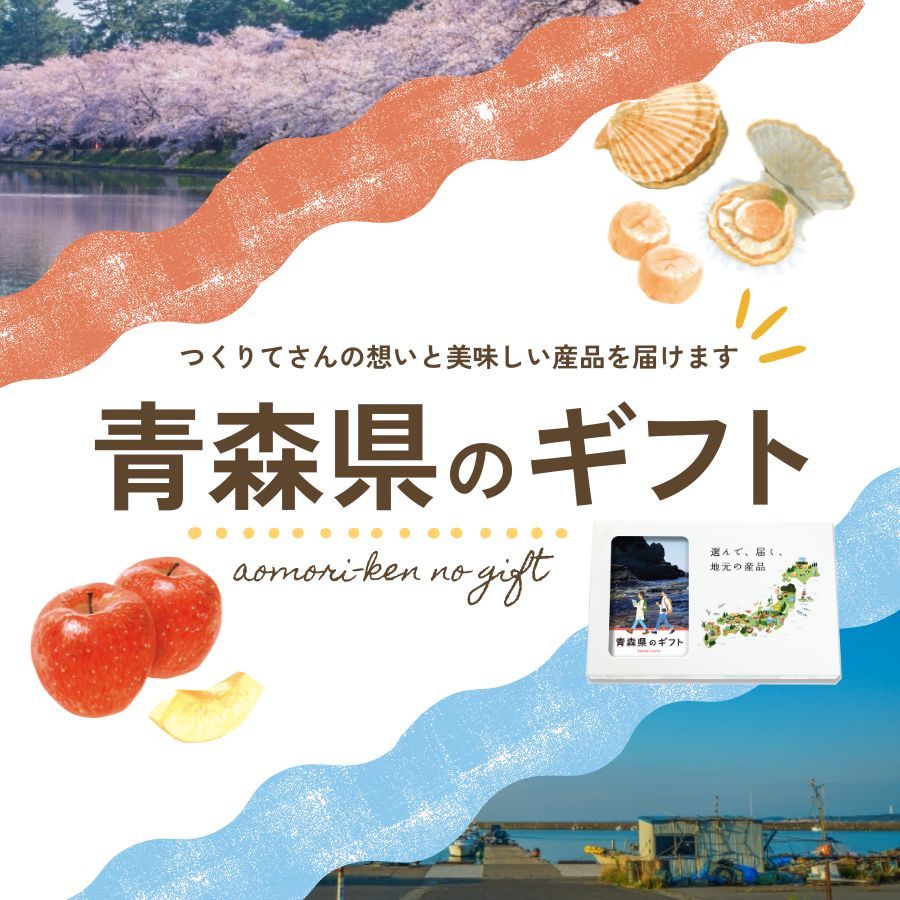**この記事はAIを用いて作成されています**
けの汁は青森県津軽地方から秋田県にかけて愛され続けている郷土料理で、大根や人参、ごぼうなどの根菜類と山菜、凍み豆腐を細かく刻んで煮込み、味噌で味付けした栄養豊富な汁物です。小正月(1月15日)の行事食として作られ、「粥の汁」が訛って「けの汁」と呼ばれるようになったとされ、大鍋でたくさん作って数日間温め直して食べることで、家事を担う女性が休めるという役割も果たしてきました。
・
和徳城落城伝説の真相
・
この栄養満点の汁物が戦国時代の城攻めと結びついているのは、1571年の和徳城落城にまつわる壮絶な伝説があるからです。津軽統一を目指す大浦為信(後の津軽為信)が石川城を奇襲攻撃した同じ日、勢いに乗った為信軍約900人が三方から和徳城を包囲しました。城主小山内讃岐守はわずか50人の手勢で出撃しますが、圧倒的な兵力差の前に討ち死にし、城兵140人も一人残らず戦死する凄惨な結果となりました。
この落城の最中、兵士たちが有り合わせの野菜や材料を米と一緒に鍋に入れて食べたのが「けの汁」の起源だという説が地元に伝わっています。戦場の緊迫した状況で生まれた即席料理が、後に津軽地方を代表する郷土料理として受け継がれたというロマンチックな物語として、現在も和徳稲荷神社には「けの汁発祥の地」の石碑が建てられ、地元の有志によって語り継がれています。
・
けの汁の味わい
・
けの汁の味は、一言で表現するなら「優しい家庭の味」です。昆布や煮干しでとっただしに味噌を溶かした基本的な汁の味に、細かく刻まれた野菜や山菜から溶け出した旨みが重層的に絡み合い、深みのある複雑な風味を作り出します。特徴的なのは大豆を潰した「ずんだ」が加わることで、汁全体がまろやかになり、ほんのりとした甘みと豆の香りが全体を包み込みます。
作りたてよりも翌日以降に温め直した方が美味しくなるのがけの汁の最大の特徴で、これは各具材の味が一晩かけてじっくりと汁に溶け込むためです。大根や人参の自然な甘さ、ごぼうの土の香り、山菜のわずかな苦味、高野豆腐の旨み、そして味噌のコクが時間をかけて調和し、「具材が多いのに味がバラバラにならない」という絶妙なバランスを生み出します。家庭によって味噌の種類や具材の組み合わせが異なるため、「おふくろの味」として各家庭独自の味わいが受け継がれています。