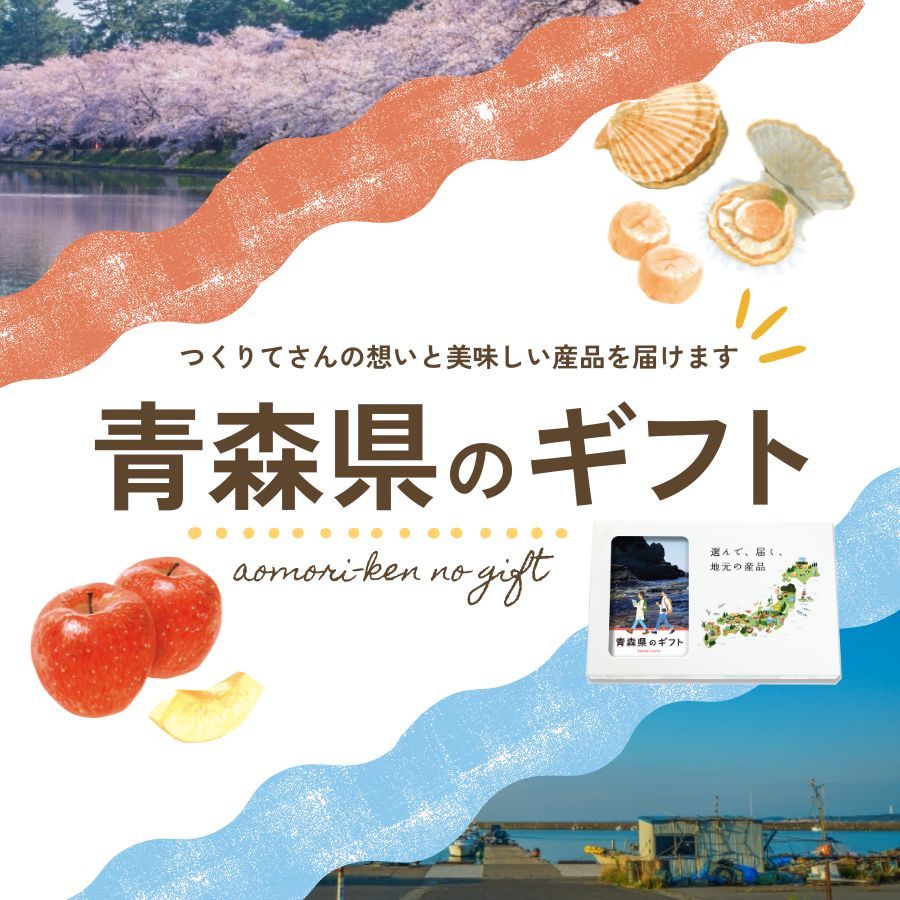**この記事はAIを用いて作成されています**
十和田バラ焼きは、約60年前に青森県三沢市で誕生し、牛バラ肉と大量のタマネギを醤油ベースの甘辛いタレで鉄板焼きにした十和田市民のソウルフードです。2014年のB-1グランプリで優勝を果たし、現在では十和田市内に約80店舗がこの郷土料理を提供している代表的なご当地グルメとなっています。
・
三沢米軍基地との歴史的関係
・
戦後まもない1945年、占領軍が三沢飛行場を接収し米軍基地として大規模な拡張工事を開始したことで、三沢の町は急激な人口増加を経験しました。基地内では米軍関係者向けにステーキ用の赤身肉が消費される一方、脂身の多いバラ肉やホルモンなどの部位は「払下げ」として市中に安価で流通するようになりました。当時の日本では牛肉を食べる習慣がまだ一般的ではなく高価な存在でしたが、この米軍基地からの払い下げ品により、三沢では比較的安く牛バラ肉が手に入るようになったのです。
基地建設に従事するため朝鮮半島から移住してきた労働者たちが、この安価なバラ肉を玉ねぎと組み合わせ、プルコギをヒントにした甘辛いタレで調理する方法を考案しました。1957年創業の「赤のれん」が発祥の店とされ、この料理は基地前に軒を並べる飲食店街で広まっていきました。三沢と十和田は1922年から鉄道で結ばれ人とモノの往来が盛んであったため、バラ焼きは自然な形で十和田市に伝播し、1958年には地元紙に「開店即好評!牛肉のバラ焼き」という広告が掲載されるほど定着していました。
・
赤のれんの発祥店物語
・
三沢基地ゲート前に佇む「赤のれん」は、1957年(昭和32年)にお好み焼き屋として創業した小さな食堂でした。大阪出身の先代店主が、お客からの要望で牛バラ肉と玉ねぎを鉄板で焼いて提供したところ大変好評となり、これを正式に「バラ焼き」としてメニュー化したのが現在のバラ焼きの始まりです。創業から67年が経つ現在も、店頭には堂々と「バラ焼き発祥の店」の看板を掲げ続けています。
興味深いのは、この老舗店が秘伝のタレの流出を防ぐため、アルバイトを一切雇わず一族経営を貫いていることです。長年使い続けている鉄器で焼き上げる元祖の味は、地元住民だけでなく全国からバラ焼きを求めて訪れる観光客にも愛されています。しかし皮肉にも、発祥店である三沢市よりも隣接する十和田市の方が「十和田バラ焼き」として全国的な知名度を獲得し、十和田商工会議所が「バラ焼き」を商標登録したことで両市の間で論争が生じているのが現状です。
・
プルコギからの調理法継承
・
朝鮮半島の代表的料理であるプルコギは、醤油ベースで甘口の下味をつけた薄切り牛肉を野菜と共に焼く料理で、「プル(불)」は火、「コギ(고기)」は肉を意味します。三沢の朝鮮系住民たちは、このプルコギの調理技術を基盤として、米軍払い下げの牛バラ肉を活用した独自の料理を開発しました。特に甘辛いタレによる味付けと、テーブル上での鉄板調理というスタイルは、明らかにプルコギの影響を受けた調理法でした。
しかし現在のバラ焼きは、プルコギとは異なる独自の進化を遂げています。プルコギが多様な野菜や春雨を使用し、専用のプルコギパンで調理されるのに対し、バラ焼きは玉ねぎを大量に使用し平らな鉄板で焼くシンプルな調理法を確立しました。またプルコギでは牛ロースやヒレなどの赤身肉が主流ですが、バラ焼きは脂身の多い牛バラ肉特有の旨味を活かした調理法として発達し、現在では青森県独自の郷土料理として確固たる地位を築いています。