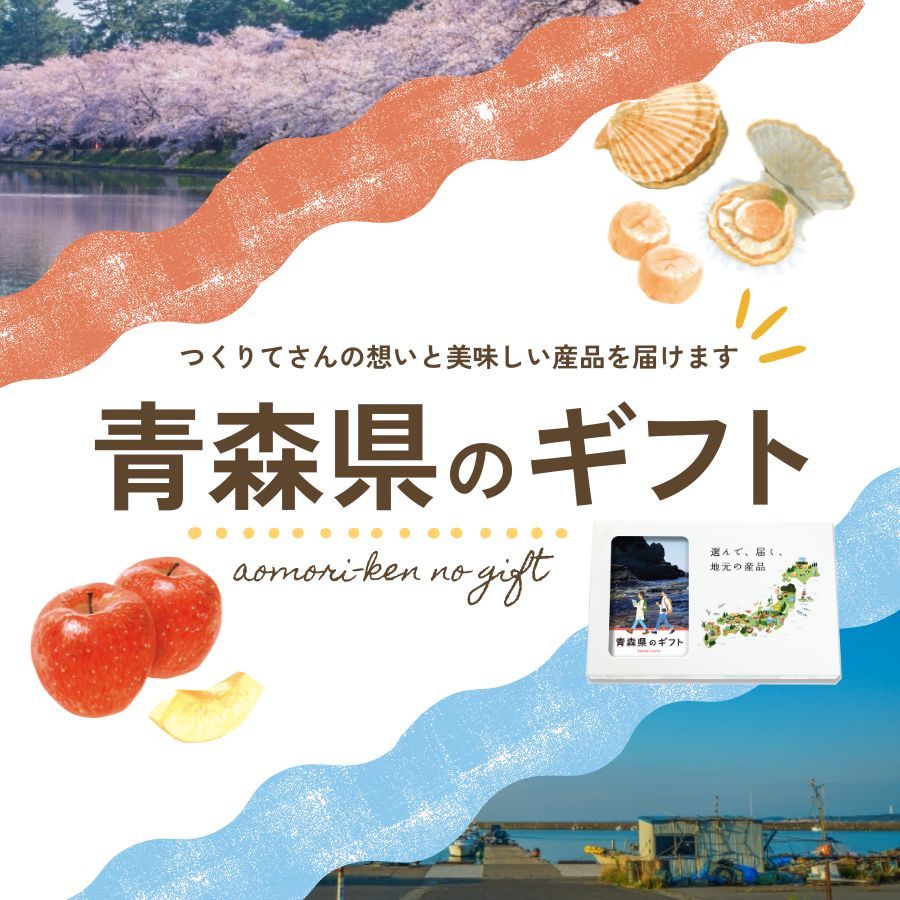弘前城の天守が小さい主な理由は、元々五層あった大天守が火災で焼失し、その後の再建が江戸幕府の築城規制によって大規模にできなかったため、やむなく三層の小型天守が建てられたためです。
弘前城は1611年、津軽氏によって当初は五層の大天守を持つ立派な城として築かれました。
1627年に落雷による火災で五層天守が焼失し、その後長らく天守は存在しませんでした。
江戸時代、幕府は大名の力を抑えるため「武家諸法度」などの法令で天守新築や再建を厳しく制限していました。
再建が許されたのは1810年(文化7年)で、この際も天守の新築ではなく「櫓の改築」という名目で許可を得る形をとり、「辰巳櫓」(御三階櫓)を三層天守として建てました。
新たに建てられた三層天守は、高さ約14.4メートルで、姫路城(約31.5m)や名古屋城(約36m)など他の有名城と比べて半分以下の規模です。
幕府の目をごまかすため、外観を装飾的に見せたり、内側は簡素に造る、各層ごとに小さくする設計上の工夫もなされました。
現在の弘前城の天守は、もともとの五層天守を規模縮小し、櫓を転用・改築したものゆえに小さいのです。
弘前城の城郭全体の規模自体は、東北地方としては非常に広大で本丸・石垣・城下町を含めた大きな城ですが、天守のみが小さいという特徴があります。
このように、歴史的経緯(火災による焼失)と、江戸幕府の築城規制という政治的要請が、弘前城の天守の小ささの直接的な理由となっています。
kaoru_0218郁(かおる) 土手の珈琲屋 万茶ンの新店主
元タクシー運転手のコスプレイヤー七々子ちゃんと同一人物
《インスタグラム》 《X》 《Youtube》 《ティックトック》
・