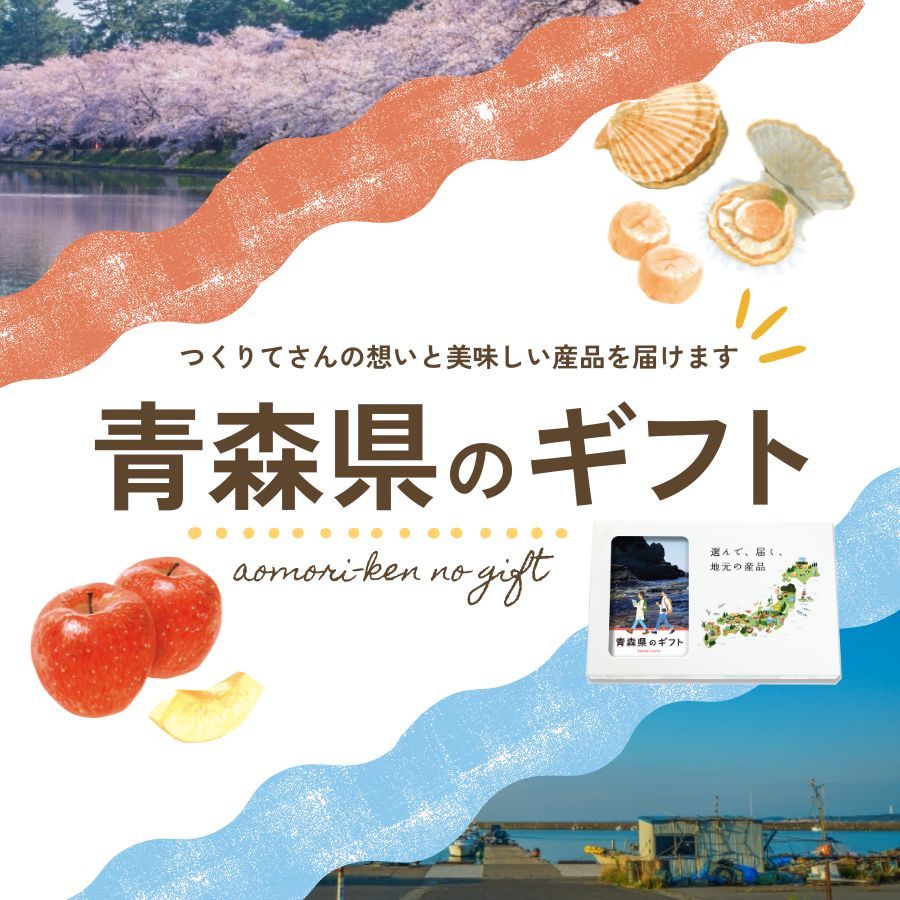**この記事はAIを用いて作成されています**
青森県八戸市の中心商店街を舞台に、1951年から続く伝統行事「八戸七夕まつり」が2025年7月18日から20日にかけて開催され、色鮮やかな七夕飾りの展示や八戸小唄流し踊り、路上イベントなど多彩なプログラムが楽しめる夏の風物詩として、約40万人の来場者を迎える予定です。
・
彩り豊かな祭典
・
八戸七夕まつりの期間中、三日町・十三日町の路上は歩行者天国となり、市民や企業が製作した色鮮やかな七夕飾りが街を彩ります。十三日町交差点に設置される特設セットの「七夕やぐら」は夜になるとライトアップされ、幻想的な雰囲気を醸し出す撮影スポットとなります。会場内には47社からの協賛広告飾り55個と18団体からの自主製作飾り81個が展示され、はっちひろばにも20団体から22個の七夕飾りが飾られます。
期間中は多彩なイベントも開催されます。初日には「第55回八戸小唄流し踊り」が行われ、昨年は14団体約600人が目抜き通りとマチニワで踊りを披露しました。また、はっちでは「七夕茶会」や「七夕お抹茶カフェ」が催され、家族連れが楽しめる「まるごとこどもはっち夏祭り」も実施されます。夜には飾りがライトアップされ、浴衣での散策にもぴったりな夏の風物詩として、多くの来場者で賑わいます。
・
八戸小唄流し踊りの歴史
・
八戸小唄流し踊りは、1971年(昭和46年)に八戸小唄の誕生を記念して始まった伝統行事です。元々の八戸小唄は、1931年(昭和6年)に当時の神田重雄市長が「八戸市を紹介したい」という思いから、東京日日新聞社主催の座談会で提案したのがきっかけで誕生しました。民謡調の曲にしたのは「今流行りの新曲は長持ちしない」という神田市長の希望によるもので、法師浜桜白が作詞、後藤桃水が作曲を担当しました。
当初の八戸小唄は座敷踊りでしたが、1953年(昭和28年)に「正調八戸小唄保存会」が設立され、屋外で踊れるよう行進用の踊りが新たに考案されました。この流し踊りは八戸七夕まつりの幕開けを飾る行事として定着し、現在では約800人の踊り手が白地にカモメ柄をあしらった浴衣姿で市中心街を踊り歩く華やかな光景が見られます。全国的にも評価が高く、日本三大流し踊りの一つとしても知られています。
・
中心商店街の変遷
・
八戸市中心商店街は約370年前の藩政時代から青森県南部地方の商業中心地として発展してきました。三日町商店街は大正14年に「三日町銀座三栄会」として組織化され、夜店や歩行者天国など独自のイベントを開催していました。昭和43年には三日町に丸光(現さくら野)と緑屋(現レック)の両デパートが同時オープンし、青森県南部と岩手県北を含む66万人の広域商圏が形成され、中心街は活況を呈しました。
しかし平成に入ると中心街は斜陽化し始めます。1989年に歩行者通行量がピークを迎えた後、車社会への対応の遅れから渋滞や駐車場不足が深刻化。1990年代には商業施設の郊外化が進み、1990年に長崎屋が移転してラピアSCが開業し、1995年には隣接自治体にイオン下田SCがオープン。さらに1994年の三陸はるか沖地震で市民病院が郊外移転したことも街の来訪者減少に拍車をかけました。現在は「はちまち」などのメディアを通じた情報発信や「みろく横丁」の設置など、中心街活性化に向けた取り組みが続けられています。