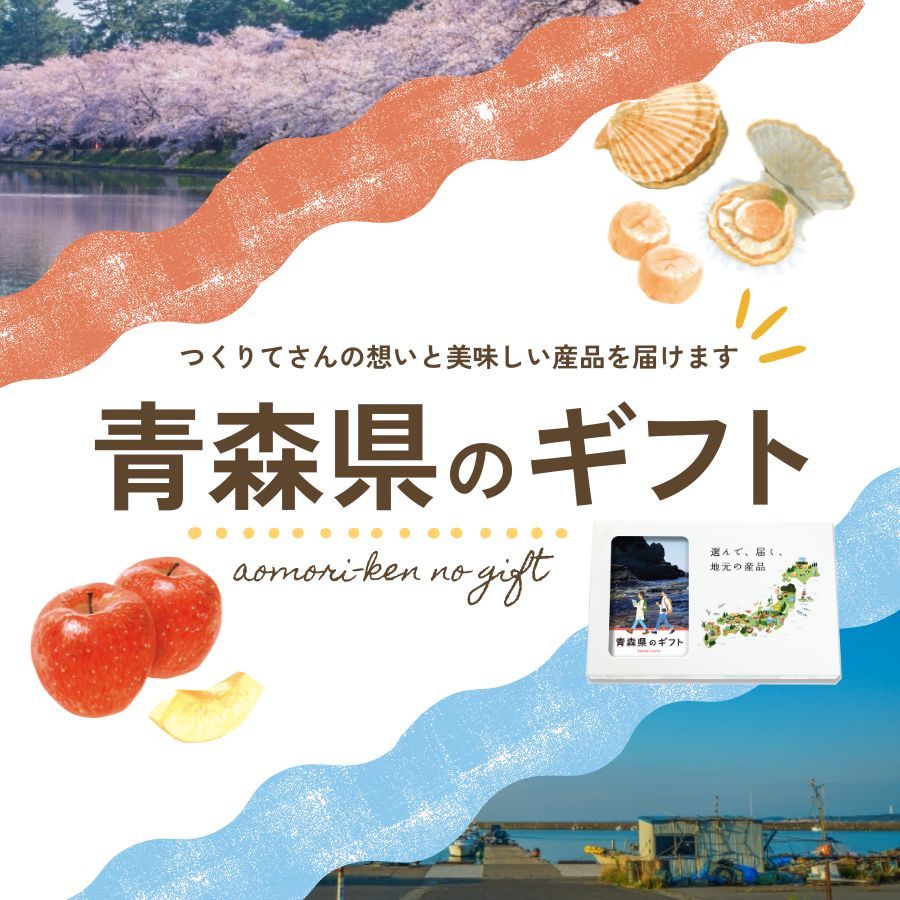**この記事はAIを用いて作成されています**
**画像出典:農林水産省「うちの郷土料理」**
豆しとぎは、青森県南部地方や岩手県北部で親しまれている伝統的な郷土菓子で、潰した青大豆や黒豆に米粉と砂糖を混ぜて練り上げた素朴な味わいが特徴です。かつては神様へのお供え物として作られていましたが、現在ではそのまま食べたり、焼いて香ばしさを楽しんだりする郷土の味として愛されています。
・
南部地方の伝統菓子
・
南部地方は古くからやませによる稲作の冷害に悩まされていたため、小麦、あわ、ひえ、蕎麦などの穀物栽培が盛んでした1。この地域特有の気候風土から生まれた伝統菓子には、「べこもち」や「きんか餅」などがあります。きんか餅は南部藩の三戸町発祥のお盆のお供え菓子で、小麦粉で作った餅の中に黒砂糖、くるみ、ごま、味噌で作ったあんを入れて蒸したもので、「きんか」は高価な食材を使うことから「金貨」や「金華」を表すといわれています2。
南部地方を代表する菓子として「南部せんべい」も有名です。米や小麦を主原料に、醤油や砂糖、干し貝柱などを加えて焼き上げた、コリコリとした歯ごたえと素朴な味わいが特徴3で、基本の「しおせんべい」に加え、胡麻や落花生を加えた「ごませんべい」と「まめせんべい」が定番です4。近年では伝統と革新が融合した「チョコ南部」や、南部菱刺しをモチーフにした琥珀糖「八戸きらり」など、地元食材を活かした新しい菓子も生まれています56。
・
青大豆と米粉の配合
・
豆しとぎの基本的な材料は青大豆と米粉ですが、その配合比率は地域や家庭によって異なります。一般的には青大豆を一晩水に浸してふやかし、塩を加えて固めにゆでた後、粗くすりつぶします12。米粉については、うるち粉だけを使う場合と、うるち粉ともち粉を組み合わせる場合があります。青森県の伝統的なレシピでは、50人分の場合、青大豆と合わせ粉(うるち粉ともち粉)を混ぜて使用します1。岩手県九戸村の「食の匠」小野寺ツギさんのレシピでは、青大豆200gに対して米粉(うるち)150gの割合で配合しています3。
豆しとぎの食感と風味を左右する重要なポイントは、青大豆のゆで加減と粒子の残し方です。ゆで方が足りないと生臭くなり、ゆですぎると軟らかくなって色も悪くなります3。すりつぶす際は完全になめらかにするのではなく、1mm程度の粒が残る程度に粗くつぶすのが一般的です3。また、青大豆の青臭さが苦手な人向けには、ごまを加えることで風味が増し、若い世代にも好まれるようになります1。現代のアレンジレシピでは、ヨーグルトを加えてさっぱりとした風味にする工夫も見られます4。
・
神様への供物としての歴史
・
「しとぎ」は本来、水で柔らかくした米をつぶし、こねて団子状にした食物で、現在の餅の原型とも言われ、古くから全国で神前のお供え物として重要な役割を果たしていました12。南部地方では冷害に見舞われることが多く、米が貴重だったため、大豆を加えて作られるようになり「豆しとぎ」と呼ばれるようになりました34。
青森県では12月に入ると「神様の年取り」と呼ばれる行事が連日のように行われ、3日に稲荷様、5日にえびす様、7日に天王様、9日に大黒様、12日に山の神様といった具合に神々を祀りました45。南部地方ではこの際の主なお供え物として「豆しとぎ」を用い、一年のご加護に感謝し、新しい年の平安を祈りました4。岩手県北部でも同様に、12月9日の大黒様、12月19日の蒼前様(馬の神)の年取りの供え物として使われ、特に12月12日の山の神の年取りの晩には12個を供えることから「十二しとぎ」とも呼ばれていました1。また、春先にはうぐいすを呼ぶものとしても作られていました67。