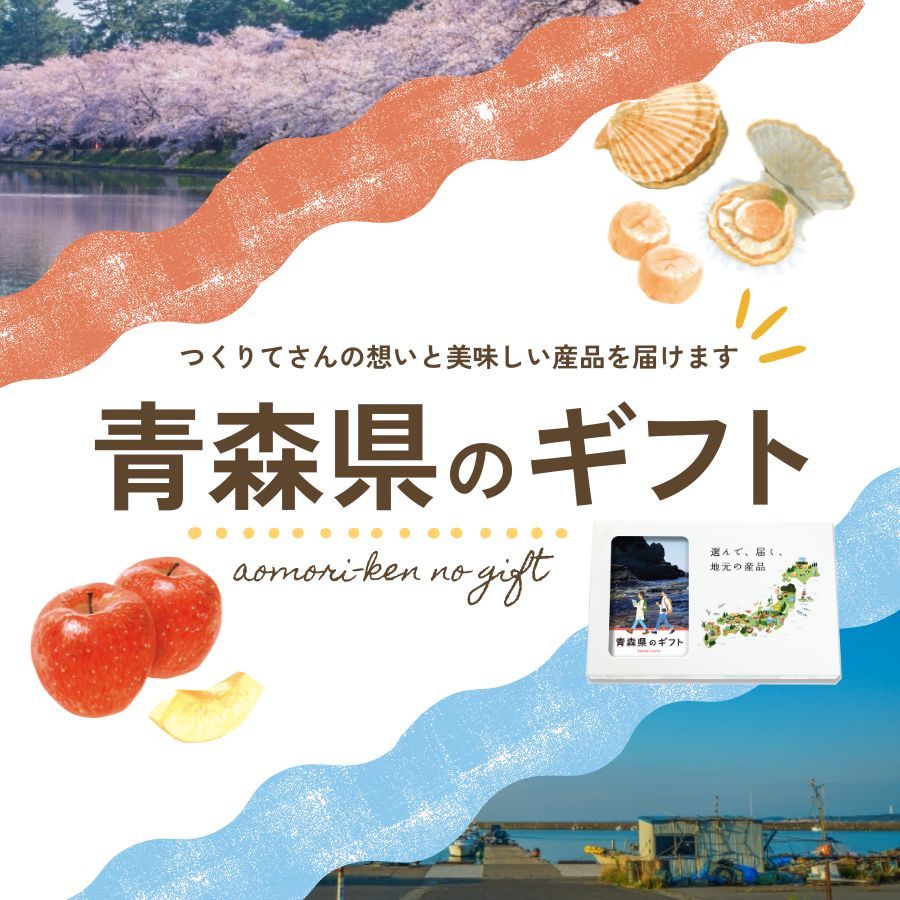**この記事はAIを用いて作成されています**
津軽地方の伝統和菓子「甘露梅」や「干梅」は、あんを求肥で包み、赤紫蘇の葉で巻いた「梅干菓子」として長く愛されており、五所川原市金木地区の「甘露梅」は黒あんを使用し太宰治のふるさとの銘菓として、黒石市の「干梅」は白あんを用いた郷土菓子として、それぞれ独自の風味と歴史を持っています。
・
津軽の梅干し文化
・
津軽地方の「梅干し」は一般的な丸い梅干しとは異なり、梅や杏の実を割って種を取り、大きな赤紫蘇の葉で包んだ「しそ巻梅漬け」が特徴です12。この独特の食文化は、津軽氏四代藩主信政(1646~1710)が大浦村(旧岩木町)に梅や杏などの実のなる木を植えさせたことに始まり3、以来、種を除いた梅や杏の塩漬けを紫蘇で巻くという伝統が根付きました4。
津軽では梅を「め」や「めっコ」と呼び、杏は「杏梅(あんずめ)」と呼ばれ区別なく扱われてきました3。各家庭で作られる「しそ巻梅漬け」は、家によって塩だけで漬けるもの、実を割って種を除いてから漬けるものなど様々な製法があり5、豪雪地帯の冬の手仕事として津軽の女性たちによって受け継がれてきました6。現在でも100年以上の歴史を持つ老舗「いした」などが伝統製法を守りながら、手作業でひとつひとつ丁寧に作り続けています16。
・
皇族尼僧の命名
・
金木町(現五所川原市)の虎屋が製造していた梅干菓子は、1907年(明治40年)頃に創製されましたが、その菓子名を「甘露梅」と改めさせたのは皇族出身の村雲日栄尼でした1。村雲日栄尼は京都瑞龍寺の門跡となり、虎屋では「村雲御門御用達」の看板を掲げ、京都瑞龍寺へ甘露梅を納品する栄誉を得ていました1。同様に、黒石町(現黒石市)の松葉堂まつむらの「干梅」も1915年(大正4年)に津軽地方で行われた陸軍特別大演習の際に宮内省(現宮内庁)が買い上げた逸品であり、その後は県当局を経由せずに宮内省へ直接納入される特別な地位を獲得しました1。
これらの梅干菓子は、炎暑で腐敗や味が劣化しないよう工夫を施された実用的な菓子であり、東京のデパートで開催される菓子陳列会や札幌、小樽の県立物産館など県外へも出品されるほど評価されていました1。弘前市の開雲堂の「干乃梅」は閉店したので味わえませんが、現在でも金木町内では甘露梅を製造販売しており、津軽地方を代表する郷土菓子として受け継がれています1。
・
松しま菓子司の伝統製法
・
五所川原市金木町に1960年11月に開業した「御菓子司 松しま」は、約65年にわたり津軽の銘菓「甘露梅」を守り続けてきました。この伝統菓子は国産小豆で作られた黒あんと求肥を、塩と砂糖に漬けた赤紫蘇で正方形に包んだもので、あんと餅の優しい甘みの後に塩味と爽やかな酸味が広がる独特の味わいが特徴です1。
2024年2月28日に惜しまれながら閉店した「松しま」ですが、その伝統の味は地域の思いによって守られることになりました。同店の斜め向かいにあるコミュニティスペース「KADOKKO」が、約20年勤務していた菓子職人の協力を得て甘露梅の製造・販売を引き継ぎ12、金木観光物産館「産直メロス」でも購入できるようになっています。松島瞭子さん(90)が長年守ってきた伝統の味は、地域の宝として次の世代へと受け継がれていくことになりました34。