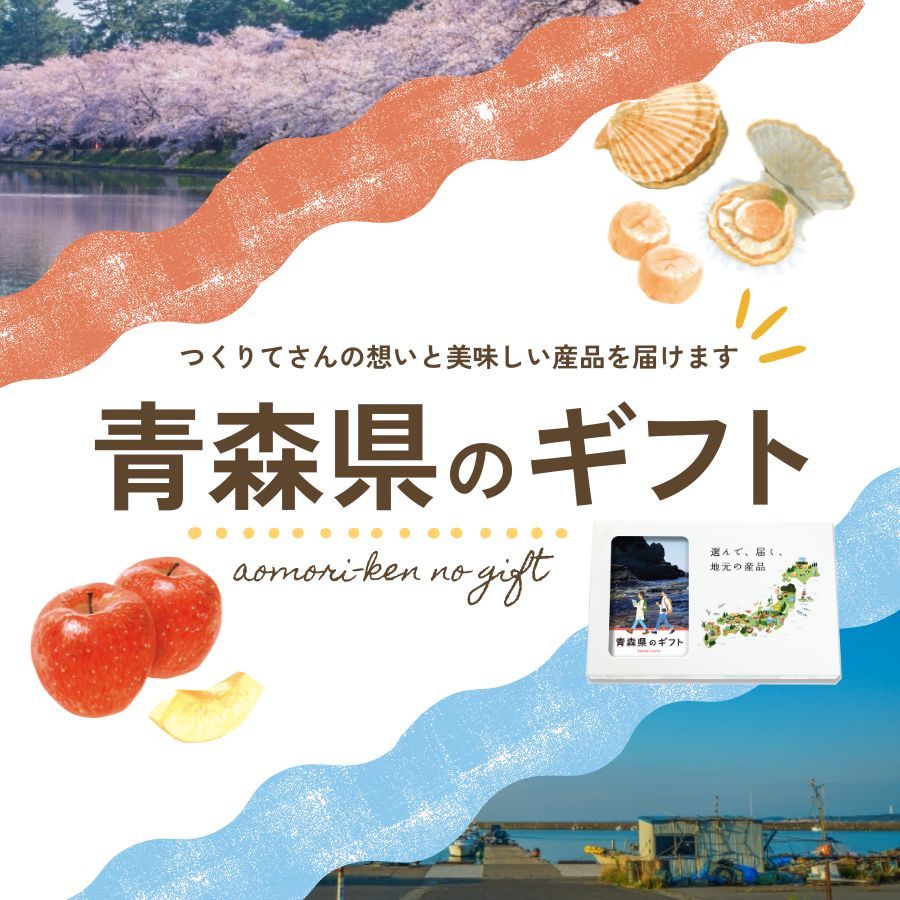青森県の南部地方で、昔から家庭の味として親しまれてきた「ひっつみ」。
小麦粉をこねた生地を手でちぎって鍋に入れる、素朴ながらも奥深い一椀です。寒さが厳しい季節になると食卓に登場することも多く、「これを食べると落ち着く」という地元の声も少なくありません。この記事では、青森の郷土グルメ「ひっつみ」の特徴や名前の由来、八戸せんべい汁との違いなどを紹介します。
・
ひっつみとは? 青森南部の粉もの郷土料理
ひっつみは、小麦粉を水でこねて寝かせた生地を、手でつまんで引き伸ばしながらちぎり、具だくさんの汁物に入れて煮込んだ料理です。
具材や味付けは家庭や地域によってさまざまですが、青森南部では次のようなスタイルがよく見られます。
出汁:鶏ガラ、骨付き鶏肉、昆布など
具材:鶏肉、ごぼう、にんじん、長ねぎ、きのこ類 など
味付け:しょうゆをベースに、酒やみりんを少し加えることが多い
見た目は「すいとん」に近いですが、生地をしっかり寝かせてから手で伸ばして入れるため、もっちり&つるんとした独特の食感が楽しめます。
・
「ひっつみ」という名前の由来
「ひっつみ」という名前は、
生地を手で“ひっつむ(ひきつまむ)”という方言からきていると言われています。
生地を「ひっつむ」
ちぎった生地を、そのまま鍋に入れて煮込む
という工程そのものが、そのまま料理名になった、生活に根ざしたネーミングです。
・
青森とひっつみの関係
ひっつみが親しまれているのは、青森県南東部〜岩手県北部にかけての旧南部藩エリアです。
青森県内では特に、
八戸市周辺
三戸郡(三戸町・南部町・五戸町など)のまち
といった南部地方で、日常のごはんから来客時の一品まで、幅広い場面で作られてきました。
米作りが今ほど安定していなかった時代、冷涼な気候に合う小麦や雑穀を活用する「粉もの文化」の一つとして、ひっつみが受け継がれてきたとされています。
・
どんな場面で食べられてきた?
かつては、主食代わりの一品として日常的に食べられていました。
現在でも、こんなシーンで登場することが多い郷土料理です。
冬場のあったかメニューとして家族団らんの食卓に
お盆や祭りのあと、親戚が集まる場での“ごちそう鍋”
学校給食や地域のイベントで出される「郷土料理メニュー」
具材を多めに入れれば一椀で満足感があり、野菜もとれることから、今も家庭料理として根強い人気があります。
・
八戸せんべい汁との違い
・
青森南部の鍋料理といえば、八戸せんべい汁も有名です。
同じく汁物なので混同されがちですが、使う「主役」が異なります。
ひっつみ:小麦粉をこねた“生地”をちぎって入れる
せんべい汁:専用の「南部せんべい」を割り入れて煮込む
どちらも鶏肉や野菜がたっぷり入り、しょうゆベースの出汁で煮込む点は似ていますが、食感と香りがまったく違うのがポイントです。
ひっつみ:もちもち・つるっとした口当たり
せんべい汁:スープを吸ったせんべいが、ふやふや&モチモチの独特な食感に
同じ南部地域の鍋料理でも、「今日はひっつみ」「今日はせんべい汁」と気分で食べ分ける家庭もあります。
・
まとめ:一椀で“南部の暮らし”を感じる郷土グルメ
・
ひっつみは、青森県南部地方で親しまれてきた、小麦粉の生地を使った郷土料理
もっちりとした生地と、鶏出汁や野菜のうまみが合わさった、素朴であったかい一椀
八戸せんべい汁と並び、南部地域の「粉もの文化」を今に伝える存在
青森を訪れた際は、八戸せんべい汁だけでなく「ひっつみ」にもぜひ注目してみてください。
家庭やお店ごとに違う味わいから、南部地方の暮らしや歴史が見えてくるかもしれません。