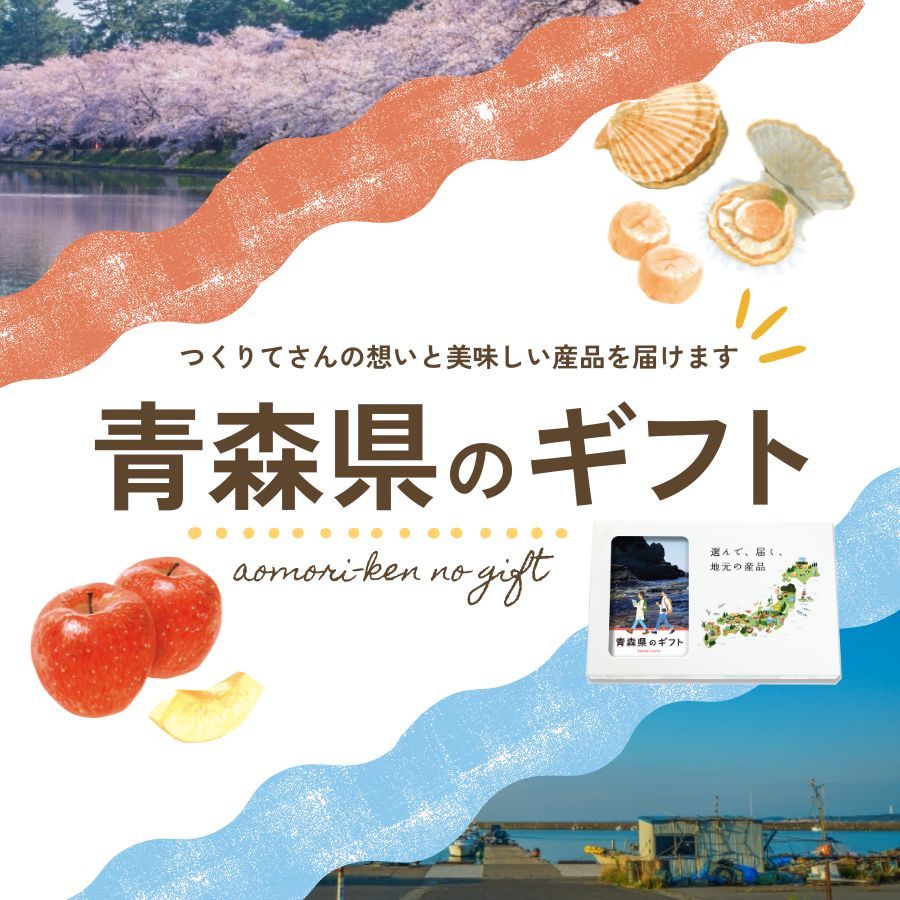**この記事はAIを用いて作成されています**
八戸せんべい汁は、青森県八戸市周辺で江戸時代から200年以上食べ継がれている伝統的な郷土料理で、汁物専用の南部煎餅を醤油ベースのだし汁に割り入れて煮込む独特な鍋料理です。2012年にB-1グランプリでゴールドグランプリを獲得し、今では全国的に知られるご当地グルメとして、年間数百億円の経済波及効果をもたらしています。
・
江戸時代からの200年の歴史
・
この郷土料理の起源は、江戸時代後期の天保の大飢饉(1833-1839年)の頃に八戸藩内で生まれたとされています。当時の人々が厳しい飢饉を乗り切るために、保存の利く南部煎餅を汁物に活用したのが始まりと考えられており、決して祝いの席のごちそうでも、もてなしの料理でもありませんでした。その後200年余りにわたって現在の南部地方一帯で食べられ続け、八戸市を中心とした青森県南から岩手県北の一部地域では、日常的な家庭料理として定着してきました。
東北地方太平洋側北中部では、冷夏をもたらすやませに悩まされており、特に江戸時代の小氷期には深刻な食糧不足に見舞われていました。そうした厳しい環境の中で、栄養価が高く保存性に優れた南部煎餅を汁物として活用する知恵が生まれ、地域の人々の命を支える重要な食文化として根付いていったのです。
・
南部せんべいの独特な食感
・
南部せんべいは小麦粉を原料として作られており、米が獲れない時期の非常食として昔から重宝されてきた保存食です。この小麦ベースの煎餅は、汁物に入れることで独特の食感変化を見せます。
煮込み始めは硬い煎餅が徐々にだし汁を吸収し、外側は適度な歯ごたえを残しながら内側はもちもちとした食感に変わっていきます。完全に柔らかくなるまで煮込まず、程よい弾力を残した状態で食べるのが八戸流で、この絶妙な食感のバランスこそが他の地域の汁物では味わえない南部せんべい汁の最大の魅力となっています。煎餅が汁を吸うことで旨味も凝縮され、噛むたびにだしの風味が口の中に広がる独特な味わいを生み出します。
・
鶏だし醤油系の基本レシピ
・
基本的な八戸せんべい汁は、鶏もも肉で旨味を出し、醤油ベースの優しい味付けで仕上げる家庭料理です。鶏肉100-200gを一口大に切って炒め、ささがきにしたごぼうと人参、細切りのしいたけ、ざく切りのキャベツなどの根菜類を加えて炒めます。水1-1.6リットルに和風だしの素を入れて煮立て、薄口醤油大さじ2-4、みりん、日本酒で調味した後、専用の南部せんべい8-10枚を3-4等分に割って投入し、4-5分程度煮込んで完成です。
地元八戸では煮干しだしと菜種油を使うことが多く、これにより味に深みが増すとされています。材料は季節に応じて糸こんにゃくやしめじなどのきのこ類を加えることもあり、最後に斜め切りの長ネギを散らして彩りと風味をプラスします。調理時間は約30分で、費用も500円前後と経済的な点も魅力の一つです。